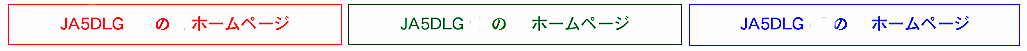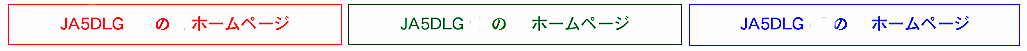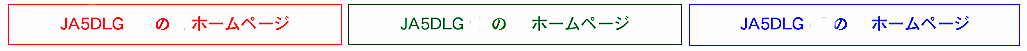|
| 栗田 樗堂 (くりた ちょどう) (寛延二年(1749)・8・21~文化十一年(1814)・8・21 65歳)) |
|
| 松山市松前町酒造業豊後屋後藤昌信の三男として生れる。 |
|
本名 政範、通称 貞蔵、俳号は、はじめ  (えんしつ)室
・ 蘭之(らんし)、のち 息陰・ 樗堂 と改めた。 (えんしつ)室
・ 蘭之(らんし)、のち 息陰・ 樗堂 と改めた。 |
|
| 「荘子」の「樗」の寓話を引用して俳号を改める。 樗→役に立たない大木→人間の名利(欲)の世界を離れた存在という意味☆荘子の理想 樗の大樹の木陰でゆっくりと休息しながら、自然に暮らす→「息陰」→「樗堂」 |
|
| 樗堂が目指した俳諧空間 |
|
| 樗堂という号は「無用の大木、樗」にちなんだものであり、息陰という別号もまた、樗の木陰で憩うという意味をもつものです。また庚申庵に掛けられていた-「追善集無益 塚しるし無益 追善会無益」という言葉にも、樗堂の名利を捨てて風雅の誠を求めた生き方をしたいとの思いが込められています。それは、「庚申庵記」の末尾の句-「よしもなき名はただ曇れ秋の月」に吐露した思いでもあったのです。 |
|
| 同町内酒造家廉屋(かどや)こと栗田家に人夫し、七代目与三左衛門(よそうざえもん)専助と称し、五代目与三左衛門政恒(俳号・天山)が初代二畳庵を興したのをついで、二畳庵を再興した。 栗田家は松山きっての造り酒屋で、近年まで、その銘酒「全世界長」・「白玉」・「呉竹」の名は有名で、他店の酒より値もよかったという。敷地は約700坪、総建坪852坪、酒倉は、33間×4間の総2階建、敷地の南は樽干し場になっていた。 樗堂は、家業の酒造業で大をなした外に、明和8年(一七七一)より大年寄役見習、大年寄、大年寄格となり、享和2年(一八〇二)53歳の時、病のため辞したが、その間、大年寄であること通算20数年に及んだことでも、彼の人柄と人望のほどがうかがわれる。 又一面、俳諧に親しんで、天明6年(一七八六)、当時の全国諸芸の達人を示した書『名人異類鑑』に38歳の樗堂は、早くも「俳諧上々、廉屋三左衛門」としるされている。天明7年、京都に上り、加藤暁台(きょうたい)に学び、近世伊予第一の俳人といわれた。樗堂の句風は、上品で美しく、おだやかでわかりやすく、しかも俗におちいらず、荘重であることは人の認めるとこ
ろである。小林一茶は、その師竹阿の旅の跡をたどり、寛政7年(一七九五)と翌年と二度、樗堂の二畳庵を訪ねており、名古屋の同門の井上士朗も、親交があり、彼を訪ねて来ている。 彼は妻・虎女(とらじょ)こと羅蝶(らちょう)とともに、真宗篤信の徒であったというが、寛政12年(一八〇〇)(庚申(かのえさる)の年)、松山城の西、味酒の地に、「古庚申(ふるこうしん)」と称する青面金剛をまつる祠の近くに、その年の「えと」と祠の名に因んで「庚申庵」を建て、風雅の生活を楽しみ、『庚申庵記』を書いた。 寛政1年(一七八九)妻羅蝶の没後、安芸(広島県)三原藩の宇都宮氏より後妻を迎えた縁で、安芸の国御手洗(みたらい)島(大崎下島)へうつり、ここにも二畳庵をいとなんで「盥江(かんこう)老漁」と自ら称し、没するまでの約10年間、殆ど、この地に過した。 |
|
| 一畳は浮世の欲や二畳庵 樗堂 |
|
| 「庚申庵」は戦災を免れ、県指定の史跡となっており、『庚申庵記』も同庵にある。『樗堂俳諧集』、『萍窓集』、『石耕集』などがある。墓は市内萱町得法寺と広島県御手洗島にある。 |
|
| 庚申庵は、寛政十二庚申年、樗堂52歳の時、松山城の西方味酒郷、俗に「古庚申」と称する青面金剛を安置する祠の近くに建てたもので、干支と祠と相応じて「庚申庵」となづけました。樗堂はそこで名利を捨てた市中の隠の境地を楽しむことを望みましたが、名利の煩わしさに引き戻そうとする松山藩に対して、強い抗議の思いを表したのが、入庵後五年を経た文化二年に書かれた 「庚申庵記」です。御手洗島へ旅立つ決意を秘め、理想の境と現実との落差に心痛める樗堂の姿が読み取れます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庚申庵記 |
|
| 我すむ坤のかた、市塵わづかに隔 |
|
| たりて平蕪の地あり。味酒の郷と |
|
| 言。寛政庚中の年、いさヽか其地 |
|
| を求得て、かたばかりなる六の |
|
| 草屋をつくり、陸ろ廬が好事の茶を |
|
| 煮ために小庇をつけたり。 |
|
| 此ほとり、もと青面金剛の安・・・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 「俳句の里 松山」 平成6年松山市教育委員会編 |
|