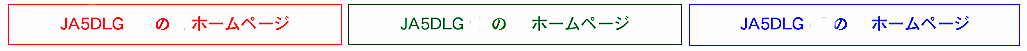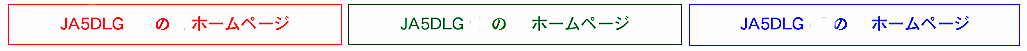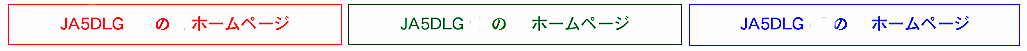「見たか町衆」 上田雅一著 「寛政歌仙」
小林一茶と樗堂と羅蝶・・・(斜字は勝岡 昭(JA5DLG)の注)
あの非情な、信州信濃のからっ風とは大違い、さすが南国伊予は暖かい。
田んぼの藁(わら)ぐろは蒸(む)れて臭うし、踏み歩く畦道(あぜみち)も、足裏に土が温い。
水藻(も)ゆらぐ溝(みぞ)川(みぞ)にも、異郷のささやきを聴く新鮮さがあった。
川辺に晒(さら)された破れ凧は、狂い舞った未、捨てられたものか。
汚れた紙の太文字は、表裏の別なく読めた。「其因?」
其因、俳号かな?。あまり聞き馴れぬ名だ。
昨今、隆盛をきわめるこの土地の俳諧(はいかい)でもあろうか。
町家の屋根が銀鼠色に光る。
点在する稲叢(いなむら)がくれに見える町場、タガを打つ桶屋の単調音に、荷商いの売り声が重なる。
わが行く手に、黄の花かと紛(まご)う女人の影、歳は二八か、にくからず、互いの距離はそれほどまでに迫っていた。
避けて通す脇道もなし、ままよと歩を運ぶ。直視の無礼もならず、伏せた視野に唐桟(とうざん)の竪(たて)縞がゆれた。
【唐桟】とう‐ざん タウ
(「桟」は桟留(サントメ)の略) 細番の諸撚(モロヨリ)綿糸で平織にした雅趣ある縞織物。紺地に浅葱(アサキ)゙・赤などの色合を細い竪縞に配し、通人が羽織・着物などに愛用。和製の桟留縞に対してオランダ人によって舶来されたものの称であったが、現在は桟留縞の総称。 |
「御免」
畝(うね)に、足踏みこんで相手を通すと、脂粉が鼻腔をくすぐつた。異性の容貌(ようぼう)をいちべつ、佳麗(かれい)なひとと見た。
片や、女の方は違う。
薄汚れの乞食坊主に道をゆずられて、一瞬、いやらしい男の体臭に加え、不快きわまる腐敗臭に失心するばかり顰蹙(ひんしゅく)した。
大気が拡散したものの、暫くは悪臭の記憶に気色悪く、たもとで顔を覆うと、その場を急ぎ逃げた。
一茶は、筆を噛み手帳をひらく。
帳の上下、綴じ部分をよけて帳の中ほどにあけた穴に墨つぼが納まる工夫。
手帳をクセのある字が走った。
春風に大あくぴする美人哉
正月十三日・槌x(樋)口村(ひぐちむら)などいえる所を過て軋て七里となん、風早灘波村、茶来を尋ね訪い侍りけるに、すでに十五年あとに死きとや。後住西明寺に宿り乞うに許されず。(江戸から)三百里、ただ彼(茶来)を力にと来つるなれば、よるよすが(縁)もなく(途方にくれる)。
朧おぽろ踏めば水なり迷い道
百歩ほどにして五井(俳人姓高橋)を尋ね当て、やすやすと宿りて、
月朧よき門探り当てたるぞ
十四日、十丁ほどで八反地村兎文宅(姓門田)に泊る。
門前や何万石の遠がすみ
歌仙、満巻。
十五日松山二畳庵(に到り、翌十六日山越の孝子桜を訪ねる)。 寛政七年紀行。( )内筆者注。
| 高橋五井(ごせい) 江戸時代の著名な俳人。小林一茶は寛政7年(1795)伊予路に来遊し、1月12日行きくれて、さまよい歩くうち、高橋五井に温かく迎えられて一夜を過ごした。五井は高橋伝右衛門の号。 |
青ものの振り売りの声が、松前半町を抜け、南古萱町の通りにまわった。
「ねぎにかぶ菜、大根(だいこ)や にんじンー おいりんかァー(いりませんか?)」
天秤の撓(しな)り塩梅で、荷の軽重は分かった。商いは芳しくないらしい。
足を棒にし、声をからしても、手を打って呼ぶ家はなかった。
羽振りのよい二代目孫六は、先代からの米穀商に加え、並びに建増した家に質屋ののれん(暖簾)をかけていた。
小つるは同じ我が家ながら、米屋の店に入った。
枡が重なった箱台の脇を抜け、糠(ぬか)の積った敷居をまたぐ。
裾をはらった拍子に、柩(かまち)にもたせてあった杖が、ころりと土間に倒れた。
奥の聞から、屈託ない常さんの声がひびく。
黒光りした杖をとりあげ、片隅に立てかけた。小つるは、常さんのあの話ぶりが、目の見えぬ人とは思えないとおかしかった。
「お帰りたかなもし」(帰られましたか)
父に帰宅を告げた彼女へ、応じたのは常さんであった。
居間に入ると脱いだ着物をばっとひろげ、衽(おくみ)をあわせ、裾をそろえた。
| 【衽・袵】お‐くみ (オオクビ(大領)の約転) 和服で、前の左右にあって、上は襟(エリ)につづき下は褄(ツマ)に至る半幅の布。上交(ウワガイ)。 |
畦道(あぜみち)で出合った坊さん、あの嫌な臭いが移ってはいないかと唐柄の布地を見つめた。
「−松前町の二畳庵さんとこのお客さん、若いけんど(けれど)なかなかの俳譜師じゃいうことですのお−」
情報の運び屋でもある、あんま稼業の声が続く。
亡師竹阿の遺した手紙と、手控えの束をたよりに、関西を経巡る(へめぐる)一茶。
松山では樗堂のほか、唐入町の魚文らとも意気投合したし、温泉も気に入って長逗留(とうりゅう)となった。
江戸、上方の話題も豊富とあって、歓待を受け、歌仙を巻いての優雅な毎日が続いた。
もみ療の手も休めぬが、口も止らない常さんである。
そろそろ暮六つでもあろうか、雀色時(いろどき)はとっくに過ぎて、辺りは暗さを増していた。
【暮六つ】くれ‐むつ 夕暮の六つ時。今の午後6時頃。季節によって異なる。酉の刻。また、その時鳴らす鐘。
| 【雀色時】すずめ‐いろ‐どき 夕暮。日暮時。たそがれどき。 |
孫六は、心地よい まどろみ に落ちていた。
付け木の灯を、行灯(あんどん)にうつした小つるは、
「もう、暗うなってしもて」
銀屏に、ゆらぐ光が模様のように映り、その反射効果で障子襖も、布団柄も、明るい。
「もう、そないな時刻かいな」
体をひねった孫六は、常さんに下(しも)をと合図する。
「ほぉ−、こお−ばしい匂(にお)いじゃなもし」
焙じ茶の香が、たちこめた。
「ほてからなァ、あの一茶さんの話じゃけんど、わしもたいがい大分(だいぶ)の人におおとるんじゃが、あないな太い足、見たの始めてじゃ、何文ぐらいあるんかいなァ。
きしゃない話じゃけんど、こないだなんかなァ、あの足、こすっとったら、あんた、屁ひるんじゃけんな、それが臭うてなァ。旦那さんこらえてつかぁさい、こんなこというて」
孫六も、一茶の人となりは承知していた。人間くさい洒脱(しゃだつ)なお人らしい。
| 【洒脱】(しゃだつ)な 何げ無くふるまう言動や軽いタッチの文章・書画の中に人を引きつける脱俗の風格が感じ取られる様子。 |
できれば、お会いして話がして見たい、と思う。
固いマメのある平手が、ボンと腰を打った。常さんの仕事は終った。
彼の手もくたびれたが、口も疲れたろう。
熱い茶をすする常さんの耳に、仏間で打った鐘がひびいた。
孫六夫婦の合掌する仏壇には、この年の初めに亡くなった母小俊、五年まえ死んだ先妻清の霊位がある。
すっかり夜のとばりに包まれた戸外に出た常さんは、我とわが肩を交互にたたいてから、杖を地に這わせた。
辻行灯の明りのさきで蠢く(うごめく)黒い杖を、危うく、青物売りの朸(あふご)がよけると、米孫の質のれんを分けた。
| 【朸】おうご(アフゴ) 「物をかつぐ時に使う棒」の意の雅語的表現。おうこ。 |
数日の後。
砧を打つ響きが、風の強弱で遠く、近くと変わる。
| 【砧】きぬた 〔衣(キヌ)板の意〕 布のつやを出したり やわらかくしたり
するために布をのせて打つ△木(石)の台。また、それを打つこと。 |
常さんが二畳庵の枝折戸(しおりど)を、くぐつて、もはや小半刻は過ぎていた。
主人の意思など忖度(そんたく)なしに、いつもの調子で口角泡を飛ばす、
| 【忖度】そんたく ―する 「他人の気持をおしはかる」意の漢語的表現。 |
「あなた、らっしもない話じゃないかな。質草に、こともあろうに大根じゃの、ねぶか(ねぎ)じゃのをもって行ったいう話じゃけんどな」
その夜の米代はおろか、あけの日の仕入れにも事かき、万事窮した商人は、売れ残りの生野菜を質入れに来た。
これを哀れんだ米孫が幾何(いくばく/いくだ-幾許)かを用立てたまではよかった。
| 【幾何・幾許】いく‐だ 副 (助詞「も」を付けて打消に用いることが多い)
いくら。どれほど。なにほど。 |
| 【幾何・幾許】いくば‐く どれほど。どんなに多く。 (「も」を伴い、否定・反語に用いる)
なにほども。 |
口さがないのが世の常、
「米孫じゃあ、ネギや大根を質にとるんじゃと」
「ウットコ (自分のところ/自家)の一張羅に染(し)みつけたり、青物の臭いでもうつっとったらどうしてくれるんぞや」
「ニンジンで金貸すような質屋、ろくな店じゃないワイ」
世間の口に戸は立てられんのたとえ、これには孫六も閉口つかまつって候。
「質屋稼業はもう金輪際やめた。明日からは質入れ一切お断り、息子の其因だけじゃない、孫子の代までさされん」
心痛のあまり、当主は寝こんでしまうほどとなった。
「そりや大違いよ、人情うす紙の如き当節、こんな御奇特な話ごわせんぞ」
| 【奇特】きとく ―な ―に 志が深く、普通一般の人には行いがたい事を進んでする様子。 |
初耳の樗堂は、語調をたかめた。
「誰ぞ、やいと(お灸)すえよるんかや」
常さんは、話をそらした。
人肌を焼くもぐさの臭いが鼻をついた。
「一茶さんですよ、三里の灸をな」
「さよかや、やいとはようきくけんなもし」
寛政七年如月の夜は、月も沈んで、庵も、町も闇に包まれ、けだるい砧の音のみが、深更になっても続いていた。
| 【二日灸】ふつか‐きゅう キウ 陰暦2月2日と8月2日とにすえる灸。これをすると年中無病息災だという。ふつかやいと。 |
| 【如月・衣更着】きさらぎ (「生更ぎ」の意。草木の更生することをいう。着物をさらに重ね着る意とするのは誤り)
陰暦2月の異称。きぬさらぎ。 |
京の書肆、菊舎太兵衛をわずらわせ、半紙本「たびしうい」を、一茶は上梓。
餞別、路銀、出版費などの名目で厚志を受けた返礼に、この本を手土産にと再来した。
大かたは散りそめて花のさかり哉 樗堂
秋風や糊こわき衣の肌ざわり 魚文
夕涼み加茂河の水に任せたり
兎文
せめてもの報恩、各一句ずつを入集した「たびしうい」は、一茶の出版第一号であった。
○ ○
御城下良夜。発句仲間数人は、城内観月の会に招かれた。
その夜の献立は、城主、風流の趣向で、芭蕉月見の記録を忠実になぞって、
一、芋煮〆、のっペいしょうが。
一、煮物 こんにゃく、ごぼう、
里いも、木くらげ。
一、吸物 つかみ豆腐、しめじ、めうが。
一、しぼり汁 とろろ、とりざかな。
信濃の乞食首領一茶坊と称する、虱つきの屁たれ男も、この日ばかりは樗堂に借り着して、風儀に従った。
| 【風儀】ふう‐ぎ ならわし。風習。行儀。作法。 作法にかなったなり・姿。型どおりの姿。 能楽で、風体(フウテイ)に同じ。 |
人並にたたみの上で月見哉
の句には、しなのの住人、阿堂と認(したた)めた。
寛政から弘化にかけ、城下の発句熱は隆盛をきわめた「知名美久佐」によると、
藩士では、萬井、麥士。
町家では庭里、路一、風芝、馬雪(南萱町)、六外、口静(米屋)嵐朝(魚町)、桐居(松前町)、幽照(紙屋町黒田)、民谷(新立) 、蕪青(湊町)以下略。
孫六長男和重(其因のちの三代目はこの年、十歳。俳譜をたしなんだか否かは不詳)は座敷の父親に、
「暗いのに、灯、つけもせんと、なにしよん?」
南向きの縁は、青い月光が射しこむ。
「ノノサンがきれかろがな、兎さんがおもちつきよるの。見えよがな」
| 【ノノサン】 方言で普通は仏さんのこと。 ここではお月さん? |
わずらわしい質屋業をさっさと廃(や)めた孫六は、さばさばしていた。
行灯をともすと、薄汚れた伊勢暦を折り、開げして明かりに近づけた。
樗堂翁の好意で借りた一茶の旅行手控え−寛政七年刊の暦を真二つにまず折り、ついで横を九等分に畳み、書き満たすと、折りを変えて記帳したもの−紙をめくる帳とは異り、何度となく折り、ひろげ、たたみを繰り返さねば読み下せない。
各地の俳人の句を書きとめたなかに一茶の句がまじる。
衣がえしばし虱を忘れたり 一茶
浴(ゆあ)みして旅のしらみを罪はじめ 一茶
彼の唯一の道づれ、虱の句が多い。
皮肉にも、一茶の絶大な後援者のひとり守静(俳号)は、しらみとり薬の製造発売元という。
こうして、読むうちにも、一茶の書きものに、誤字の多いことに気づく。その誤りが書きぐせとなっていたようだ。
例えば諏訪が諏方、炬燵を巨達、桔梗とかくべきが桔校と各所で同じ誤りを繰り返している。(寛政紀行の槌口村は、樋口村である)
万葉を愛(この愛も憂と誤記している)し、古今の文献に暁通。歌仙連歌の席では「執筆」の大任を果している彼なのに。
幼少時代、寺小屋通いもままならなかった一茶である。十五歳で江戸に出てからの十余年間は謎ときれているが、この歳月こそが驚異的勉学にいそしんだ星霜の年代であったのか。
孫六は、伊勢暦凡三百五十五日を折り畳むと、良いものを拝見でけた、とつぶやいた。
○ ○
常さんに、月夜はない。
「こんばんは、あんまの常でございます」
其因は、常さんの手をとって奥座敷に案内すると、さっさと引っこんだ。
「今晩はよいお月夜で」
「へえぇ常さんにお月さんが?」
「いんげのことよ(どういたしまして)、こがなんでも(私のように盲人でも)、何でもよぉ見えますぞな」
今宵、孫六家は、慶びを漲らせていた。
行灯が部屋の三隅にすえられ、床の間に百目蝋燭(ろうそく)がゆらいで、銀屏がいちだんと照り映えていた。箪笥、長持に熨斗(のし)。結納が三宝にのる。
| 【熨斗・熨】のし (「伸し」と同源) 火熨斗ヒノシの略。 「のしあわび」の略。 方形の色紙を細長く、上が広く下の狭い六角形に折り畳み、その中に熨斗鮑ノシアワビ(後には紙で代用)を小さく切って張り、進物に添えるもの。 |
小つるの縁談が調い、こうした品々が紙屋町の手島屋から届いたのは、その朝のことであった。
当の小つるは、庭の竹矢来に隠れ、行水をつかっていた。
月光を洛びて裸身がなまめく。その肌を滴がつたい、白い湯煙がはいのぼる。
長じてのちに盲いた常さんには、女体の艶かしさが想像できた。
麥土、樗堂。そして、一茶の三人は月あかりの裏通りで、ひときわ明るい屋敷に注目した。垣根ごしの遠目にも、婚礼調度の華麗さには驚かされた。
「米孫殿のおうちか?」
麥士は小声で一言。
一茶の視線は、庭の片方にむけられていた。
湯浴みをすませた女人のもろ手が、項(うなじ)の髪をつくろうの図である。
行水のあと ぐるにゆう髪のたば
覗くとて蜂にさされし小柴垣 麥士
その後、手島屋六右衛門との新婚生活は二年というはかなさで、小つるは他界。
○ ○
やがて来る七回忌までに、亡妻羅蝶の遺句集「夢の柱」を脱稿すべく、樗堂は忙しかった。
腹立てた角とも見えずかたつぶり 羅蝶
樗堂はこれあるため、この日、八反地に兎文の病後見舞いに赴いた一茶、宜来、魚文たちと、行を共にすることができなかった。
更衣 綻び見るも なみだかな 樗堂
外の闇で、木棺が泣く。
はじめ空耳かと疑った連れ節の声が、
「伊予の松山陽気な所 二分札さえ 三味を弾く」
(宝暦年間発行の二分札にビワを弾く弁財天女が図案化されていたことと、札を銭に引換える手数料が二分、その差し引いたこととの掛け詞)
犬の遠吠えは、夜歩きの人へのおそれでもあろうか。
複数の足音が、庵の庭に入って来た。
二つばかり放屁(ほうひ)したのは、一茶であろう。
| 【放屁】ホウヒ 屁ヘをひる。 とるに足りないことのたとえ。 |
樗堂は、茶布で碗(わん)をぬぐいながら苦笑してむかえた。
狭い庵室(あんじち)が賑わぎ、生気をとりもどした。
風早の町の殷賑(いんしん)ぶり、兎文の本復が報告された。
「あちらでも俳詣は益々ご盛んです」
この日、蝸牛庵で催した詠吟が披露された。
樗堂は、一茶に会釈して、
「米孫さんから、あなたに拝借した日記に添え、路銀の足しにでもと、これが届いています」
例の伊勢暦と奉書の包みを一茶の膝頭へ、丁重に揃えた。
「それで思い出しました。世間はまこと、広いようで狭いもんじゃわい」
魚文は目を見ひらいて語り、同行の友と領きあうのであった。
話の概要はこうである。
門田家二代目妻女の実家は、風早郡の二神牛之助であるという。あの南古萱町の米屋孫六の祖先はやはり二神牛之助、つまりは双方とも、元をただせば縁つづきということになる。
家と家とのむすびつきは、まるで連歌ではないか。
奉書に書かれた米屋孫六の筆跡を見つめて、一同はうなずきあった。
夜はいよいよ更け、庵には一茶と樗堂の二人だけとなった。
「お疲れたなァ、しんどいことないかいな。よかったら、二人で巻いてみるかな」
「大丈夫です。お願いします」
行灯の芯を出し、油を注ぐと樗堂は硯のふたをとった。
薮越や御書(おふみ)の声も秋来ぬと 一茶
牛のすすらす白粥の露 樗堂
院の月薄霧の香の寂(さび)ぬらし 〃
衣摺るべき平石もなし 一茶
髪洗う土は求めし早苗餐(さなえぶり) 〃
鶏(にわとり) 喰(くら)う 小狐をうつ 樗堂
初表(しよおもて)を終え、紙を返す音のみの静けさ・・・・・。
この時、異様な叫声が、闇を切り裂いた。
徒事(ただごと)なちじ、提灯に灯をうつすや「札の辻の方角・・・・・」
樗堂の声をあとに聞いて、一茶は飛び出した。
異変にむかって、人々が走った。
あわやと人々打ちよりて虫の息なる人はとのぞく、按摩ひねりの盲人を、何者ともしらず(わからない。)鑓(やり)もてしたたかに(腹を)通して逃げ去りしあと、いたは(わ)しくにがにがしく、しきりにうしろ寒くなりぬ。あは(わ)れなみ(並)の人にしもあらば曲者ひっとらへ(え)もすべきに、其の身は目さえくらければ闇の鳥の網に入り、流れの魚の毒にあえるごとく思いもかけぬ命失いけるよと、見知らぬ者までも袂をしぽりぬ。是たから(金銭)を奪う盗人にもあらず又意恨打にもあらで、かかる災いの起りけるは魔王のたぐいの此世乱さんとするふるまい(振舞い)かとおばえて今この御世(みよ)に住める心地もせず、かく見る我たぐひも翌(あす)の日此難にあはんこともはかり知るべからずと、今更胸凍る夜にぞありける。
冬枯にどれか先立つ草の花 (一茶日記)
この時代、この地に、かかる殺人事件のありたるとの記録は見あたらない。
盲人のあんまが、常さんであったか否かも不詳。
不審なことは、これと同じ記述が文化三年寅年の一茶日記にも遺されていることである。
彼は、信濃の国、乞食の首領と自称するほか、しばしば虚構を仕組む人であった。
この叙述もまた筆の戯れではなかったか?
樗堂は、文化十一年(1814)八月二十一日六十六歳で逝去。
一茶が、訃報を知ったのは、三カ月の後のことであった。
此次は我身の上か鳴き烏 一茶
大事の人を亡くしたれば此末つづる心もくじけて、ただちにしなのへ帰りぬ。
花の影寝まじ未来が恐ろしき 一茶
一茶が他界した文政十亥年(1827)。奇しくも同じ年の六月、二代孫六は七十三歳を一期として黄泉の国に旅立った。
| 【黄泉】コウセン よみ 地上にわき出ているという泉。地中の水。死後の世界。あのよ。よみじ。 |
赤文字は「JA5DLG」の補間注釈です。
| (参考書誌) |
|
|
|
| 伊予史談 |
|
伊予史談会 |
|
| 樗堂俳詣集 |
|
栗田 樗堂 |
|
| 伊予文化史の研究 |
|
景浦 椎桃 |
|
| 寛政七年紀行 |
|
和田 茂樹 |
|
| 伊予風早俳壇の兎文 |
|
和田 茂樹 |
|
| 伊予俳詣史 |
|
景浦 勉 |
|
| 一茶全集 |
|
信濃教育会 |
|
| 電子広辞苑 5版 |
|
|
|
Microsoft
Book shelf Basic
Version 3.0 |
|
|
Microsoft Bookshelf Basic version 3.0,
Copyright (C) Microsoft corporation 1993-2001
Shin Meikai Kokugo Dictionary, 5th edition
(C) Sanseido Co., Ltd. 1972,1974,1981,1989,1997
|
| 『漢字源』 |
|
学習研究社 |
EPWING版 (C)1993年 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和五十七年一月「アミーゴ」初出 |
|