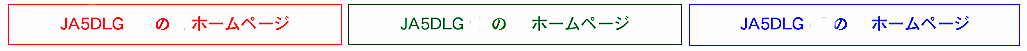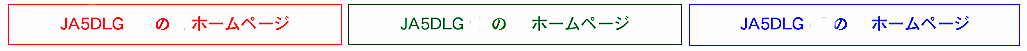|
|
|
|
十二支とは(故事来歴) |
|
|
|
|
|
十二支は,十干より古く、殷の時代から使われていたとも言われます.それが日本に伝わり
ました. |
|
|
まず動物が浮かびますが,元々動物は関係していません. |
|
|
アルファベットみたいな もので,方角や時刻、日月などを数えるための記号集でした. |
|
|
子,丑,寅,卯,辰,巳,午, 未,甲,酉,戌,亥で,草木の成長の度合を表わす語を順番に並べたものです. |
|
|
たとえば, 卯はボウで,草木が茂る状態を表わしています. |
|
|
江戸時代まで、この十二支を使って、時刻 方位などを表わし、日常生活に身近なものでした. |
|
|
どう星に関係しているかというと、年の十二支の決め方は、黄道を12年で1周する木星を
基準とし、黄道を12にわけて十二支を当てはめ、 |
|
|
木星と反対方向に動いていく「太歳」なる星を 仮定し、その場所をその年の12支としたのです. |
|
|
木星の場所で、年の干支を記述する方法は、日本でも各地の庚申塔に見られます. |
|
|
紀銘年と 言うものですが、暗号化が激しく、よほど熟練しないと読めません. |
|
|
木星は、龍、星、歳という文字で記述されているようです.大歳(太歳?),大才と書くこともあるようです. |
|
|
B.C.5~3世紀の中国の春秋時代に、十二支に動物をあてはめるようになりました. |
|
|
民衆に 覚え易くするためだと言われます.日本でも、十二支は、強引に当てはめられた動物の名で
発音するものとして伝わりました. |
|
|
子は元の発音はシだったのに、ネズミのネになり、以下は それに続いて、十二支独特のへんてこな読みで現在も使われています. |
|
|
|
|
|
日本の星の民俗 |
|
|
|
|
|
天文民俗学 |
|
|
|
|