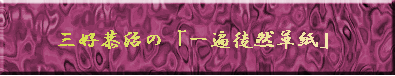|
| 一遍会インターネット会員である岩田憲明氏から平成19年7月27日から8月末までに21通の『私がAPUで考えてきたこと』と題する思索の手記を受け取った。私一人がこの手記を独り占めすることは許されないと考え、同氏のご了解を得て、「一遍徒然草紙」に掲載させていただいた。感想や所見を頂ければ、私からお伝えしたいと考えています。尚、同氏のHPアドレスを下記しますので、是非お立ち寄りいただきたいと思います。尚、9月以降同氏には長期にわたる病気療養生活に入っておられます。一日も早いご快復を心からお祈りしております。 |
| − 哲学茶房のサクサクHP −http://www.oct-net.ne.jp/~iwatanrk/index.htm |
| − 哲学茶房別館 −http://diary.jp.aol.com/xfdhsqbydz/ |
| − 哲学茶房 時事論集 −http://green.ap.teacup.com/iwatanrk/ |
|
|
| 私がAPUで考えてきたこと(1) |
| 私のAPUでのテーマは観光です。もともと哲学が専門なのですが、哲学の観点から観光について考えたらどうなるのかと思って勉強を続けて来ました。ということで、「観光におけるフィクションの意味」というのが私の論文のテーマなのですが、ここでフィクションといってもピンと来ないかも知れません。フィクションというと、小説などの物語のように架空のお話と考える方が多いのではないかと思います。もちろん、それもフィクションなのですが、私の場合、人が守っている社会的取り決めもフィクションの中に入ります。つまりは、人間が頭の中で作り出したものがフィクションなのですが、それは単に架空のものというわけではなく、人間の作ったものとして人間自身のあり様を規定するのではないかというのが私の観点です。 |
| 例えば、物語のような架空のお話にしても、そこには各自の希望が含まれています。こんな世界があったらいいなとか、人生はこうあるべきだとう考え方がその中には含まれているというわけです。また、社会的な取り決めとしてのフィクションはより現実的な力を持っています。私たちの社会は法律によって運営されていますし、日頃使うお金にしても、それをお金として価値のあるものと見なす取り決めがあってこそ、現実に流通しているわけです。いずれにしても、私たちの世界はただ現実に流されているわけではなく、私たちのフィクションによって人間の行動が決められ、規定されているということができるでしょう。 |
| 私は観光について、このフィクションを次の2つの立場から考えています。1つは観光客の立場です。観光客は自分の理想とする日常にはない世界を観光に求めます。これは物語としてのフィクションの性格を持つものですが、ここでは観光客側からの観光地への意義づけがあるのであり、彼らの価値観が観光のあり様を規定しているといえるでしょう。 |
| もう1つは、観光客を受け入れる人たちの立場です。観光はすでに大きな産業となっていますから、それ自身現金収入を得るための大きな手段です。しかし、それだけなのか。観光を通して地域の見直しが進み、観光客との交流を通して新しい地域の可能性が生まれるのではないかというのが私の考えです。ここではまずお金というフィクションによる産業としての観光の可能性が問われますが、より以上に地元の人たちと観光客の交流のための新しいフィクションが可能ではないかということが問われます。現実に観光とは観光客と地元の人たちの出会いの機会なのであり、そこに有効で新たなフィクションが生まれるのではないかというのが私の視点です。 |
| このようなわけで、私の論文はまずこの2つの視点を中心に次のような構成を取ります。 |
| 1.個々人の主観的フィクションはいかなるものか。 |
| 2.現実の観光の可能性はいかなるものか。 |
| 3.理想的な観光を可能とする条件はいかなるものか。 |
|
| (1)では観光だけではなく、広くエンターテーメントの考察を通して、個々人のフィクショナルな世界が何を求めているかが問われます。(2)では観光客を受け入れる地域とはどのようなものかが問われます。ここではお金によって成り立つ社会から地域共同体の特性を区別するために、地域通貨の実践にも触れています。(3)では観光客と地域の人たちが本当に触れあうためには、その地域の自然・歴史環境が重要であることが示されます。人間が新たに結びつくためには人間を超えたものを背景に持つ必要があるのですが、その点を掘り下げてみたいというわけです。 |
| 実は、この構成はヘーゲルの考え方に影響を受けたものです。直接本文では触れていませんが、私の考えはその背景に哲学を持っています。いかに人間のフィクショナルな世界がうまく実在の世界と重なり合っていくべきかというのが、私の論文の本当の主題です。これは決して観光に限られたテーマではないのですが、観光という具体的な対象を通して長年培ってきた私の哲学的発想が実際のどのように生かされるのだろうかということを試みたのが、APUで私が考えてきたことです。 |
| 私がAPUで考えてきたこと(2) |
| 観光は普通楽しみだと考えられています。そのことには間違いがないのですが、普通の生活を離れた状態に自分のおけるという点において、単なる楽しみ以上の意味を持ちうるのではないかというのが私の考えです。 |
| 私はまず観光の特性として「気晴らし」と「リクリエーション」という2つの概念を考えました。日本語だと同じ意味になってしますのですが、後者は本来re-creaction、つまり再創造という意味を持っています。ですから、私がここで「リクリエーション」という時、そこには観光を通して観光客の日常を変える可能性が秘められています。 |
| 実際にはこの「気晴らし」と「リクリエーション」は同じ観光の中に含まれており、どのような観光が気晴らしだとかリクリエーションだとかいうことは断言できません。けれども、いくつかの典型を考えることができるのではないかと思います。昔は職場を中心とした団体旅行が中心でしたが、これは「気晴らし」の要素が強いものではないかと思っています。というのも、観光の目的が日常の維持にあるからであって、それを見直したり変えることではないからです。ここでは現状の維持が前提となっており、現実を維持することが目的であって、自分の内面にある価値意識を掘り下げて、現実そのもののあり様を問うというものではないからです。現在では女性を中心に、親しい友人や家族での旅行が主流ですが、団体旅行ほどではないにしても、まだ「気晴らし」の要素が強いのではないかと思います。 |
| リクリエーションの典型と思われるのは、巡礼です。日本だと四国の巡礼が有名ですが、多くの人たちが自分の日常を問い直すために旅に出ています。巡礼ほどではないですが、自分を問い直すための旅は良くあることで、最近は「自分探し」という言葉も使われるようになりました。これは日常を離れて、いままでの日々を問い直すことから来ているのだと思います。リクリエーションは、単に未体験の土地に行くだけではなく、それをきっかけに自分の内面を問い直し、それを新たに現実に行かすことを考えるきっかけになるのではないかと思います。ここでは、主観的な理想世界と客観的な現実世界が交差するわけですが、この交わりがリクリエーションの特徴であり、新たな観光の可能性ではないかというのが私の見方です。 |
| 私はこの理想と現実との関係をよりはっきりとした形で日本のサブカルチャーの歴史の中に見出しました。大塚英志さんの「教養としてのマンガ・アニメ」という本があるのですが、その中で次のような話が出てきます。戦時中の空襲の中で手塚治虫は漫画を書いていたのですが、その中で主人公が防空壕を出て敵の飛行機の数を数えるシーンが出てきます。マンガのお約束通り爆弾を受けても主人公は平気なのですが、最後に機銃掃射を受けて彼は死んでしまいます。とても悲しい話ですが、ここに理想としてのフィクションの世界に現実が侵入せざるを得なかった事情が見て取れます。アメリカのカートゥーンですと、主人公はあらゆる苦難を体験しながらも最終的にはうまく行くサクセスストーリーですが、日本のサブカルチャーの物語は必ずしもそうではありません。ガンダムにしてもエヴァンゲリオンにしてもこのような苦悩が物語にリアリティ(真実味)を与えています。 |
| 私はこれを「悲劇の感覚」と読んでいますが、観光といってもリクリエーションの場合、どうしてもこのような感覚が背景にあるのではないかと思います。つまり、理想世界と現実世界とが交わる時、そこにはどうしても不調和が生じるのですが、それをいかに受け止め明日につなげていくかというきっかけになるのが、リクリエーションの本質なのではないかと思っています。そこからいかに復活するか。観光には「気晴らし」の要素を含みながら潜在的にこのような「リクリエーション」の可能性を秘めているのではないかというのが私の考えです。実際にはさほど深刻ではないにせよ、この可能性を実際の観光の中に求めていくのが次の課題となります。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(3) |
| 前回では、エンターテイメントにおける理想世界と現実世界との関係を考えてみました。今回は実際の観光地における、この2つの世界の関わりを見てみたいと思います。 |
| ここで研究の対象として取り上げるのは東京ディズニーリゾートと秋葉原との2つの観光地です。これらについてはすでに以前のメールで東京レポートとして取り上げましたので、今回は深くその中身について言及はしません。しかし、非常に対照的な観光地だと思います。まず、ディズニーリゾートが日常世界から隔離された理想の世界を演出しているのに対して、秋葉原は日常の妄想が現実化したところがあります。以前もご紹介した通り、ディズニーリゾートでは東京の近くにあるにもかかわらず青空と緑で見事に仕切られた物語の空間を演出しています。人々はその中で日常を忘れ、自らの理想世界、夢の世界を体験できるわけです。これに対して、秋葉原は人々の必要が積み重なった街であり、古くからの電気街、電器製品の安売りのお店、そして最近ではオタクの聖地ともいわれています。その一方で、多くの外国人が訪れる観光地としてたくさんの日本人形が売られていることを考えると、実に多様な発展をしてきた街だといえるでしょう。 |
| この2つの観光地の違いは、まずディズニーリゾートが大資本によって計画されたものであるのに対して、秋葉原が自然発生的にできた街であるという点に求められるでしょう。しかし、違いはそれだけに止まりません。ディズニーリゾートが家族連れ、もしくは女性をターゲットとしたリゾートであるのに対して、秋葉原は独身男性の趣味がその街の基礎にあります。最近では土日を中心にメイド服を着た女性を見かけることが多くなりましたが、これももともとは男性の妄想が生み出したところがあります。あまり取り上げられないのですが、秋葉原にはかなりアダルトDVDの店が多いのです。だからといって治安が悪くなっているわけではないのですが、そこにこの街の根本に男性の欲望があるという特性が出ているのではないかと思います。 |
| ディズニーリゾートを訪れる家族連れや女性には常に帰るところがあります。つまりは、自分の居場所をきちんと持っている人が異世界を楽しみに来ているわけです。けれども、秋葉原を訪れる男性、もしくは女性は必ずしもそうではありません。思春期の若者、特に男性は将来のために自らの家を持たなくてはならないのです。そのような人たちにとって、理想世界は単なる理想世界としてあるわけではなく、これからの現実を左右する要素がその中にあるわけです。ディズニーリゾートでは「行ってらっしゃい」と入る前に言われますが、秋葉原ではメイド喫茶で「お帰りなさいご主人様」と呼ばれるのは、この街に映し出された願望の違いを端的に示しています。 |
| このように書くとディズニーリゾートが単なる「気晴らし」の場のように思われるかも知れませんが、必ずしもそうではありません。私はすでに居場所を持つ人たちにとって、ここは心の中にある理想世界を再確認させる重要な場所なのではないかと思います。宗教の世界でも、限定的に理想世界を実現させ人々にそれを心のとどめてもらうために、多くのお寺が造られました。越前の永平寺や以前作られた山科本願寺はそうでなかったかと思います。けれども、「リクリエーション」としては積極的なものではなく、消極的なものだと思います。というのも、それは心の中にある理想世界を保持するためのものだからです。 |
| これに対して、秋葉原は未だ居場所を持ち得ていたい人々の思いがどこかにあると思います。これが「悲劇の感覚」を生み出しているのですが、恐らく普通の人たちはこの街の多様性の中にそれを見出すのは難しいと思います。けれども、彼らの多くがひとりであることを考えればこのことは理解できるのではないかと思います。もちろん秋葉原は楽しい場所ですが、観光地の本質を考える時はこのような視点も必要です。このようなフィクションが現実世界に露出したような街を考える時、現代社会の背後にある問題にも触れておく必要があるでしょう。次回は現代社会が逆にフィクションによって覆い尽くされ、実在の世界が見失われているのではないかということを考えてみたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(4) |
| 私たちの生きているこの社会の多くの部分がフィクションで成り立っているというと、皆さん驚かれるかも知れません。フィクションを単なる頭の中の作り物と捉えるならば確かにそうかも知れませんが、私たちの社会が人間の作ったルールで成り立っており、そのルールが人間のフィクションの産物であるとするならば、このことはむしろ当然のことです。けれども、私たちは「現実」という言葉でこのフィクションで成り立つ社会のことを指すのが多いのではないでしょうか。 |
| フィクションの産物は以前示したように法律やお金だけに限りません。便利な生活を提供してくれている科学技術の産物もそれに入ります。人間は頭の中で自然のあり様を再構成することができます。それに従って自然に働きかけてきたわけですが、このことによって人間は自分追い切る環境を大きく変えてきたといえます。特にと解では、フィクションの産物である人工物が氾濫し、なかなか自然の姿を見ることはなくなりました。確かに便利にはなったのですが、自分の都合に合わせて対象に働きかけ、自分の都合の良い刺激を受けることが多くなってきたわけです。その一方、個々の人間は社会のリズムに合わせて生きなくてはならなくなっています。現代人がやたらと忙しいのはそのためです。結果として、昔からの人間関係は希薄となり、家族の絆も弱くなっています。お金がないと生活ができないいまの状況はこのような世の中の歩みと無縁ではありません。いずれにしても、これは人間が本来生きてきた環境から離れていることを意味するでしょう。 |
| 私は東京に行って何人かの人にあって感じたのですが、人工物に囲まれて生きるという危険性を意識している人が少ないように思えました。ある人間がそこで生きている背後にはいろいろな要因が存在します。もちろん親の存在が第一ですが、その人を育てる自然・歴史環境があることが前提となっています。ところが、この環境が非常に見えにくくなっています。その地域にはその地域の地霊ともいうべきものがあります。それは自然の恵みであったり、人々が生きてきた歴史であったりするのですが、それを人々は無意識ながらも感じながら生きてきました。昔はこれらの環境がお寺や神社などの宗教施設を中心に維持されていましたし、さまざまな伝承がこれらの環境に意味を与えていました。ところが、現代ではそれを見ることは都会では希のようです。逆に効率を重視した同じような施設が増え、子供の時からそれを当たり前のように見て育った人が増えてきているのではないでしょうか。 |
| このような中で観光を含めたエンターテイメントには2つの方向性が生まれます。その1つはは人工物を通してより都合の良い状況をつくり出すことですが、これは「気晴らし」を生み出す方向性だといえます。もうひとつは、人工物に物足りないものを感じ、何か本物を求める「リクリエーション」の方向です。ディズニーランドのような良質のエンターテーメントはその核にきちんとした理想を持っていますが、そうでない人工的な観光を求める場合も多いのではないでしょうか。特に、バブル期に考えられたリゾート施設の多くはそのようなもののように思います。そもそも利益を前提に多くのお金を投資するというパターンが従来の産業と同じなのですが、そこには人に快楽を与えて儲けようという意図が見え隠れします。観光サービスを提供する側はこの2つの方向性を考えて自らの求めるものをはっきりさせる必要があるでしょう。 |
| いずれにしても「気晴らし」のためだけの多くの施設が失敗し、エンターテイメント全体において悲劇の感覚を持つ日本のサブカルチャーが受け継がれているのは、人々が「リクリエーション」を求めているからではないかと思います。パチンコでウルトラマンなどの古い日本のエンターテイメントが甦っているのもそのためでしょう。その感覚をいかに観光に生かすか。このことを考えるために、社会を動かす重要なフィクションであるお金について考えていきたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(5) |
| 私たちが日頃当たり前のように使っているお金ですが、このお金について根本から考えた人はどれだけいるでしょうか。お金そのものはコインであったり紙切れであったりするのですが、価値のあるものと交換できるものとして、それ自体値打ちがあるものと考えられています。けれども、どうしてこの交換を通じてお金に価値があると考えられるようになったのでしょうか。 |
| お金がなければ物々交換ということになりますが、これには「あげたいもの」と「もらいたいもの」が互いに一致することが必要です。けれども、なかなかこのような一致は見られません。けれども、お金があるとこのような一致にかかわらず交換をすることができます。つまりは、「なんぼ」のお金で買ったり売ったりすることになるわけですが、このおかげで経済の流れが成り立っているのは確かです。 |
| 何でお金ができたのかというのには諸説がりますが、塩や貴金属などの腐らない貴重品を裏付けにした紙を物々交換の仲立ちに使用したというのが始まりではないかと思います。昔はこのような貴金属そのものがお金の材料として使われていました。貴金属は装飾品としても使えますが、何よりも希少価値があり、時間が経っても劣化しないことが強みだったように思います。このような裏付けがあれば、たとえそのお金を交換に使うことができなくても何らかの形で元を取ることができます。これが個々の取引の信用をある程度保証するのですが、国が交易を促進するためにそのお金を公に認めればその信用は高まります。現在はコンピューター上の数字がお金の働きをするようになっていますが、このように頭の中で考えたフィクションがすぐさま現実的な力を持つのは、このような歴史的な経験の積み重ねによるといえますが、経済が発展してお金なしには世の中が動かなくなっていることも大きな理由でしょう。 |
| このように経済のお金は媒介として大きな意味を持つのですが、それ自体は中立的なものと見なされるのが普通です。しかし、必ずしもそうではありません。いまのお金には利子がつきますが、この利子のために多くの事業は短期的に利益を上げる必要に迫られています。また、その一方でお金のある人はどこかに投資して利子や配当によって利益を得ようとします。この場合、持てるものはますます富み、持たざるものはますます貧するわけですが、お金そのものが普通の品物のように劣化しないことを考えると非常に持てるものに有利であることが分かるでしょう。結果として、経済の媒介であるお金は一部に集中し媒介としての役目を果たさなくなることもあります。 |
| ベルナルド・リエターさんはこのお金の特質をいち早く見抜いた人ですが、その一方でお金の本質が人々の「取り決め」であることも指摘しています。私がお金をフィクションの産物とするのも彼の考えに基づいているのですが、すでにお金は人間の手を離れて勝手に動き始めているのではないでしょうか。その一方で、多くの人はお金の本質に思いを寄せることなく、あたかもお金自体に価値があるように思いこんで働いています。 |
| 私はこのようなお金の現実を見た時、自分が長年考えてきた記号論を思い起こしました。次回はそのことについて少し触れてみます。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(6) |
| 私の専門は哲学です。ですから、観光や経済を考える時も哲学が基本となるのですが、お金の本質を理解した時に自分が長年考えてきた記号論のことを思い浮かべました。これは記号論といっても1つの世界観なのですが、次のような言葉にまとめられます。 |
| 1. 世界は記号の総体である。 |
| 2. 世界は機能(funciiton)として自らを解釈する。 |
| 3. 世界は自ら意味のつながりとして成り立っている。 |
|
| 恐らくこのテーゼを読んで意味の分かる人はまずいないでしょう。私もこの発想を得た時、理解されないと思い長年封印をしてきました。このことについては私のサイトの「医療と哲学(1)」で解説しているのであまここ々では詳しく述べませんが、限定的でありながらも、お金について考えるとこの記号論が当てはまるように思えたのです。 |
| 具体的にはこうなります。お金はそれ自体価値のない紙切れだったりしますが、人を通して価値あるものと見なされ、一連の経済の流れ、つまりは価値を持つとされる商品の流れを成り立たせているというわけです。お金を見て喜ぶのは人間だけです。人間はお金を手に入れて、それを何らかの商品と交換する権利を得ます。実際に商品とお金を交換したり、それを何かに投資することによってお金はめぐり経済が成り立つわけです。ここでは「世界」といっても経済の世界に限定されますが、記号としてのお金が人間によって価値あるものと見なされ、交換を通じて世界を成たたしめていることが理解できるでしょう。 |
| ここで問題になるのは人間がなぜお金を価値あるものと見なすかです。それはお金そのものに価値があるからでも人間が勝手にお金に価値があるとしているからでもありません。そこにはお金を通じて交換が成り立つという客観的状況があります。お金の成り立ちについては前回書きましたが、お金が品物と交換されるという信用があってこそお金は価値あるものとされるのです。私はこの客観的状況を「環境」と呼びます。実は、私の記号論においてはこの環境がとても重要で、この環境が成り立つからこそ記号は記号としての意味を持ち、それに従って機能は記号を解釈できるのです。 |
| お金についても同様のことがいえます。どのような背景がお金の価値を裏付けしているのか。現在私たちは日本銀行などが発行した公のお金しか考えつきませんが、本来お金はそれに限ったものではありません。そこにはお金の背後にある社会のあり方の問題があるのですが、そこは次回のことといたしましょう。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(7) |
| 現代私たちはいまあるお金を当たり前のように使っています。つまりは、お金をすでに社会がお金としていることを当たり前として考えているのですが、すでに述べたように、そこまで人々がお金を信用するようになるには長い時間がかかっています。現在のお金は、国のような巨大な社会が背景にありますから、そのお金の性質も法律のように個々の人間を超えて決まっているものと考えられています。しかし、お金はすべてそのような巨大な権威によって支えられているとは限りません。仲間内でポイントをつくり、仲間内の貸し借りを手帳を使ったり携帯電話で自動的に精算できるようになれば、それも立派にお金として機能します。そのような発想の下で考えられたのが、地域通貨であり、実際にヨーロッパなどでは失業者などの間で一定の役割を果たしているようです。 |
| このような地域通貨と従来のお金の違いは、お金の意味を決める背景にある社会の違いにあると私は考えます。従来のお金の背景には、いちおう発行しているのは日銀などの銀行ですが、国家のような権威があり、その国の中では使う人が誰であろうがそのお金は通用します。しかし、地域通貨の場合、その背景にあるのは仲間内の信用であり、当事者が地域通貨をやめようと思えばそれは無効になります。私は社会学の用語に従って、前者のような社会をゲゼルシャフトと呼び、後者をゲマインシャフトと呼びますが、この2つはお金の意味を規定する「環境」の違いを示す重要な違いだと私は考えます。 |
| この対となる用語はテンニエースという社会学者により提唱され、マックス・ウェーバーによってより深く探究されました。ゲゼルシャフトは冷たい社会とも呼ばれるように、個々人を上から規定する規則によって成り立ち、多くの場合、会社組織のように自らを維持するための職員を持っています。これは国家のみならず、会社のような組織を考えてもらえれば良く理解できると思います。それに対して、ゲマインシャフトは暖かい社会、もしくは共同体と呼ばれるように、ゲゼルシャフトのような固い組織ではなく、その時々に応じて互いに助け合う組織だということができるでしょう。無論、現実の社会はこの2つの要素を同時に含んでおり、かつての村落共同体のように、厳しい規則によって村人を規制する場合も現実にはあります。 |
| 私はこの2つの社会の特質を、より進んで<目的ー手段>の関わりから捉えます。ゲゼルシャフトは一般の会社が利潤追求を掲げるように何らかの目的を持ち、その中のメンバーにその目的のために働くことを求めます。会社の給料などはその見返りということができるでしょう。それに対して、ゲマインシャフトはその共同体のメンバーの生活の安定が直接の目的ですが、ゲゼルシャフトのように特定の目的を持たず、メンバーをそのための道具としては考えていません。むしろメンバーのために組織があるというのが本当のところでしょう。このことに加えて先に掲げた「上から規定する規則」によってゲゼルシャフトが運営されていると考えると、ゲゼルシャフトでは法律にせよお金にせよ誰がそれに従い利用するかということに無関心であるのに対して、ゲマインシャフトでは個々の人間に合わせて柔軟に対応がなされることが多いので、そうではないと言えます。 |
| 私は人間社会をこのように区分したことには重要な意味があると考えます。というのも、このことによって事実をより深く解釈することができるようになるからです。二等辺三角形の2つの角がなぜ等しいかは、ただこの三角形を眺めるだけでは理解できません。頭の中でこの三角形を二分する補助線を引き、二等辺三角形が2つの等しい直角三角形の合体したものだと分かった時、初めてその理由が分かるのです。このことは世の中を理解する知識が単に事実として外側から与えられるのではなく、その事実を自分なりに解釈することが学問には必要であることを物語っています。話は少し横にそれましたが、次回はこの2つの「環境」の違いを通して「疎外」の問題を考えてみたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(8) |
| 私は以前から地域通貨の活動に関わってきました。ですから、APUでの研究でも地域通貨のことに触れています。具体的には大分の地域通貨、yufu
fuku 湯路についてですが、これらの地域通貨も含めてまだ日本には本格的に生活を支える地域通貨はないといって良いでしょう。何しろお金さえあれば何でも手にはいるのが日本ですし、その分地域の助け合いの感覚も薄れているのが現状です。けれども、これらの地域通貨の活動は円などの一般通貨が危機に瀕した時の布石になりますし、何よりもコミュニティの特性を考えるのに非常に参考になります。 |
| 私が実際に地域通貨を使ってみて感じたのは、まず相手によって価格の設定がかなり柔軟にできるということです。コンピューターの打ち込みの作業をお願いした時は、こちらの都合に合わせてかなり安くやってもらいました。また、かなり小回りがきくのも強みで、私はかなり古本などをその時の都合で売ることができました。このような感じですが、お互いに仕事を依頼できることもコミュニティづくりでは重要です。私は占いで地域通貨を稼ぎましたが、これは人と知り合うきっかけになりました。お金で依頼するのに比べて質は落ちるかも知れませんが、その手軽さを考えると地域通貨は便利なものです。何よりもお互いの都合に合わせてやり取りができるのが魅力で、多少の無理がきくのが地域通貨です。 |
| 一般通貨では以前では値切りがあったものの、最近はほとんど定価販売です。また、こちらの懐具合にかかわらず定価は一定しています。ですから、お金持ちの嗜好品も貧乏人の必需品も同じように価格によって表示されるのですが、必ずしも私たちの必要度を反映したものではないのは確かです。 |
| 経済学では私たちが主観的に必要な価値を使用価値といい、市場でつけられる価格に基づいた価値を交換価値といいます。お金はこの交換価値によって動くのですが、必ずしも使用価値を反映したものではありません。お金が利子を持ち、お金持ちがますます富む傾向があることを考えるとこれは大きな問題です。彼らの意向はより強く市場に反映されることになるでしょう。品物は一度市場に出されると商品としてその価値が決定されますが、そこではその商品に関する個人の事情は反映されなくなります。 |
| これは先に述べたゲゼルシャフトとゲマインシャフトの違いをその背景に持っています。ゲゼルシャフトでは個人は均一の存在として、つまりは匿名の存在としてその事情には関知しません。その上、ゲゼルシャフトの原理が支配する市場では、より大きな利潤を求めることが求められ、つまりは需要と供給の原理によって価格の大枠が決められます。そこで個人がどれだけ品物を必要としているかという使用価値は交換価値に置き換えられているわけです。 |
| 私はこのことを使用価値の「疎外」と考えます。もともと疎外とはもとの事情から切り離されて新しい状況の中で独自の意味を持つこと考えていますが、これは「ひとり歩き」という日本語で表現すると分かりやすいかも知れません。マルクスは「労働の疎外」ということを説きましたが、これは本来人間に属するはずの労働が市場では価格をつけられて、人間からは独自の意味づけを与えられることを意味しています。私が考えるのは「使用価値の疎外」であり、私たちが本当に求める度合が市場では正確に反映されず、特定の人間の使用価値が歪んだ形で反映されることを指しています。 |
| これはゲゼルシャフトを基盤とするお金ではどうしても避けられないことです。一端市場原理の任されれば、それにあらゆる政治的事情が関わります。どうしてアメリカはイラクにあれだけの軍事費をかける一方で多くの途上国の人たちが貧困に喘ぐのでしょうか。このことを考えると、自らの生活の最低限の基盤を得るために地域通貨の併用も必要なのではないかと私は考えます。というのも、地域通貨では利子もなく、見知った人間どうしの取引なので、使用価値の疎外が少なくて済むからです。 |
いずれにしても、観光を取り巻く経済の状況はこれから明らかになるのではないかと思います。単純な利潤追求のための観光は結局は観光そのものの使用価値から離れていきます。いかに採算を維持しつつ、コミュニティレベルでの観光を実現するか。これは観光を越えたあらゆる分野に共通の課題ではないかと思います。
いままでコミュニティーの価値の重要性を述べてきましたが、伝統的なコミュニティーには閉鎖的・過度に保守的などのマイナスイメージもあります。実は、このような伝統的コミュニティーの立て直しに観光が役立つのではないかというのが、私の視点です。 |
| 私はここで「隣人」の概念を深く考えて見ました。隣人は単に空間的に近くにいる場合だけとは限りません。電話や手紙もありますし、最近ではネットを使ってより簡単にコミュニケーションが取れるようになりました。その一方、最近の市町村合併により以前は異なった近隣の町村の人々と付き合う機会も増え、広い単位で地域を考える必要も出てきています。私はそのような中で、日頃よく顔をつきあわせる範囲の人たち、車でなら日帰りできる範囲の人たち、やや遠く県外に住んでいる人たち、遠く海外に住んでいる人たちと隣人の空間的距離を分けて考えます。 |
| 従来の日頃よくあう人たちのレベルでは自然と交流がなされますが、その一方、一度人間関係がこじれると仲介者もなく確執が固定化する場合もままあります。空間的距離に応じて、遠くの隣人をそのコミュニティーの中に招くことによって、この確執を越えて地域活動ができるのではないかと私は以前から考えていました。 |
| 海外などの遠くの隣人は滅多に来ることはありません。しかし、それがきっかけで近隣市町村の人たちと知り合った例があります。以前ベルナルド・リエターさんが由布院に来られた時、それがきっかけで私は別府の方と知り合いになりました。私が本格的に別府の地域活動に参加するようになったのはこれが理由です。私は大分市の出身ですが、なかなか別府とのつながりがなく、湯布院のイベントを通じて近隣の方と知り合うことができました。このように遠くに隣人を通じて近くの隣人を知ることが多々あるのですが、私はこのような試みを「遠交近交策」と呼んでいます。 |
| 心の通じた友人は空間的距離に関係なく交流することができるのですが、この距離を超えた交流を地元に生かすことが地域活動の有力な手段なのではないかと思います。観光はまさに遠くの他者をこちらに招き入れる行為ですが、それをきっかけにメールなど恒常的な交流を行うこともできるのではないでしょうか。実際、別府八湯MLというのがあり、そこでは地元の人だけではなく全国の別府を愛する人たちの意見が飛び交います。このMLに参加する県外の人たちの多くは別府のリピーターなのですが、彼らの外からの視線は別府にとって非常に貴重なものだと思います。 |
| また、別府には多くの留学生が住んでいますが、彼らが地元の人たちと新しいコミュニティーを作っている例もあります。別府のバプティスト伝道所には多くの留学生が集まるのですが、彼らのために日本語と英語で説教がなされ、賛美歌もプロジェクターでローマ字の歌詞が出るようになっています。教会では牧師夫婦、従来の信者たち、そして留学生たちが互いに媒介となってお互いをつなげながら助け合っている姿があります。この基盤には信仰があるのですが、それぞれの地域においても自らの地域を基盤としてこのような交流は可能なのではないでしょうか。 |
| 空間的な距離によって隣人も区分されますが、その特性を互いに生かしつつ、互いに媒介し合うことによって新たな地域づくりができると思っています。観光は新たな隣人を得るきっかけとなりますが、このきっかけを通じて単なるお金儲けだけではない地域活動もできるのではないでしょうか。次回は具体的な別府の地域活動を通じてそのことを少し考えてみます。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(9) |
| いままでコミュニティーの価値の重要性を述べてきましたが、伝統的なコミュニティーには閉鎖的・過度に保守的などのマイナスイメージもあります。実は、このような伝統的コミュニティーの立て直しに観光が役立つのではないかというのが、私の視点です。 |
| 私はここで「隣人」の概念を深く考えて見ました。隣人は単に空間的に近くにいる場合だけとは限りません。電話や手紙もありますし、最近ではネットを使ってより簡単にコミュニケーションが取れるようになりました。その一方、最近の市町村合併により以前は異なった近隣の町村の人々と付き合う機会も増え、広い単位で地域を考える必要も出てきています。私はそのような中で、日頃よく顔をつきあわせる範囲の人たち、車でなら日帰りできる範囲の人たち、やや遠く県外に住んでいる人たち、遠く海外に住んでいる人たちと隣人の空間的距離を分けて考えます。 |
従来の日頃よくあう人たちのレベルでは自然と交流がなされますが、その一方、一度人間関係がこじれると仲介者もなく確執が固定化する場合もままあります。空間的距離に応じて、遠くの隣人をそのコミュニティーの中に招くことによって、この確執を越えて地域活動ができるのではないかと私は以前から考えていました。
|
| 海外などの遠くの隣人は滅多に来ることはありません。しかし、それがきっかけで近隣市町村の人たちと知り合った例があります。以前ベルナルド・リエターさんが由布院に来られた時、それがきっかけで私は別府の方と知り合いになりました。私が本格的に別府の地域活動に参加するようになったのはこれが理由です。私は大分市の出身ですが、なかなか別府とのつながりがなく、湯布院のイベントを通じて近隣の方と知り合うことができました。このように遠くに隣人を通じて近くの隣人を知ることが多々あるのですが、私はこのような試みを「遠交近交策」と呼んでいます。 |
| 心の通じた友人は空間的距離に関係なく交流することができるのですが、この距離を超えた交流を地元に生かすことが地域活動の有力な手段なのではないかと思います。観光はまさに遠くの他者をこちらに招き入れる行為ですが、それをきっかけにメールなど恒常的な交流を行うこともできるのではないでしょうか。実際、別府八湯MLというのがあり、そこでは地元の人だけではなく全国の別府を愛する人たちの意見が飛び交います。このMLに参加する県外の人たちの多くは別府のリピーターなのですが、彼らの外からの視線は別府にとって非常に貴重なものだと思います。 |
| また、別府には多くの留学生が住んでいますが、彼らが地元の人たちと新しいコミュニティーを作っている例もあります。別府のバプティスト伝道所には多くの留学生が集まるのですが、彼らのために日本語と英語で説教がなされ、賛美歌もプロジェクターでローマ字の歌詞が出るようになっています。教会では牧師夫婦、従来の信者たち、そして留学生たちが互いに媒介となってお互いをつなげながら助け合っている姿があります。この基盤には信仰があるのですが、それぞれの地域においても自らの地域を基盤としてこのような交流は可能なのではないでしょうか。 |
| 空間的な距離によって隣人も区分されますが、その特性を互いに生かしつつ、互いに媒介し合うことによって新たな地域づくりができると思っています。観光は新たな隣人を得るきっかけとなりますが、このきっかけを通じて単なるお金儲けだけではない地域活動もできるのではないでしょうか。次回は具体的な別府の地域活動を通じてそのことを少し考えてみます。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(10) |
| 別府ではいまさまざまな地域活動が試みられています。地域通貨「湯路」もそうですが、さまざまな一連のイベントをそろえた「オンパク」、まちあるきの実践、シルバー世代の定住を目指した「わくわくラクダ」、B級グルメなど、別府の特性を生かした活動がなされています。特に、オンパクはそのノウハウを函館にも紹介し、別府発のイベントが全国展開をはじめています。私の研究ではそれぞれにコメントをしているのですが、実際に私が関心を持つ2つのイベントを取り上げることにいたしましょう。 |
| 1つは「わくわくラクダ」です。これはシルバー世代の定住をはかるものですが、すでにバリアフリーの住宅や定住者たちの交流が始まっています。私はこの活動には直接関わっていないのですが、別の側面からこの活動に関心を持っていました。それは宗教的な心のケアーの問題です。退職後の生活を多くの人は希望に満ちあふれたものと考えていますが、心身の健康を考えると必ずしもそうではありません。いままでの無理が出てくる時期でもありますし、老病死の現実が近づいてくる頃でもあります。そのことを考えて私は別府に関わる宗教関係者との関係を重視してきました。別府南無の会もそうですし、お医者さんとして真宗の活動に関わっている田畑正久先生との関わりもその中に入ります。 |
| もともと別府は宗教的な歴史がある場所なのですが、それを生かして精神的にも充実した生活を退職後も送ることができないかというわけです。病気になって私自身この思いを強くしています。確かに別府は温暖で温泉にも恵まれています。しかし、老後の生活には人々の協力と宗教的な心の支えはどうしても必要です。あまり宗教的な臭いを出すと縁起でもないと思われるので実際にこの立場から「わくわくラクダ」の活動には関わっていませんが、このことは定住が現実化してから問題になってくるように思います。 |
| もう一つは、上には書いていないのですが、竹瓦横丁のお掃除です。野上本館の協力で私は水曜日の午前10時から竹瓦横丁のお掃除をしていました。報酬は5湯路で結構よい話なのですが、長い間参加するのは私だけという状態が続いていました。最近は学生さんも参加するようになったようですが、いまはどうなっているか分かりません。とにかく、ここで掃除をして近所の温泉で湯路を使い循環させる活動をひとり地道に続けてきたわけです。 |
| 私がこのような活動をしていたのにはわけがあります。掃除はまちづくりの基本だからです。掃除をしているとそのまちの現状が見えてきます。無造作に捨てられたタバコの吸い殻や空き缶、それだけではなく側溝には多くの空き缶などのゴミが捨てられています。せめて携帯の灰皿を持ってくれればと思うのですが、それも難しいようです。 |
| 私は学生などの外の人間が別府の掃除をすることによって、別府の人たちが自分たちの地域の現実を意識してくれるのではないかと考えていました。地域通貨はそのための便利なツールです。多くの人外の人間が側溝の掃除をはじめれば、地元の人たちも地域の現状に関心を持つでしょう。とにかく別府は汚いのです。夏には臭いもしてきます。汚いことは必ずしもマイナスではないのですが、観光において不快な臭いは禁物です。このことを実際住んでいる人があまり自覚していない。それが問題だというわけです。 |
| さまざまな活動にも関わらず、一般的な別府市民の意識は低いと言わざるを得ません。掃除のこともそうですが、市政も常に混乱しています。せめて外の人が来ているのだという自覚が必要なのですが、観光客が来るのが当たり前と思っている節があります。その一方で、いかに自分たちが恵まれた環境にあるかの自覚がありません。学生など本来外部の人たちとの交流でそこを変えていきたいのですが、時間が必要なのは確かでしょう。私が病気で掃除ができないことがとても残念です。 |
| 観光地にはさまざまなところがあります。地域が一丸になって企画を推し進めている湯布院などの事例もあります。別府の場合は恐らくそうはいかないでしょうが、それなりに観光の可能性はあるはずです。次回は観光客と地元の意図たちの交流の視点から、観光地の意味を問い直してみたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(11) |
| 私の研究では「故郷」つまり「ふるさと」が大きな意味を持っています。これは私の恩師である西川先生の「環境哲学への招待」の中で紹介されたハイデッガーという哲学者の「故郷喪失」の発想と近いのですが、この故郷は普通にいう生まれ育った場所という意味ではありません。むしろ心の拠り所になる思い出の場所というところでしょうか。ですから、正確に言うと、特定の場所を指すのではなく、ある場所での理想的な人間関係、そしてその人間関係がその人の人生の支えになっていることを指しています。 |
| 私がこの発想を得たのは別府バプティスト伝道所で「ゲール(寄留者)」の話を聞いた時です。そこで感じたのは現代人は本当に自分の心の拠り所となる場所やそこでの人間関係を持っているのだろうかということでした。すでに日本の家族関係が希薄になっていることは他でも述べてきましたが、そのような関係にとどまらず地域なら地域の伝統に根ざした生活の中で育ってきたのだろうか、それが疑問になったわけです。もしそのような環境で人が育たなかったら、その人は狭い世界しか知らず、自分の快不快だけで動く人間になってしまうことも否定できません。実際に、効率優先の社会ではどこも同じような風景になってきていますし、自分を支えている目に見えないものに意識を払う機会は失われているのは確かでしょう。 |
| 私はそのような環境の中で現代人が本能的に「ふるさと」を求めているのではないか、そのふるさとを観光を通じてある程度実現できるのではないかと考えています。私が前回地元の人たちと観光客との交流の可能性を示唆したのはそのためです。しかし、ふるさとは人との交流だけで成り立つものではありません。そこに人を生かしてきた地域があり、そこに人が生きてきた歴史があってこそその交流は意味を持つのです。ところが、案外地元の人たちは自分たちの住む地域を知りません。観光地でも同様で、観光客から訪ねられても多くの場合、地元の人たちは自分たちの住む地域についてあまり知らないのです。逆に言うと、観光客によって地元の人たちが自分の生きる地域に関心を持つわけですが、そのことが地域の活性化にどれだけ繋がるかはその時々によるでしょう。 |
| いずれにしても、私はこの「故郷」「ふるさと」を実体的に特定の場所として見るのではなく、ある自然・歴史環境を背景に地元の人たちが外の人たちと交わり新たな伝統を形づくるものと考えています。つまりは、活動の場として捉えているわけですが、観光客にとって一時の滞在に過ぎないにしても、このような場の活動に加わることは新たなふるさとを心の中に育むことになるのではないでしょうか。もちろん、地元の人たちにとってこの活動は新たに自分たちを生きる場所を再発見するきっかけになります。というよりも、その活動そのものが人間の本来生きるべき場所であるのです。地元の人たちと外部の人たち、そしてその共通の基盤となる地域の自然・歴史環境が一体化すること、そこに観光をはじめとした地域活動の可能性があります。 |
| 無論、この活動は観光というレベルで行われる場合、産業としての採算レベルをある程度クリアーしなくてはならないでしょう。そのことは自らの生きる場所を確保する上でも必要なことです。しかし、無駄な開発をして観光客を誘致することは、理想的な交流ができないのは無論のこと、地域の自然・歴史環境を破壊することにもなりかねません。次回では、このような失敗を防ぐためにも、地域の歴史環境の重要性に眼を向けたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(12) |
| 前回は私たちがよるべき「故郷」がその地域の環境と共に地元の人たちと外部の人たちとの交流によって成り立つのではないかと述べました。ここではその活動がいままでの地域の伝統との連続性を保つことが必要ではないかと考えてみます。すでに地元の人たちと外部の人たちとの連携の可能性については書きました。しかし、このような人間の活動と自然・歴史環境がどのように1つの流れを形づくっていくかについてはまだ触れていません。実際、それぞれの地域にはそれぞれの歴史があるのでしょうが、現代になってその歴史がとぎれてきているのは確かですし、すでに述べたように地元の人が地元のことを知らない現状も多く見受けられるようになりました。このような中で地元の人たちと外部の人たちとが相互に刺激を与えながら、自分たちがいる地域について関心を深めることができるのではないかと思います。 |
| その意味で興味深いのが桑子敏雄さんの「環境哲学」という本です。この本は景観の重要性を哲学的立場から明らかにした本ともいえるのですが、私が注目するのは「履歴」という概念です。いま私たちがここにいるのはそれなりの歴史的背景があってのことです。その背景の下に私たちは育ち自分たちの感覚を得てきたわけですが、どうもその背景に対する自覚が衰え、その背景そのものも見えにくくなっているのではないでしょうか。桑子先生はその背景を「履歴」と名付けその重要性を強調されています。 |
| 桑子先生はもともとアリストテレスの専門家です。私も哲学をやっているので、正直その手筋が見えるところがあります。人は過去との連続性の上に自然と先人とつながり、今があるわけですが、このことは単なる自然保護の発想からはなかなか出てきません。けれども、このつながりを失うことは私たちの精神の空洞化を意味しています。オウムの信者が以前、神社のお寺をただの背景にしか見えないといっていましたが、ここに空洞化した現代人の精神と、それに入り込むカルトの現実が見出されるのではないかと思います。 |
| 私はこの発想を「攻殻機動隊」というアニメの中のセリフから感じ取りました。ゴーストハック(記憶の操作)され操られた人間に対して、その人間の過去を問いただすシーンが出てきます。子供の時の思い出、母親の顔、これらを無意識のうちに奪われた人たちが犯罪を犯すわけですが、これは別にSFの話とは限りません。家族の絆が薄れ、自然の中で戯れることの少なくなった現代人は多かれ少なかれゴーストハックの危険を抱えているのではないでしょうか。 |
| この「履歴」を失うことは他人とのつながり、自らを生かしてくれている環境とのつながりを失うことです。自然環境も含めた他者は自己に対して快不快の刺激を与える対象に過ぎず、私たち自身がその中で他者のために生きている現実を覆い隠してしまいます。日本のアニメも桑子先生の「履歴」の概念もその問題を指摘しているのですが、互いに連携のない異なった分野で同じような発想が出てくるところに事態の深刻さが見て取れます。 |
| いずれにしても、「故郷」を取り戻すことは実はこの履歴を再び見出すことではないかと思います。昔から人間はその環境に意味を与えてその意味の体系の中で生きてきました。それは神話や伝説の形で伝えられてきましたが、事実でないからといって決して無意味なものではありません。次回はこの環境の意味づけについて考えたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(13) |
| 私がフィールドにしている別府市には鉄輪(かんなわ)という地域があります。蒸し湯で有名なところなのですが、この蒸し湯が一遍上人によって開かれたという伝説が残っています。実際に一遍上人がここに来たかどうかも定かではないのですが、外部の人間と地元の人たち、そしてその地域の自然環境を考える上で面白い説話なのでここに紹介しましょう。 |
| 一遍上人一行が鉄輪を訪れた時、地獄のように吹き出す噴気に驚きました。地元の人に聞くとこのために作物もできないとのこと。上人は地元の鶴見権現に籠もって解決策の伺いを立てます。すると経文を一字ずつ書いた石を噴気に入れてそれを塞げばよいという神託を得ます。一行は地元の人たちと協力して、多くの苦難の末、この仕事をやり遂げます。ただ、一ヶ所だけ噴気が止まりません。上人が再び神託を仰いだところ、蒸し湯にするべしということで、ここに蒸し湯が誕生します。その内部は仏国土を象徴したものであり、その効能はあらたかだという評判も立ちました。 |
| これが蒸し湯の説話のあらましなのですが、ここにはまず外部の人たちとしての上人一行、そして地元の人たちの協力が見られます。それに「鶴見権現」で象徴される自然環境がベースになって蒸し湯が誕生したことが述べられています。 |
| この話がどの程度真実かは定かではありませんが、蒸し湯の由来を反映していることは確かでしょう。現在、この話は紙芝居となりネットでも公開されています。いままで鉄輪(かんなわ)の地名の由来を知らなかった地元の人たちも、観光客にその話ができるようになりました。これは自然・歴史環境の自覚を通して外部の人たちの地元の人たちの交流の機会である観光がうまく行っている例だと思います。ここで問題なのは、この話が真実であるかどうかではありません。ではなく、この話が蒸し湯の歴史を象徴しているかどうかです。もしそれが地域活動に動機づけを与えるものであれば、必ずしも事実である必要はないのです。 |
| この意味において、より面白い事例が別府にあるので紹介しましょう。 |
| 別府の南部には秋葉神社と中浜地蔵という2つ宗教施設があります。このうち中浜地蔵は以前は奈良時代に遡るといわれていたのですが、最近の研究で幕末に指摘に建立されたお地蔵さんではないかと分かってきました。秋葉神社は火難の神、中浜地蔵は水難の神と呼ばれているのですが、この事実によってこの意味は薄れるでしょうか。私はそうは思いません。事実、慶長時代には地震によって多くの人たちが水難で亡くなりました。またこの中浜地蔵は地元の人たちによって手厚く管理されています。このことを考えれば、私はこの2つの宗教施設の役割は薄れないし、地元の人たちはこの2つを核にまちづくりをできるでしょう。 |
| これら物語の例で分かるのは、その物語が何らかの事実と連関を持ち、人々にまちづくりの動機づけを与えていることです。事実との連関といっても、その事実との機縁を感じさせればよいのです。私はその物語の中に、地元の人たちそして外部の人たちをその地域に結びつける秘密があると思うのです。それこそがフィクションの力なのですが、このことについては次回といたしましょう。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(14) |
| 人は単に事実の世界に生きているわけではありません。一時的な必要に従って生きているのも確かですが、この実在する世界に意義づけをし、自らの価値観に従って生きているのです。地域には多くの神社仏閣、お地蔵さんなどがありますが、これらは人々がその地域の特定の場所に対して特定の意義づけをしてきたことの現われです。このような歴史的ともいえるフィクションの装置を読み解く学問に「環境歴史学」という分野があります。それぞれのお地蔵さんにも地域の境界線とか水源地とかの意味がありました。昔の人たちはこのような意味を重んじ、自然や他の人たちとのバランスを取りながら生きてきました。特に、別府には温泉が多いのですが、そこにはお薬師さんなどが置かれています。それは自然の恵みに対する何らかの感謝の意味があるのでしょう。 |
| 先に出した「環境哲学」などの本もこのようなことに言及していますが、異なった分野から似たような見解が出されているにもかかわらず、それらは互いに没交渉であるように思えます。「履歴」については「攻殻機動隊」のアニメの例もあるのですが、どうもこれらの考えがいままで総合的に考慮されることがなかったのも確かでしょう。しかし、このことはとても重要な問題です。というのも、人は単にその時々の必要に迫られて生きる存在ではなく、自らの価値観を現実に重ね合わせながら生きていく存在であり、それだからこそ「生き甲斐」と呼ばれる感覚も生まれるからです。 |
| 仮に人が目の前の必要だけで生きていたらどうでしょう。それは一時的な快不快の感情に動かされて生きているということになりますが、そこにおいて人は快不快の感覚を受け取る主体であっても、何かに働きかける行動する主体ではありません。行動する主体でなければ、人間は自らの生の意義そのものを見失ってしまうでしょう。 |
| 地域に生きるフィクションを考える時に問題となるのは、これらのフィクションが単に人間の頭で考えられたものではなく、現実の世界に何らかの形で裏付けを持っているという点です。前章で述べたように、それは必ずしも事実によって裏付けられる必要はなく、その人の行動の機縁となる程度でかまわないのですが、自らのフィクションを現実に投影しそれを生かす何らかのきっかけを必要としています。人はそのことによって人としての他者と交わり、人間そのものを生かす前提となる「何か」を地域の環境の中に見出すのです。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(15) |
| 私が論文の前段階で書いたリサーチペーパーで取り上げたのはだいたいいままで書いた通りです。このあと結論が続くのですが、ここではいままで言及した概念がまとめられます。せっかくですので、ここでも取り上げておきましょう。 |
| 1.フィクション |
| 2.取り決め(お約束) |
| 3.疎外 |
| 4.循環 |
| 5.故郷(ふるさと) |
|
| この中で「循環」以外は本文で直接言及したと思います。この循環とは、理想的な夢の世界と事実による現実世界との循環のことをいいます。具体的には、秋葉原の事例、つまり夢の世界が現実に張り出してきていることの紹介や、鉄輪などの例で示したように、現実世界にフィクショナルの意味づけをすることなどがこの循環に当たります。 |
| そもそもこの「循環」の概念は、仏教の回向の考えから来ています。仏教では理想の浄土の世界が現世とは熱にあると説かれていました。つまりは死後に行く世界として浄土があったわけです。しかし、そもそも浄土は死後に赴く天国ではありません。そこは理想的な修行の世界であって、そこで仏になって再び衆生を救うのが狙いです。このように現世と浄土とは深いつながりがあるのですが、『南無阿弥陀仏』と称える功徳が仏様と自分をつなぐものと考えられ、親鸞はこの念仏は仏様から与えられるものであり、すべての功徳は仏様からの他力にあると考えるようになりました。 |
| このような回向の考えは、鉄輪で取り上げた一遍において、『南無阿弥陀仏』と称える現世そのものが浄土という考えになります。ここでは浄土と現世が一体化しているのであり、私が観光において理想とする夢の世界と現実との重ね合わせがある意味で実現しているわけです。私はリサーチペーパーでこのことにも触れましたが、今回のメールでは特に書きませんでした。 |
| 実は、このように私の発想は単なる思いつきではなく、その背景に深い思想的なつながりを持っています。実際に文字で書くのはその表面だけですが、本当はこの深みも理解してもらいたいのです。けれども、アカデミズムの現代の制度ではそもそもこの深みがないのではないかと感じられます。次回からは、このアカデミズムの問題と絡めて最近私が考えてきたことを述べてみたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(16) |
| 私が自分の考えを述べるにあって一番苦労するのは「フィクション」の概念がなかなか理解してもらえないことです。世間では“この物語はフィクションであり・・”というテレビのテロップが効いているせいか、それが真実を含み真実を実現する力があることをなかなか分かってもらえないのです。特にアカデミズムの世界はそうで、フィクションは真実とは相反するもとと見られているため、フィクションが実在を露わにするという発想が理解してもらえないところがあります。 |
| このフィクションの実在性をたとえて言えばこうなります。確かに実際に金がないのに大きな組織を作って金を採掘しようとすれば、それは無駄骨に終わるでしょう。しかし、本当に金があればこの組織を通して金は姿を現します。この組織の部分がフィクションで、金そのものがそれを裏づけるものですが、普通の人たちはそのように考えません。実際にそこに金がないのに、金があるように夢想するのがフィクションだと思っているのです。 |
| しかし、人間のフィクションをつくり出す能力、実在とは別に観念の世界を作り出す能力が人間を他の動物と異なったものとしたのは確かです。言語によって人は実在世界を観念によって再構成しますが、このことによって意思の伝達が可能となり、より意図的に自然に働きかけることができるようになったのです。有限個の言葉で無限の事象を表現できるのが言語ですが、これは人間のフィクショナルな能力の最たるものです。また数学にしてもそうで、数学のおかげで定量的に自然に働きかけることによって近代文明が成り立っています。人間はフィクションの力で自からの環境を変えてきたのです。にもかかわらず、個々の現代人は事実だけを真実だと思いこんでいるふしがあります。つまり、頭の中で見出される観念的なものはすべてフィクションであり、真実ではない。とにかく事実のみが、つまりは事実として目に見える事柄だけがあてになるものであるという感覚を持っているのです。 |
| このことは次のような人間のタイプにも現れています。ディズニーランドや秋葉原などの観光を考える時、このような観光地に対して次の3つのタイプの人間が考えられます。 |
| 1.これらの観光地は作り物であり、一時の気休めに過ぎないから無駄だと思う人。 |
| 2.たとえ作り物であっても、そこで見る夢は自分にとって必要であると思う人。 |
| 3.夢には現実を変える力があり、一見ただの作り物に見えても、観光には意味があると考える人。 |
|
| 一般の人たちはだいたい(2)のタイプに属する人間かと思います。しかし、(1)のタイプの人間もかなりいて、そういう人たちは自分たちは賢い大人だと思いこんでいるようです。しかし、本当は(3)が真実であり、人間は夢と現実の世界を「循環」しつつ、言語は数学のフィクションの力を借りて世の中を変えてきたのです。にもかかわらず、夢を馬鹿にする人がいる。“夢を見失なわないで”と言われることがりますが、夢によっていまの社会が出来上がった以上、実はこれは現代人の多くが現実そのものを見誤っていることの裏がえしなのです。 |
| 次回はこのことを深めるために、言語と数学、特に数学がいかなるフィクションであり、どれだけ現実を変える力があるか、ちょっと述べてみます。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(17) |
| 数学は純粋な抽象化による記号の学問です。ですから、私たちの経験から独立しているという点で観念の体系、つまりはフィクションと見なすことができるでしょう。しかし、このことは数学が実在世界を表現できないということではなく、むしろ数学は実在を正確に表現することによって近代科学の支柱となってきたのです。つまりは、数学の記号と実在とはうまく対応してきたのですが、これは実在を数学という物差しでうまく枠にはめ、その枠を組み合わせることによって逆に実在を明らかにしてきたといえます。 |
| このように考えれば、数学はうまく実在世界と対応してきたわけですが、数学が複雑になるにつれ、どうしても実在とは直接的に合致しない観念が生まれました。それは虚数と無限です。前者は実在からはみ出した数ですし、後者は頭で考えることができても、実際にあるかどうかは分かりません。私はこの2つの問題を実在とフィクションとの対応の問題として深く考えてきました。 |
| 虚数の方は割と速く結論が出て、これは間接的に実在と対応する数であることが理解できました。ある2次方程式の解が虚数になっても、それは現実の解を得やすいかどうかの度合をそれは示しています。例えば、その2次方程式が何かを作るためのものだとして、虚数解は現状ではxをいくら操作してもそれはできないことを示しています。しかし、方程式の他の定数をいじればxにも実数解ができる、つまりはそのものができることを意味しています。虚数解があまりにも大きいと無理ですが、小さければその調整は可能でしょう。虚数はその調整の度合を示す数だったのです。 |
| 問題は無限の方でした。無限にまつわるパラドックスは多いのですが、それは完全に解決されているとはいえません。だいたい微積分が成り立つのはなぜなのか、これが疑問でした。私がこの問題を解決したのは発想の転換によるものです。無限と有限との間には絶対的な壁があります。[無限の数+有限の数=無限の数]
というのがありますが、これは無限の量に対して有限の量は意味を持たないということです。しかし、実際にはこのようなことはありません。私たちが現実で扱う数は有限な数なのですから、イコールということは無いわけです。しかし、たとえイコールでもその状況が成り立つとすればどうなのか。これは現実の有限の数の世界をカバーすることになります。つまりは、無限の分だけフィクションの世界である数学は現実世界より広く、数学で成り立つことは現実でも成り立つのです。その意味で無限は数学において、実在から離れた純粋に理想的な観念だといえるでしょう。 |
| 私が数学の問題にこれだけこだわったのは、人間のフィクショナルな世界と実在世界との対応関係の限界を見極めたかったからです。普通、フィクションは物語の言葉と見られていますから、ここまで考える人は少ないのでしょうが、私は哲学者として気になったのです。実は、今回のAPUの研究の裏にもこのような表に出ない多くの問題意識がありました。私はこのような裏の問題意識こそ研究を豊かにすると思っているのですが、一般にはなかなか分かってもらえません。次回は現在の学問のあり方を含めて、その点を考えていきたいと思います。 |
|
| 私がAPUで考えてきたこと(18) |
| 現在の学問は自然科学をはじめ部分に当たるそれぞれの事実を集めることを重視します。つまりは、事実を的確に集めそれを積み上げることによって結論を得ようとするわけですが、これは社会を対象とする学問の多くが「○○科学」というところからも見て取れるでしょう。焦点を絞り、正確に事実を集め結論を出そうというわけです。しかし、社会を対象とする学問の場合、それでうまく行くでしょうか。社会科学などの他の学問を無視して経済学だけで経済を論じるのはナンセンスですし、これは他の分野についてもいえます。すなわち、各学問に通底する物事のあり方を知らなくてはならないのですが、このことはどうもおろそかにされているように思えます。 |
| 私は観光においてフィクションを論じる際にも、このフィクションについて数学基礎論からの考察をすすめました。また、哲学からもカール・ポパーという人の第三世界論というのを念頭に置いています。ですから、フィクションといっても絵空事とは考えませんし、むしろなぜ人間のフィクショナルな世界が実在世界と噛み合うのか、またはうまく噛み合わないのかを考えました。他の学者のように一般人の常識だけで考えているわけではないのです。しかし、彼らの多くはフィクションの概念を理解しません。これは彼らが常識に頼り、その一方で事実のみを学問の拠り所としているからではないかと思います。 |
| 確かに事実を明らかにしたり、事実の新しい解釈を打ち出すためには事実そのものの詳細な分析が必要です。ですから、巻末に付されているレファレンス(参考文献)というのが重要な意味を持つようになります。しかし、すべての学問が同じようにあらねばならないというわけではありません。新しい発想を打ち出す研究はレファレンスの量よりも日頃その人がどれだけ広く深い問題意識を持っているかが問われます。私の数学に対する考えはその一つです。また、時代が熟せば同時に同じような考えが生まれることがあり得ます。限界効用説の発見は同時に3人によってなされたといわれています。ネットの発達したいまではあまりそういうことはないでしょうが、それでも言語の違いなどがありますから、似たようなことが起こりえます。そもそもレファレンスによって他人の考えに振り回されていたら、自分で考える余裕はないでしょう。 |
| 私はレファレンスそのものを否定しませんし、それが論文の審査の形式的基準にある程度なるのは当然だと思います。しかし、その量にあまりとらわれすぎると学問の本質である発想を見失うのではないかとも考えます。正直、私が本を買う時チェックするのはこのレファレンスの量です。良い発想を本から得ようとする時、レファレンスが多く、註がやたらに短い本は買いません。結局はどこの誰かが言ったことの寄せ集めが多いからです。それに対して、註が結構長い本には注目します。そこにはこの本の発想が出てきた過程が見て取れることがあるからです。ウェーバーの本などその典型ですが、少し註を見ただけでも彼の問題意識の広さ、研究の深さが良く分かります。 |
| 事実を積み上げれば真実が得られる、これは現代人が暗黙に考えている知に対する前提です。しかし、真実というのは事実という形で客観の側にあるだけではなく、発想という形で私たちの側にもあるのです。次回はそのことを明らかにしていきましょう。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(19) |
| 現代人は事実を重要視します。それは具体的に目に見えるものを確実なものとしているからでしょう。これは実際の個々の事象を基礎に物事を考える見方であり、哲学的に言えば、個物をそれの属する類とか種よりも優先させる考え方です。これは専門用語で「唯名論」といいます。この唯名論では、確実なのは個々の事実、物体だけであり、類や種などは人間が付けた名前に過ぎないということになります。厳密に言うと、犬や猫も動物の種類になりますから、これも人間が名前を付けたものに過ぎないとなりますが、これらの違いは実際に目で見ることができるので、これまで人間が勝手に名前を付けたものだと考える人は少ないでしょう。 |
| しかし、「資本主義的生産様式」とか「封建社会」とかの抽象的な用語になるとどうでしょう。これは人間の想像力がつけたもの、勝手な理屈づけで誰かが言い出したものと考える人はいるではないでしょうか。少なくとも、これらは主観的な物の見方の産物だと思う人は多いように思います。現代人は、どうも人間の頭で考えたフィクショナルな事柄を絵空事と考える傾向があるようで、なかなか目に見える具体的な個物を持ってこないと納得しない、つまりは事実にしか納得してくれない傾向があるようです。しかし、これは間違った物の見方と私は考えます。 |
| 個々の事実は写真でいえばドットの部分に過ぎません。確かに正確にドットを集めれば写真はきれいになります。しかし、その写真に写っているものを他のものからうまく区別する認識力がなければ、私たちはその写真を理解することができません。学問的な理論も、多くの事実に裏付けられるにせよ、結局はこの区別する認識力が重要なのではないでしょうか。ドットの少ない写真でも何が写っているかを推測することはできます。しかし、この認識力なしには何が写っているか推測すらできません。個々の事実偏重の学問では結局木を見て森を見ない傾向に陥ります。実際には、特定の分野の「あり様」に眼を向けても全体の「あり方」を見ない傾向が生まれます。 |
| 二等辺三角形の向かいあう2つの角が等しいことを証明する時、いくら三角形全体を眺めていても結論は出ません。真ん中に補助線を引くことによって2つの直角三角形の合体したものがこの三角形と理解した時、答えが出るのです。学問で重要なのはこの補助線を引く能力です。ある特性に従ってあるものを他のものから区別する、そのことによって全体の「あり方」が浮かび上がってくるのです。私の研究の例を取れば、ゲゼルシャフト(近代的市民社会)とゲマインシャフト(従来の共同体)との区分がそれに当たります。 |
| ウェーバーはこのことの重要性を認識していたようで、ゲゼルシャフトとゲマインシャフトの両概念に注目するだけではなく、理念型という形であり方の違いに注目していました。しかし、このような試みはその後には顧みられなかったようです。何でも定量化し、その量によって対象を理解しようとするのが現代の学問のあり方であり、科学の名の下による専門化もこのことによって進んだのですが、定量化とは質的な違いを無視することに他なりません。一方、科学が学問の条件であるように見なされる反面、哲学はその居場所を失いました。これは長い伝統を持つ学問の歴史から現代の学問が遊離していることを示しているのではないでしょうか。次回はこの観点から書いてみます。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(20) |
| 私の大学での勉強は博士論文を出す前段階で止まっています。ちょうどその段階で病気が発覚したせいですが、タイミング的には良かったと思っています。ただ、前段階での審査は私が見る限り混乱したものであり、時として教授陣の意見の不一致が事を非常に混乱させていたのではないかと思います。普通、博士論文は指導の先生が了解をすれば提出できるのですが、APUの場合審査委員会のチェックが必要です。そのことが問題を大きくし、留学生の中でも博士を諦める人がでました。 |
| だいたい社会を対象をする分野において、専門外の人が審査できるのは形式的な事柄だけです。しかし、そのようなチェックがなされたとすれば多少の修正がなされただけで済んだでしょう。私のような論文は哲学のセンスのない人間には「分からない」のが当然ですが、このことが大きなネックとなりました。また、観光にしても環境にしても、1つのテーマにはいろいろな立場からのアプローチがありますが、この学問的な立場を理解できるのは指導の先生しかいない場合も多いのです。このような学問そのものに対する理解の不足が事柄を混乱させたのでしょう。 |
| 私はここに哲学の貧困を見ます。哲学は前回触れたように、大きな視野から全体を区分し新たな視点を提供する能力です。そのためには、特定の学問にとどまらず、あらゆる学問に関心を持ち、実践においても同様な形で広く知恵を求める態度が必要です。ところが、現実には専門馬鹿といわれる人が多く、社会を専門とするにもかかわらず、実践に縁のない人も多いのです。これが哲学なきいまの現状といえるでしょう。 |
| 哲学は西洋では「愛知学 フィロソフィー」と呼ばれてきました。知を愛する学ということですが、私はこれよりも「哲学」の方が好きです。というのも、知を愛することは哲学の表面的な部分を他人が外から見ただけで判断した結果とも取れるからです。謂はば、「オタク」という感じでしょうか。哲学する人は、世の中の根本的な「あり方」を探し求めます。そのためには、知の分野を問わずあらゆる知識や知恵を求めるわけですが、これは手段に過ぎません。本当は哲学する人は知を通して世界を愛しているのです。ですから、その本質をズバッと見出す概念、つまり区分を世の中の諸々のあり様の中に求めるのです。しかし、これは唯名論的な立場からすれば、フィクションの産物であっても、実在の裏付けを持たないものです。 |
| 私はこの中に自らフィクションの産物の中に埋もれながらも、自身のフィクションを絵空事としか考えない現代人の弱さを見ます。その意味で、現代人は「唯名論」の名前を知らなくても唯名論的感覚におかされているのです。次回はこの唯名論が実在を拒否することによって、人間の意識の世界に閉じこもっていることを明らかにしてみましょう。 |
| 「リアルワールドなんて全然リアルじゃない」というのは確かあるアニメにあったセリフですが、事実だけで構成され、単に「気晴らし」のみを提供しようとする社会はたとえ事実によって構成される社会であっても決してリアルといえる社会ではありません。紆余曲折はあるにせよ、個人のフィクションが社会のフィクションを通して現実の世界と重なり合う社会、その中で自らの居場所を見出し行動する場を見出すこと、つまりは故郷を見出せる世界が本当にリアルな世界といえるのではないでしょうか。何が「リアル」かというのは日本のアニメが長年追い求めてきた問題ですが、私は観光を通じて観念の理想世界と事実の現実世界とがうまく重なり合うことによって、この立場から一定の答えが出せるのではないかと思っています。 |
|
| 私がAPUで考えたこと(21) |
| 私が唯名論を嫌うのは、極端なそれが「私にとってだけ」の立場に固執する独在論な立場に移行するからです。実在は「私にとってだけ」存在する、だから私が実在の側に踏み出してそれと交わることがない、これが私が一番恐れるところです。極端な実在論もこの点は同じで、実在の意味をなす類や種はすでに実在の側で決められているから、私の側の行動は意味が無いというものです。 |
| 実際には、実在がどのような種や類に属しどのような意味を持つかは実在たる客観の側と私の側たる主観の側との関わりによります。客観は私に実在を与え、主観たる私は主体として行為することによって実在の中で自らを生かします。その時に重要になるのがこの2つを包摂する環境です。私たちはその環境に従って実在の意味を見出し区分をなしているのです(このことについては多義図形の解釈が参考になります)。この日常的活動そのものが「生」と呼ばれるものなのであり、私たちは常にこの環境に配慮をしなくてはならないのです。 |
| そもそもこの環境が実在がこうある私がこうあるという現実の根拠となっていました。いまの実在と私との関係はその中の一時的なものにしか過ぎないのです。このことを知る時、私たちは自身を超える大きな存在に気づかされざるを得ません。それを神と呼ぼうと、法と呼ぼうと、それはいまここにあって働き続けているのです。にもかかわらず、現代人の多くはこのことに眼を向けません。人間が生きていくために必要なもの、使用価値の高いものは99%以上この大きな存在から与えられたものです。しかし、人間はその中で希少性のあるもの、労働力が関わるものなど、ごく一部だけを論じて経済学を成り立たせています。現代人の知的活動などはそんなものかも知れません。 |
| 私は長年哲学を続けてきました。科学基礎論から自然哲学、はたまた社会哲学から宗教哲学までです。そんな中で結局私が気づいたのは、「私にとってだけ」の立場を廃することがその実践的目的ではなかったかということです。「独在論の誘惑@(アニメのこと)」もそうですし、APUでのフィクションの考察もそうです。最初は自然への憧憬から始まった私の哲学ですが、その現実的な意味においては私を超えることがそのテーマではなかったかと思っています。 |
|
|
|