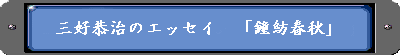|
鐘紡は歴史の古い会社である |
| 1887 |
鐘紡は明治20年(1887年)に誕生した歴史の古い会社てある。 |
|
我々が過去80余年にわたる鐘紡の歴史をたどるのは、単に先達の事鎚を知り、苦難の歳月、栄光の日々を回想するためてもなく、まして社歴の良さを誇り、輝かしい伝統を誇示して社外に宣伝するためでは決してない。 |
|
我々は社業の盛衰や先達の事鎚をiあるがままの姿に於いて見つめもう一度考えなおして、それから新しい意味を妄及みとらねばならないと信じているのだ。 |
|
|
|
鐘紡は紡績業から出発した |
|
ようやく産業革命を迎えた臼本カミはじめて興した近代自勺工菜は明治15年頃から開始された工拳としての綿紡績菜てあった。原始的には日本の紡績業は三つの流れがあった。即ち〈1〉藩の殖産事発としての紡績工場 〈2〉官営模範工場 (3〉純粋の民間企業の三つてある。 |
|
明治中期には純粋の民間紡績間のみが残されていた。これには権勢の庇護に縋って育った紡績業と、独立独歩の紡締とては最初からその気迫に雲泥の差かあり、技術的にも経営上からも一歩ぬきんてていたことか一つの大さな原因てあった。この独立独歩の精神か、この業界の伝統となる素地はこの時につくられたのてあった。 |
| 1886 |
〈明治19年〉東京日本橋に9軒の繰綿問屋があったが、その中の5軒がシナ綿の定期売買を主業とする東京綿商社という資本金10万円の会社を創立した。 |
| 1887 |
〈明治20年〉ところか需給の関係から、綿花の在庫に悩まされ.、その打開策として90万円の増資を断行し、紡績経営に乗り出すことになった。5月6日設立登記。8月、「東京綿商社」を解散し「鐘ヶ淵紡績株式会社」と改称し、初代社長に三井得右衛門が就任した。 |
| 1888 |
〈明治21)三井の出資を得て土地を東京府南葛飾郡隅田村隅田川畔「鐘ヶ淵」に求めイギリスより最新式の機械を輸入して模範的工場の建設に着手した。 |
| 1889 |
〈明治22年〉工場の設計は挙げて学者に託し、費用を惜しまず建材や設備に舶来品を用い、30,240錘の当時我が国最大の工場を造った。世間てはこの工場を見て「三井の道楽工場」といったという。 |
|
|
|
初期の苦境 |
|
こうして出発した鐘淵紡績株式会社てはあったが明治25年頃までは極度の経常難であつた。その原因としては |
|
〈1〉機械と人間の調和を欠いたこと。〈機械に人間がついていけないほど機械が最新式であったともいえる) |
|
〈2)熟練工はもとより職工数も不足していたこと。 |
|
(3)日本綿は糸切れが多かったこと。 |
|
等が挙げられる。 |
|
しかし、これらの創業期の苦しみも後年の大を成すための貴重な試練てあった。例えば日本綿は糸切れが多かったことは、インド綿の使用と混綿技の開拓を進めることになったのてある。 |
|
|
|
中上川彦次郎の登場 |
| 1892 |
初期の経営の失敗から、株主問には解散を主張する者もあつたが、監査役の稲廷利兵衝かこれに強く反対し三井家の顧問てもあつた井上馨を動かし、井上の命により、・中上川彦次郎が改革に乗り出した。中上川は明治25年の第10回総会に於いて、朝吹英二と共に取締役に就任し、明治26年に社長となり朝吹を専務に鐘紡の積極的経営に乗り出した。 |
| 1894 |
中上川は紡績菜の将来に遠大な抱負を持っていたのて明治26年に東京工場に10・000錘の第二工場を設け、さらに朝吹と謀つて第二次の拡張を断行することとなった。それも工場を関西紡績業地の真只中へ進出させ、そこに、大陸を柏手とする大紡績工場を営もうとする意図て明治27年兵庫支店を設立、40,000錘の工場建設に着手した。 |
|
|
|
朝吹英二 |
|
朝吹英二は中上川の妹婿てあるが、専務に就任してからは人力車は不経済だからと自転車て会社通いをはじめたような人物て「仕事に厳しく、人には温かくを実躇した人てあつた。 |
|
その頃、どこの会社ても賄(まかない、食堂)は請負になっていたのを直営にしたのも朝吹てある.請負だと利益をあげねばならないが、直営ならば会社が負担すればよい、それだけ食物ガよくなるというのて、日本最初の賄直営をはじめたのてある。 |
|
|
|
中央l司盟会との紛争 |
|
明治20年前後から大規模な紡績工場の出現て、労働力とくに熟練職工が不足し層々職工の奪い合いがみられた。紡績適合会は職工に関する規約を強化したが、これには鐘紡も加盟していた。ところか明治25年頃から各社の増錘、新工場建設か盛んとなり、職工不足は再び甚だし<なって釆たのて、明治26年には新たに中央綿紡績業同盟合が結成された0同盟会によって職工の雇い入れ、解雇、給与、労働時間、疾病、衛生、賞与、貯金、懲罰まて詳細に規定し、職工の移動を防止せんとしたものてあった。 |
| 1896 |
鐘紡兵庫工場が明治29年に操業を開始すると、約3,000人の従業員を必要とし、また、当時鐘紡の待遇は日本一てもあったのて他社を退めて鐘紡に入る者か続出した。 |
|
中央同盟会はこれを大きく取り上げ、全国新聞に広告し、当社に対して宣戦を布告するにいたった。中央同盟会から再三の入会勧告があったが、兵庫工場支配人武藤山治は、「職工は自己の欲する工場に移動する自由を奪われることになり、自然会社側に於ても賃金待遇上に進歩、改善の必要がなくなり、職工の利益幸福は非常に殺がれる」として頑として入会しなかった。 |
|
これに村し、同盟各社は綿花綿糸を取扱う商人や運送業者に鐘紡との取引中止を要請し、さらに大阪の侠客に依頼して鐘紡の経験工を連れ出してきた者には金5円、本人に1円、未経験工を連れ出してきた者には金3円、本人に1円を出すことにした。そして武藤に全治1週間以上の傷を与えた者に300円の賞金を出すと言ったという。 |
| 1897 |
この紛争に中上川が乗出して、三井銀行が同盟側の各社との取引を拒絶するまてに至り、財界の重大問題となった。そして遂に日銀総裁岩崎弥之助の仲裁に委ねることとなり、渋沢栄一もこの間を斡旋して、同盟の規約の一部を修正するかわりに鐘紡も入会するということになって明治30年2月15日を以て落着した。 |
|
この事件は我国紡績会社の職工待遇上一大転機を画したもので、鐘紡の人間尊重の精神は世間に高く評価されると共に、これを契機に紡績会社全般の待遇が改められたことは事実てある。 |
|
|
|
武藤山治 |
|
三井銀行神戸支店副長をしていた武藤山治が朝吹英二によって中上川に推挙され、鐘紡に入社したのは明治27年4月てあつた。以後昭和5年1月まて36年にわたり鐘紡の経営に当り、終始ヒューマニズムを貫いて、当時稀有の縫営者として注目を浴びた。 |
|
|
|
ヒューマニズムと進歩牲 |
|
山治は企業の許すギリギリの線までヒューマニズムを貫徹した稀有の経営者として、又常に進歩的経常施策を実践する時代の先駆者として名声を馳せたのてある。 |
| 1899 |
明治32年本店支配人となってから2年程は極度の金融雉に見舞われる等、苦心を重ねたが、山治は常々抱いていた従業員の幸福増進のためいろいろの施策を着々と実施しはじめた時には厚きに過ぎるとして社内や外部の同業者から非難を浴びるほどてあった。 |
| 1919 |
大正8年5月にワシントンて開かれた第1回国際労働会議こ雇主側の代表として出席した山治は鐘紡従業員に対する待遇方法の英訳本を出席者に配つた。これは各国委員や顧問の中ても労働者側の委員間にセンセーションを捲き起こし、このため日本から出席した労働者側代表は却つて各国の同情を失なうような結果にもなった。 |
|
|
|
鐘紡の福利厚生 |
|
大正14年に発行きれた『女工哀史』は紡績工場の職工の立場から見た当時の紡績工場の実態を描いたものてあるが、その中てさえ「鐘紡は別だが」という鐘紡賞賛の言葉を随所に散見するのてある。(例えば職工に対する電話の扱い、社宅事情、工場内の床の整備状況、医局の医師の態度、休日の催し物、休憩施設、等てある。) |
|
|
|
温情主義論争 |
| 1925 |
このような鐘紡の経営は「温情主義」と呼ばれたが これに対して一部に批判的な者もあったことは事実てある。大正8年から大正10年にがナて京大の河上肇と武藤との間に行なわれた温情主義論争はその一つのあらわれである。 |
|
前述の第1回国際労働会議こ出発する前に、山治は雑誌『タイヤモンド』に「吾国労働問題解決法」という論文を公にした。この中て山治は、近来学者論客の中には温情主義排斥の議論を為す者が多いけれども、それは西洋の労働者と日本のそれとの境遇を同一視することによつなされる誤つた議論てあり、西洋の労働史には温情主義の時代はないから、労働者は権利を主張するのは当然てあるが、だからといつて労働者が権利を主張しさえすれば労働問題は解決するかの如くいうのは誤りてあると述へた。 |
|
これに対して河上は『社会閑地研究』に載せたロバート・オウエン評伝の中て多少冷かし気味に論駁し、温情主義は日本独特のものてはなく、西洋にもそれ以上の温情を労働者に注ぐ事業家かあると述べた。これをきっかけに何度か論争がなされたが、議論か噛み合わぬ面もあり、両者共納得せぬまま自然消滅した。 |
|
このような批評はあつたにせよ、山治は「鐘紡の経営方針でも営利よりは道義に立脚することを信条としていた」ことは確かてある。 |
|
|
|
武藤山治の事蹟 |
|
| 明治35年 |
(1902) |
男女工手のため補修学校設立 |
| 同 |
, |
女工手のため乳児保育所設置 |
| 明治36年 |
(1903) |
注意書箱設置(自己を表現することの比較的少なかった当時にあつて、従業員の声を聞こうという試みあった) |
| 同 |
, |
『鐘紡の汽笛』創刊、後に『女子の友』発行(共に現在の社内報てある) |
| 明治38年 |
(1905) |
鐘紡共共済組合設立(ドイツクルッブ社から学んだ制度で、現在の健康保険の揺籃であった) |
| 同 |
, |
鐘紡職工学校設立 |
| 大正 3年 |
(1914) |
職工幸福増進係を置く |
| 大正 4年 |
(1915) |
精神的工場操業法を実施 |
| 同 |
, |
高砂保養院を創設 〈従業員の転地保養先) |
| 同 |
, |
年金制度発足 |
| 大正 7年 |
(1918) |
鐘紡研究所を設立(理化学研究所を範とした研究所) |
| 大正12年 |
(1923) |
鐘紡無料診療所を開設(現在も鐘紡病院として残っている) |
|
|
|
|
戦時体制下の鐘紡 |
|
鐘紡が在華紡(中国本土にて紡績業を営むこと)として大陸への進出を企てたのは大正8年中国の関税改正で関税自主権を取り戻し、日本製品に対する関税引上げによって、日本品の中国進出を抑えようと図つたことへの対応である。これを見てとって、資本と機械と技術をもって現地に乗り出すことになったものである。 |
|
鐘紡の最初の在華紡は大正11年の上海の公平紗敞である。日本の紡績が当初上海に工場設置を集中したのは、治外法権の共同租界があり、租税負担は日本内地はもとより、中国人紡績より軽く、著しく経営を有利にしたためてあった。なお鐘紡はすでに明治44年に絹糸を合併した際、同社の経営下にあった上海製造絹糸の工場を経営下におさめていたので、実際には鐘紡の大陸進出はこの時すてに行なわれていたものとみてよい。 |
| 1930 |
このように鐘紡は海外にまて発展を開始していたが、昭和5年春、淀川工場に大掛かりなストライキが起り、全社に波及した。その頃、経済情勢は、第一次大戦後の異常な好景気の反動として世界を襲った恐慌のさなかであった。紡績業者は戦後の好況期の体制のまま、整理調整の必要を感じながらも、思い切った企業の合理化には手をつきかねていた。 |
|
そこへ鐘紡が企業合理化の先頭を切って、賃下げ等を発表した。その内容は「戦時手当支給を廃止し、あらためて一律3割の特別手当を支給する」というものてあった。戦時手当とは第一次大戦による物価騰貴に対応するものとして出された臨時給で、社員には本給の6割、職工には日給の7割を支給し、以来10年間続いてきたもので、この貸下げ等によって社員は本給の3割、職工は日給の4割を削られることになり、本給、日給を含めると、各自の実収入は2割3分程度の減収となり、会社側は年間300万円の経費節約を見込んでいた。ところが当時鐘紡は3割5分という高率配当をしており総同盟の西尾末広の指導によって大争議が起きたのてある。 |
|
この争議は解決まてに56日間を要したが、西尾末広に立ち向い一歩も退くことなく、堂々と所信を貫いたのが、当時副社長になったばかりの津田信吾てある。後に西尾は「(従業員例の態度も立派だったが)それにもまして津田の態度は立派だった。教え子に対する情愛と会社の重役としての威厳と落ち着きを兼ね備えた立派な態度てあった。」と述べている。 |
|
|
|
戦時下の紡績 |
| 1937 |
戦時体制下の紡績菜の変化は昭和12年から昭和16年の対日資産凍結まての期間と、太平洋戦争突入以後との二つの段階に分けられる。 |
|
第一段階は軍需物資や生産財を輸入するための外貨獲得の手投として、繊維は輸出促進、内需抑制の政策がとられた頃てある。輸出品以外には強制的にスフが混用されることになり、木綿物の買いだめが起り、真冬にユカタの売れたという。 |
|
第二の段階は、円域以外の綿花輸入は全く杜絶し、生産は大巾に縮小され、企業の整備統合と、遊休設備の軍需転換が進められた頃てある。したがって紡績業にとっては生産は縮小の一途を辿るばかりて、かっての黄金時代とは似ても似つかぬ日々を迎えることになった。強いてプラスの面をとりあげるなら、強制的なスフの混用で、戦後における化繊工業確立の基盤がこの時代に培われたことぐらいてあった。 |
|
昭和13年鐘紡は資本金を6千万円から1億2千万円に増資して事業の拡張につとめていたが、昭和13年11月資本金6千万円で新たに鐘淵実業株式会社を創立し、繊維部門以外の各種事業に手を伸ばしはじめた。昭和19年2月両社は解散して、鐘淵工業株式会社を設立し、資本金3億2千4百万円、社長に津田信吾、副社長に倉知四郎が就任した。昭和19年末の鐘淵工業の事業は、直営事業域129(内国内87、海外42)直系会社52社を数え、民間企業としては日本で最大の会社であった。その事業内容は繊維は言うまてもなく、各種鉱業、金属、航空機部品、化学、パルプ、製紙、農牧畜業にわたっている。 |
|
|
|
企業の規模比較 (昭和11年の上位30社) |
|
| 順位 |
会 社 名
|
収入 |
順位 |
会 社 名
|
収入 |
順位 |
会 社 名
|
収入 |
| 1 |
日本製鉄 |
332 |
11 |
明治製糖 |
85 |
21 |
片倉製糸紡績 |
55 |
| 2 |
鐘ヶ淵紡績 |
301 |
12 |
大日本麦酒 |
75 |
22 |
神戸製鋼所 |
54 |
| 3 |
王子製紙 |
231 |
13 |
古河電気工業 |
75 |
23 |
郡是製糸 |
51 |
| 4 |
三菱重工業 |
120 |
14 |
日立製作所 |
73 |
24 |
旭ベンベルグ絹糸 |
43 |
| 5 |
内外綿 |
110 |
15 |
日本石油 |
71 |
25 |
日本塗料製造 |
42 |
| 6 |
三井鉱山 |
101 |
16 |
台湾製糖 |
70 |
26 |
住友金属工業 |
42 |
| 7 |
日本鉱業 |
95 |
17 |
日本鋼管 |
61 |
27 |
大日本紡績 |
41 |
| 8 |
三菱鉱業 |
94 |
18 |
富士瓦斯紡績 |
56 |
28 |
日本電気工業 |
40 |
| 9 |
大日本製糖 |
89 |
19 |
旭硝子 |
56 |
29 |
東京電気 |
40 |
| 10 |
日本毛織 |
87 |
20 |
東洋紡績 |
55 |
30 |
日清紡績 |
39 |
|
|
(注)昭和11年、収入は売上高、投資収入及び雑収入の合計(単位百万円) 三菱経済研究所「本邦事業成績分析」により作成 |
|
|
|
昭和19年当時の鐘紡直営・直系事業 |
|
| 兵 器 |
4工場(内3、外1) |
航空機用部品 |
8社(内7、外1)) |
| 航空機部品 |
7工場(内) |
造船舶用関連機器 |
7社(内) |
| 造船舶用関連機器 |
4工場(内3、外1) |
製 鉄 |
2社(内) |
| 製 鉄 |
6工場(内2、外4) |
鉱 業 |
3社(外) |
| 鉱 業 |
7工場(内2、外5) |
軽金属工業 |
3社(内) |
| 航空燃料・化学工業 |
6工場(内5、外1) |
航空燃料・化学工業 |
7社(内6、外1) |
| 繊 維 |
|
繊 維 |
9社(うち3、外6) |
|
|
| 15工場(内9、外6) |
| 18工場(内15、外3) 内外研究所5乾繭場1 |
| 7工場(内) |
| 6工場(内4、外2) |
|
・ |
・ |
| パルプ及び製紙 |
3工場(内2、外1) |
パルプ及び製紙 |
5社(内) |
| 油 脂 |
2工場(内) |
油 脂 |
2社(内1、外1) |
| 窯 業 |
3工場(内2、外1) |
農 業 |
1社(内) |
| 製薬・化粧品 |
2工場(内)) |
水 産 |
1社(内) |
| 農・牧畜 |
農牧場など外20ヶ所 |
その他 |
4社(内3、外1) |
| 研究所 |
3(内) |
、 |
、 |
|
|
|
(注)田中宏 『鐘紡の系列』 直営事業 119事業場 直系事業 52社 |
|
|
|
敗戦による痛手と復興 |
| 1945 |
戦時体制の事業の拡張と発展は、当然敗戦こよる打撃を大きなものにした。紡績10社の内ても戦争による損失の最も大さかったのは鐘紡てあり、その特別損失の合計額は12億4千万円余と、第二位東洋紡の倍額てあった。戦時中の企業整備によつて昭和16年当時の設備の半分を供出した上に、戦災によって喪失した設備の帳簿価格が1億円余、戦争で喪失した在外資産が3億円余てあった。 |
|
昭和20年12月、津田社長が追放て退社、副社長の倉知が社長となったが、やがて倉知も財界追放となり、昭和22年6月武藤絲治が第10代目の鐘紡社長に就任した。昭和21年5月社号を鐘淵紡績株式会社の旧商号に改めたが、昭和21年12月には特殊会社に指定きれ、さらに昭和23年2月には過度経済力集中排除法による指定を受けた。 |
|
武藤は紡績10社と共同歩調をとって、指定解除を総司令部に働きかけ昭和24年3月、全面的にこの指定はとり消された。武藤が最も頭を痛めたのは、12億円余の戦時特別損失金の処理てあった。一時は資本金の9割、旧債権の2割8厘を打ち切らねばならぬ破目にさえ陥つた。 しかも法律に基いてそれはてきることてあった。重役の中には、後に負担か残るからこの際切り捨てて、新しい会社として出発した方か良いという意見も多かつた。しかし彼はこれに反対し苦しい中からのやりくりで、見事この難局を切り抜けた. |
|
戦後の鐘紡の復興は、次の三つの時期に区分することがてきる。 |
|
(1)終戦からドッジラインまての復興と再建の時期(昭和20~昭和24年) |
|
前述のような経過を辿つて戦争の痛手から奇捌的に立ち直った鐘紡は昭和24年に化学部門を分推し(鐘淵化学)、再出発の歩みを始めた。昭和24年には3S運動が提唱され、新しく3Sバッジ(社章)、社旗、社歌が制定きれた。「鐘紡新聞」の創刊もこの年てある。 3S運動とは、スピード、サービス、セービングの3つの運動をいう。 |
|
(2〉朝鮮動乱ブームの発生から、デフレ政策が実施される問の設備の拡大と、経営の飛躍的発展の時期(昭和25~昭和26年) |
|
いわゆる糸ヘンブームで、この時期に新規に紡績業を始めるものが続出した。(新々紡) |
|
(3〉合理化と近代化の推進による経営の充実と企業基盤の強化を図つた時期(昭和27~昭和32) |
|
|
|
不況対策 |
| 1958 |
繊維産業の不況は他の産業に先がけて昭和32年初めにはすてに現われはじめた。繊維業界があらゆる繊維部門にわたって不況に突入したのは、戦前戦後を通じて初めてのことてあった。このため昭和33年4月の各社決算は軒なみに収益の低下を示した。鐘紡も例外てはなかった。ここに至って、昭和33年9月末曽有の不況を克服すべく歴史に名高い「不況対策」を実施したのてある。この内容は従業員の貸金を1年間1割カットし、幾つかの不採算工場は閉鎖するというドラスチックなものてあった。 |
|
当時、産業界は朝鮮動乱の特需、神武景気といった好況と不況とが繰り返される不安定な時期を迎えていた。そして昭和33年は最大の不況の波カくおし寄せていたのてある。統計によれば、この年の労働争議の総件数は1.864件、総参加人員は636万人を数え、警職法改正反対闘争とからんで争議は激化の一途を辿ったのてある。そして、この年の争議て特徴的だったのは、不況を反映して企業整備・人員整理反対のための争議が非常に多かったことてある。 こうした状勢の中て「鐘紡の不況対策」は実施きれた。全従業員は打って一丸となり「鐘紡護持の精神」に徹し、賃金の切下げに応じ、慣れ親しんだ職場を離れて合理化に協力した。鐘紡のいずれの事業場にあっても赤旗一本立つことなく、労働歌の合唱きれることもなく、ただひたすら鐘紡の理想実現のために、この試練を克服したのてある。 |
|
この不況合理化を通して鐘紡は労使間係を単なる利害村立する斗争の関係としててはなく、運命を共にするパートナーとしての新しい労使間係へと発展する契機を作ったのてある。即ち鐘紡労使の考え方は①「生産における労使の信頼にもとずく協力」②「分配における労使の誠意ある協議」ということてあり、「会社の繁栄は従業員の繁栄てあり、日本の繁栄にもつながる」という考え方に発展するのてある。 |
|
|
|
不況対策の成果 |
| 1961 |
労使一体となつての必死の努力により、昭和34年4Rには黒字に転換し、昭和35年10月には売上高、利益高共10大紡のトップに躍り出て、鐘紡の戦後第二の奇蹟と云われたのである。(第一の奇跡は戦後の復興)。そして労使間係における運命共同体理論そして事前協議制は不況対策というキャンペーンのなかて生れ、育ち、成長したのてある。 |
|
不況村策が成功し業績が回復すると直ちに一年間にわたってカットされていた賃金は一括して支払われ、新たに退職金の増額・女子優遇資金の設定(勤続の短しい女子従業員に退職金面で優遇する)・持家奨励制度などを内容とする従業員繁栄村策が次々に打ち出され、同時に長期経営計画として安定5ヵ年計画を発足させたのてある。 |
|
|
|
GK(グレーターカネボウ)計画 |
|
昭和36年には「より偉大な鐘紡を建設し、従業員の幸福に資する」ことを目的に、第一次クレーターカネボウ建設計画(GK計画)か発足した。天然繊維から合成繊維へ、そして労働集約的産業から資本集約的産業へと転換を計らんとするものてあった。綿紡績業から出発した当社にとっては画期的な転換てあった。具体的こは、昭和37年にナイロン部門・化粧品部門に進出し、翌38年には食品部門に進出した。 |
|
天然繊維を中心にしていた鐘紡が、多角化の道を歩みはじめるのてあるが、これは単に利益の追求のみならず衣食住という人間の基本的生活を豊かこし、総合の美を追求することを企業の発展目標としたものてある。昭和39年には第一次GK計画達成に引き続き、第二次GK計画が発足、「従業員繁栄協定」が労使間で締結され、「会社の繁栄は従業員の繁栄である」という労使共通の理念が具体化されたのてある。 |
|
|
|
現状と展望 |
|
昭和43年6月、武藤絲治は会長に退き、社長に伊藤淳二が45才の若きで登場し、経営陣の若返りが実施された。 |
|
直ちに、〈1〉ナイロンを中心とする合繊部門の拡大 |
|
〈2)天然繊維部門の自動化による安定 |
|
〈3)化粧品部門の充実 |
|
などを骨子とする長期計画が立案発表された。 |
|
そして今、カネボウは世界に比類なさ紡織技術をもった総合化学会社へと飛糾しようとしている。一方、未来産業としてのファッションビジネスに取り組むことを栄光の1970年の年頭に発表し、大きな注目を集めた。三年間の実績によって名実共にファッション産業界のリーダーとなったカネボウは、更に1972年6月、ペンタゴン経営を基盤として、人類の生命、生活の成長と向上に貢献しようとする「ヒューマンライフインダストリー」への展開を打ち出したのてある。 |
|
かけがえのない地球に生を受けた我々は、一日一日を大切にしたい。生さ甲斐に満ちたヒューマンな日々てありたいと希求している。、カネボウは今、この世にバラタイスを創る一助になりたいと願っているのてある. |
|
|
|
結語・・・歴史の継承者たれ! |
|
以上80余年の鐘淵の歴史を辿つて、我々はそこに流れる二つの伝統を汲み取ることがてきる。一つはヒューマニズムてあり、他の一つは開拓者精神と科学的合理主義に基く時代の先駆者としての勇気てある。我々は先人のヒューマニズムに学び、日々の生活の場において実践すると共に、常に時代の推移を見極め次代へのヴィジョンを持って生きることを学ぶのてある。社史の表面に表われる人名は決して多くない。我々はその人々の陰の力となった無名の人々の血と涙を常に思うへきてあろう。 |
|
「ローマは一日にして成らず」されど大ローマは瓦解した歴史的現実を思う時、鐘紡を決して瓦解させてはならない。歴史の継承とは。先人から手渡された遺産を更に量質ともに高めて、次代にバトンタッチすることである。最後に、歴史の継承者として崇高な責務を果たすことを共に誓い合おう。 |
|
|