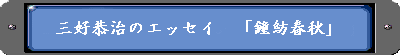| 定年退職までの東京二年間の予定された生活の中で、泊まってみたい宿は幾つもあったのだが、なかなか時間の余裕もなく、結局「思い込みの宿」としては五軒を訪れたに過ぎない。故里に帰郷後の四国からの旅行は、結構もの入りにはなるが、年一軒程度は自分なりに納得できる宿を夫婦旅で計画したいものだと思う。 |
| ところで、「思い込みの宿」五軒とは |
| 1) 日光金谷ホテル |
| 2) 箱根宮の下富士屋ホテル |
| 3) 上高地帝国ホテル |
| 4) 軽井沢万平ホテル |
| 5) 尾瀬長蔵小屋 |
|
| である。 |
|
|
| 1) 日光金谷ホテル |
| 日光金谷ホテルは、日本で「最初のホテル」という歴史的事実もあり、有名過ぎて特に記す必要はないのかもしれないが、一冊の書籍の出会いから、私にとって「忘れられないホテル」となり、「訪れてみたいホテル」となった。 |
| 平凡社の東洋文庫(二四〇)に入っているイサベラ・バード著「日本奥地紀行」(高梨健吉訳)が描いた明治十一年の陸奥や蝦夷の風光、民俗、世情の描写にうんざりしながらも、日光の金谷一家の出会いと、置賜(米沢)盆地を「東洋の平和郷」というべきだとの激賞は大いなる救いであった。米沢の上杉鷹山の治世については、内村鑑三が「代表的日本人」(REPRESENTATIVE MEN OF JAPAN)を一九〇八年に刊行し、岩波文庫にも入っている。 |
| 一方、イサベラ・バードの「日本奥地紀行」は、チェンバレンが明治二十三年(一九八九)に「本書は英語で書かれた最善の日本旅行記である」と称賛しているが、彼女は明治十一年四十七歳で米国から日本を訪れ、横浜で宣教師ヘボン博士(ヘボン式ローマ字で著名)の家に滞在し、博士の諸注意を受けて、日本青年伊藤と二人で「日本奥地」へ旅立った旅行記である。横浜-東京-日光-新潟-米沢-山形-新庄-横手-久保田(秋田)-青森-函館-室蘭-白老・平取(アイヌ部落)まで足を伸ばし帰路につくが、六月十日から九月十七日までの三か月の大旅行である。明治十三年は、西南の役で西郷隆盛が自刃してから僅か一年後であり、当時の世情を考えると、「よくぞまあ、ご無事で」が率直な感想である。 |
| 旅人に対しては寛大な民族であることは、室町末期に来日した宣教師も記しており、古代の朝鮮からの渡来者に対して同様であるが、このことは日本人として大いに誇りにしてよいのではないか。 |
| 平成十年三月春分の日に日光を妻と訪れた。日光市街から少し山手にある「日光田母沢御用邸記念公園」に立ち寄り、案内を請うて明治三十二年(一八九九)造営の建物を見学する。一時期、大正天皇が長期に利用されたので宮内庁の事務所も併設されており、広さは四、五〇〇㎡、部屋数は一〇六室ある。謁見室、展望室、御寝室、御座所、神器「草薙剣」奉置の間や、現天皇の小学生時代疎開中の書斎や、悪戯された庭園をゆっくり時間をかけて見学した。 |
| 美智子皇后や御子達と那須御用邸にお出かけの折りに、時に旧日光田母沢御用邸にお立ち寄りの節は、時間超過は毎度のことで、腕白時代を懐かしみ、皇后や御子達にも当時の気分をお伝えの御様子とのことであった。誰しも少年時代は懐かしいものだし、夢が一杯にあった。天皇陛下も同様であろう。 同世代を生きた者として、親しみを感じたひとときでもあった。 |
| 差し障りがあるので説明していただいた御方の名前は割愛するが、大正天皇の寵愛を競った女官たちの夜の秘事や、皇后お出まし時の鈴の音の先触れなど、平民には想像もしがたい宮中の生活は、昭和天皇とともに消え去ったと信じたい。数年後に、公園として整備の上、大幅に一般公開されるとのことであった。 |
| 日光関所跡を通って、明治初年に建てられた金谷本家を訪れる。雨戸は締め切ったいたのだが、明かりが見えたので恐る恐る案内を乞うた。上品な御年配の婦人が門口に出られたので挨拶をし、建物内の見学を申し出た。気持ち良く了承していただき、二十枚以上ある雨戸を改めて開けていただいた。ヘボン博士が、イサベラ・バードが、そして数多くの欧米人が日光を訪れ宿泊した金谷本家(日光金谷ホテルの発祥の地)に入る。自宅を継ぎ足し継ぎ足した建物であるが、却って一室一室の雰囲気は違っており、効果を出している。山側の庭には清冽な谷川を取り込み、狭いながらも日本庭園の雰囲気を醸しだしている。 |
| 天井は低く、一六五糎の自分でも窮屈だから、明治時代とはいえ、来訪外国人客は腰をを屈めて部屋を移動したかと思うと滑稽である。料理室から二階の居室に料理を運ぶ中二階の踊り場の活用は、日本の木造建築ならではの知恵の一端を垣間見せて呉れる。 ヘボン博士はじめ多くの外国人から、本格的なホテルの建設の要望があったのは、この一面からみても至極当然のように思える。 |
| この夜、日光金谷ホテルには外国人の宿泊客も多く、ヘボン博士のような教養を感じさせる紳士や、シックに装った淑女を散見した。在日の外交官家族であろうか。資料室で、箱根富士屋ホテルの再建の使命を帯び、金谷家から養子に入った金谷正造氏の経緯を知り、今は小佐野財閥の国際興業系列に入った、あの箱根宮の下富士屋ホテルのことが気になりだした。 |
|
| 2) 箱根宮の下富士屋ホテル |
| 明治十一年創業の箱根宮の下富士屋ホテルには、昨年(平成九年)暮れに訪れ、もっとも由緒ある花御殿(本館)の「南天の間」で一泊した。天井も壁もテーブルも部屋の木製の鍵も、装飾は南天で統一されている。南天は漢方では咳止めの薬効があるから、冬向きの部屋だなと妻に笑いながら語りかけた。前日は河口湖、山中湖から富士山を眺めて強羅で泊まり、当日は箱根小湧園と彫刻の森美術館に立ち寄り、翌日はホテルから浅間山(二六三〇フィート)に登るという強行軍であった。 |
| 富士屋ホテルの資料室で山口(旧姓金谷)正造氏のことを調べたかったが、説明は必ずしも充分とは言いがたかった。気にかかっていたのだが、六月下旬に港区三田図書館で、慶応義塾大学出身の山口由美さん(トラベルジャーナル勤務)の「箱根富士屋ホテル物語」を書架から発見する。著者は、富士屋ホテル経営者の末裔であり、親族者として血族の葛藤を生々しく描いている。 |
| 初代 山口仙之助、二代 正造(仙之助長女の婿、妻と離別後、婿養子なるも妻が家を出て当人は社長として残留)、三代 堅吉(次女の婿養子)と続くが、親族間の不信と憎悪が相続時に爆発し、山口一族所有の株式の過半が、最終的には国際興業の小佐野賢治社長の手に落ちる。資本主義の論理は非情であり、井戸を掘った山口一族は遂に箱根山から下りることになった。 |
| 著者はジャーナリストであるが故に、身内の恥を公表できたと思うが、それにしても凄まじい人間葛藤である。金谷家から婿養子に入った正造は、ホテルマンとしては革新的な時代に先駆けた経営者であったのは事実であるが、婿養子が妻と離別することで悲劇の種が播かれ、山口家との血縁間の溝が深まり、修復は不可能となったのであろう。それにしても、日光金谷ホテル(金谷家)と箱根富士屋ホテル(山口家)の因縁は、日本のホテル業の創業期の大きなドラマである。 |
|
| 3) 上高地帝国ホテル |
| 昨年は六月、ホテルのロビーの暖炉が赤々の燃えていた時期だったので、今年は紅葉の九月の予約だった。九月に入っても地震が続いており、阪神大震災罹災者だけに地震の後遺症が消えておらず断念する。カネボウ薬品に勤務当時、帝国ホテルが一〇〇周年の記念事業として関西進出を打ち出したが、カネボウ薬品大阪支店の敷地が帝国ホテル大阪の建設予定地と抵触した。大所高所からの経営判断で土地交換に応じた経緯もあり、インペリアクラブのメンバーとして、竣工後、帝国ホテルを懇親会や宿泊で大いに利用させてもらった。帝国ホテルの会長は国際興業の小佐野社長であり、箱根富士屋ホテルとは「縁戚」であるのも不思議な御縁といえよう。 |
|
| 4) 軽井沢万平ホテル |
| 軽井沢には、一昨年(一九九七)十月四日、東京に転居した翌週に出掛け、黄葉と白樺が関西育ちには魅力的であった。偶然、軽井沢駅で、別荘の落ち葉焚きに来ていた武藤量太君(武藤山治令孫)に出会ったのは双方にとって驚きであった。 |
| 今春は、中軽井沢にある鐘紡の健康保険組合の保養所に宿泊してサイクリングに汗を流す。星野温泉-野鳥の森-軽井沢タリアセン(ペイネ美術館、深沢紅子野の花美術館、軽井沢高原文庫)。翌日は追分(堀辰雄記念館、追分郷土館)-旧軽井沢(矢ケ崎公園、別荘地帯、旧軽銀座)。昼食は軽井沢万平ホテル。 |
| ところで、調査していないのだが、軽井沢万平ホテルはどの大資本の系列か? もしかしたら----------------? |
|
| 5) 尾瀬長蔵小屋 |
| 昨年(一九九七)六月に、二泊二日(一泊は深夜バス利用)で尾瀬に出掛け、大清水から尾瀬沼一周と鳩待峠から尾瀬ケ原(山の鼻-龍宮-ヨッピ吊橋)を回った。東京での妻との最後の思い出旅行は、九月に入って尾瀬(長蔵小屋・東電小屋)に決定した。出発までに余裕があったので、何冊かの書籍に目を通し、昨年とは違った行程を計画した。更に、自分なりの関心をある程度満たしてみたかった。 |
| 1) 会津側から入って、沼山峠から尾瀬沼東岸の三平下まで歩き、前年の三平下から 大清水と結んで、江戸時代の尾瀬内の会津・沼山街道を完成させる。 |
| 2) 平野長蔵翁の実像に迫ってみる。虚像としての長蔵翁の紹介が多すぎる。 |
| 3) 平野家三代と尾瀬の自然保護運動 |
|
| 併せて、平野長蔵翁がふるさと檜枝岐村を捨て尾瀬沼に墓所を造らざるをえなかった背景や、自然保護運動家にとっては歴史的には敵である東京電力の立場から尾瀬の自然保護への協力を、現地で感じてみたかった。学生時代に歴史を少しは齧った者としては、イデオロギー的著作物には生理的に反発したくなるし、勧善懲悪的な英雄と悪魔の葛藤にはどうしても眉唾ものの内容を直観的に感じることになる。 とは申せ、今日の尾瀬の自然保護運動を否定したり、軽視しているのではない、為念。二泊三日は、妻と一緒でもあり、無理のない、雨でも予定変更しないで散策できるコースを立案した。 |
| 第一日 |
会津高原-檜枝岐村-沼山峠-大江湿原-ヤナギランの丘-尾瀬沼東岸(三平下)-南岸中間-ビジターセンター-長蔵小屋(宿泊) |
| 第二日 |
大江湿原-浅湖湿原-沼尻-白砂湿原-下田代-赤田代-三条の滝・平滑の滝-赤田代-東電小屋(宿泊) |
| 第三日 |
ヨシッポリ田代-中田代-龍宮-上田代-山の鼻-ビジターセンター-尾瀬植物研究見本園-鳩待峠-沼田尾瀬植物研究見本園-鳩待峠-沼田 |
|
|
| ヤナギランの丘に立って平野家三代の墓に詣でた。墓は尾瀬沼を、そして長蔵小屋を優しく見守っている。尾瀬沼の主は平野長蔵その人であり、檜枝岐村の有力者や発電会社の無理解と権力に歯向かってきた男の生きざまが墓標に凝縮しているようだ。平野家の墓所から尾瀬沼を眺めていて、個人的な感慨にふけっていた。 |
|
|
| 実は、私の家の来歴は、戦国時代の伊予の豪族河野家史書から登場し、徳川時代は道後一帯の大庄屋として、明治維新は旧里正とし無事に迎えることになる。墓所は道後姫塚の義安寺にあるが、一基だけは墓所から離れた義安寺境内の山の中腹にあり、松山城(松平氏)と持田村(現在は町)を向いて立っている。私から数えて七代前に当たる三好平兵衛(諡号等陳)は、天明四甲辰年四月墓石の立っているこの場所で自決している。天明の飢饉で松山藩も御多分の漏れず大凶作であり、持田村の年貢が払えず責任を取らされたか、村人に不穏な空気があった咎を糾弾されたのかもしれない。 |
| 家書に記載がないので、等陳の墓を松山城と持田村を向いて立てたのは、無念(反抗)の気持ちなのか、豊作を祈念し村を護るという気持ちなのか、今まで自分自身曖昧な気持ちであったが、平野長蔵翁の墓前に立って後者であることをはっきりと直感できた。この悲劇的な自決により家名存続が許されて、同じ温泉郡の庄屋から婿養子を迎えることができた。 |
|
|
| しかし何故平野長蔵翁の墓が墳墓の地から遠く離れているのだろうか。疑問はそこから始まった。 |
| ふるさと檜枝岐村は、かつては冬季には雪に閉ざされ、会津でももっとも辺境の地であり、最奥地でもあった。昭和四十五年には、面積 三九一平方粁、人口 九八三人、人口密度 二・五人/平方粁、耕地 五反、九割以上が森林で国有地であり、観光資源を除けば典型的な過疎の村である。平成七年度の人口は六四四名で、急速な激減化・高齢化の波に襲われている。 |
|
| 更に、星姓 六十三戸、平野姓 六十二戸、橘姓 十七戸、その他 八戸で、歴代村長をみても、初代~四代 星姓、五代 橘姓、六代星姓で、星姓は、江戸時代以降村を取り仕切ってきた歴史を、今日も色濃く残している。初代村長 星愛三郎氏の実家は、名主で関守の家系であり、祖父善作氏は明治六年の新制度下では戸長(村長)であった。参考までに記述すると、村の旅館六軒中、星姓五軒、橘姓一軒である。また尾瀬の山小屋では、星姓四軒(尾瀬・原ノ・温泉・渋沢温泉)、平野姓三軒(長蔵・第二長蔵・燧)で、橘姓のオーナーはいない。更に、星・橘・平野姓とも、旧家の伝承では西日本が「原籍」である。 |
| 星姓は、和歌山件西牟婁郡白浜町(星の里)、橘姓は三重県員弁郡北勢町を発祥としており、熊野三社系ともいわれており、山岳宗教(山伏)との関連があるのかもしれない。 一方、平野姓は京都(八瀬)発祥といわれるが、苗字が一般的であり、村の人口では星姓に匹敵するも、村の運営は星姓を中心に橘姓が保管するのは何故なのだろうか。 |
|
| 星姓と橘姓は固まった部落構成であるが、平野姓は檜枝岐川を向かい合って部落を構成している。平野姓は、星姓と橘姓に比して新しい部落なのか、血族結婚を避ける村の掟なのか、興味はあるが、軽はずみなことは口に出来ない。 |
| 星姓が経済的にも宗教的にも村を支配していた当時、平野長蔵なる青年が燧ケ岳に祠を立てて新たな宗教(明治二十一年 燧岳教会)を起こし、かつては会津(沼田)街道の要所であった尾瀬沼の漁業権他権利一切を、代議士であり司法大臣であった横田千之助と組んで檜枝岐村から委譲を受けて養漁を起こすことになった。極端に貧しいが、秩序があった山村に、革新的かつ無法図な青年の破壊的な行動に対して、村の有力者や村人がどの様な反応を示したのか、現代に置き換えても分かるような気がする。 |
| 豊かな水源を持つ尾瀬の山岳地帯の開発にあたって、東京を中心とする関東圏の人口増加と軍備拡張と鉱工業の発展で電力事情の逼迫が予想される中で、貧しい山村に多額の保証金を提示されたとすれば、村として同意することがそれほど社会悪だったのだろうか。敢然と立ち向かった平野長蔵青年に、村の対応は「村八分」(村からの排除)しかなかったのではないか。村(共同体)を護ることが、人権を護ることより重要だとする迫害を、現代の我々は、マスコミの論調同様に責めることができるのだろうか。南の開発途上国の「自然破壊」を北の先進国は批判しているが、先進国は自然破壊によって文明を築いてきたことを語ろうとしない。首都圏の半分を元の武蔵野に戻すことの方がはるかに容易であろう。 |
|
| 東京電力の子会社である尾瀬林業の自然保護への活動は、もっと評価されてよい。尾瀬周辺の山岳の過半が東京電力の所有であることが、尾瀬の荒廃を救ったことを更に評価すべきであろう。もし個人の民有地であったとしたら、企業の無制限な開発や、農地解放後の小作農の自立化には大いに役立ったが、安易な脱農業による農村の疲弊を見るときに、公益企業の持つ歴史観と識見と経済的支援を無視してよいものだろうか。幸いなことに、福島県檜枝岐村も群馬県戸倉村も、尾瀬を「観光資源」として評価し、実質的に経済的なメリットを得ているので、目下「自然保護活動」対「車道・電力利用」は小康状態にあると思うが、より多くの経済的メリットを県・村・住民・電力会社は要望しているのは事実だろう。 |
| 長蔵小屋は、尾瀬にとって、明治から今日まで、そして二十一世紀にも象徴的な存在であり、「記号」であろう。昭和九年に竣工した現「長蔵小屋」が、生活排水をゼロにした山小屋に改修された時に、尾瀬の「自然保護活動」は新しい時代を迎えるのではあるまいか。 |
|
| 檜枝岐村の基礎資料は、「檜枝岐村史」(昭和四十五年刊行)を参考にしました。平野家三代については「尾瀬に生き尾瀬に死す 平野長英尾瀬の歩み」(石村虎三郎著・健友館)と「尾瀬---山小屋三代の記」(後藤充著・岩波新書)ほかです。 |
| 「思い込みのホテル」は、夫婦にとって「想い出のホテル」になっていくのでしょう。 願わくは、日光金谷ホテル・箱根宮の下富士屋ホテル・上高地帝国ホテル・軽井沢万平ホテル・尾瀬長蔵小屋のたたずまいは「日本宿屋遺産」として、今後とも残ってほしいし再度訪れてみたいものである。 |
|
| (追って)関西の「思い込みのホテル」では奈良ホテル、都ホテル(現ウエスチン都ホテル)が印象に残っている。 |