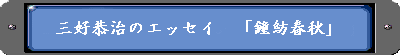| 「日記」は小学校(正確には国民学校であるが)から断続的に書いており、ビジネスマンになってからは「業務日誌」となったが、鐘紡の人事部人事課長の任命を受けて以来今日まで「博文館日記」で書き綴っている。約40年分である。鐘紡の人事施策の背景、経営最高幹部との軋轢、社員との交流を「人事の目」で執筆しているので原文のままで発表することは許されまいと自覚している。 |
| そこで64歳の役員定年を前にして、平成九年から「ひと・出会い・旅」なる「自分誌」を毎年発行して親しい仲間に読んでもらった。もっとも熱心な読者であった萱森敬一君が一昨年逝去したこともあり、年刊誌の発行は中止した。萱森君は慶応経済学部C組のクラスメイトであり、欧州経済史特にハンザ同盟の権威者であった高村象平教授の共通のゼミ生であり、鐘紡入社志願書に松澤泉君と彼の名前を親友として記載した学友であった。 |
| 読者でもあった昔の部下達から、今年(平成19年)明治以降日本の代表的企業として君臨した鐘紡(カネボウ)が実質的に消滅することでもあり、鐘紡(カネボウ)の雰囲気を伝えるエッセイをインターネットホームページに掲載して欲しいとの要望もあり、思い切って「三好恭治のエッセイ『ひと・出会い・旅』」を立ち上げることにした。 |
| 「鐘紡(カネボウ)の社史社風」「鐘紡技術学校修了生へのメッセージ集」「社内教育体系」「人事考課体系」「女子寄宿舎管理マニュアル」「見習生(鐘紡幹部社員)採用、教育、配置方針」「企業内同和推進方策」など自らが立案実行した人事施策を中心に記述するつもりである。但し人名についてはプライバシーがあり省略するが、役職名は表示する。 |
| 執筆に時間を要するので、助走として既刊の「ひと・出会い・旅」誌から数編を抜粋して掲載します。感想などお寄せ頂ければ幸甚です。 |
|
|
|
|
|
| 平成九年版「ひと・出会い・旅」を、恙なく纏めることができた。 |
| 三十数年に及ぶ会社生活の中で、その多くはビジネス上のつきあいであるが、オフビジネスの一年間の記録をぜひ残したいと思い、ワープロ執筆してきた。「みよぶたくんへの手紙(手術で入院した次男への家族の励まし記録)」「折々の句」「学生の時代 就職・卒論・友情」「婚約時代」「阪神大震災私記」「浩一抄 その光と翳と(未完)」 「道後三好家来歴」と一冊また一冊と私家本が増えて来て、本箱の一隅を占めるようになった。毎年の記録は「三行日記」として取り纏め、十年毎に「不惑の時代」「天命の時代」とし、還暦以後も「耳順の時代」「不踰矩の時代」−−−−−と気力がある限り書き留ていきたい。 |
| そのなかで、会社生活の殆どを人事関係中心に過ごしてきたし、人との出会いを「一期一会」として大切にしてきたので、自分にとっての人生の糧となった「自分以外皆師也」の思いを、毎年「人・出会い・旅」に書き留めた。ビジネス関係の「人・出会い・旅」はオフビジネスよりは遙かに多いが、ご迷惑をお掛けすることがあってはと危惧し、「人事課長の時代」 「人事部長の時代」 「工場長の時代」などは、個人的なノートに書いたままで、ひっそりと眠らしておきたい。 |
| 平成九年版「人・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しております。 同時に、この一年間「夫唱婦随」で、我が儘に付き合ってくれた妻にこころからの感謝を捧げ、ともに健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十年三月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十年版「ひと・出会い・旅」を、恙なく纏めることができた。 |
| 平成十年は、私にとっても家内にとっても人生の転換点の年であった。六月末にカネボウ薬品株式会社を退任し、昭和三十三年鐘ケ淵紡績株式会社入社以来四十年に及ぶ鐘紡での生活に終止符を打った。秋十月には、早々と父祖伝来の地である伊予松山の陋屋に帰郷し「古里の人」としての生活を始めた。東京や大阪での退職後の新しい職場に関して暖かい御支援をしていただいた方も少なくはなかったが、学生時代・家住(社住)時代から林棲時代・遊行時代への人生の遍歴に当たっては豊かな自然の中で過ごさせていただくことにした。 |
| 会社生活の殆どを人事関係中心に過ごしてきた。人との出会いを「一期一会」として大切にしてきたし、自分にとっての人生の糧となった「自分以外皆師也」の思いを毎年「ひと・出会い・旅」に書き留めきたので、引き続きゆったりした時間のなかで、その思い形に、形を文字(冊子)に纏めていきたいと考えています。日本的組織人事管理については、幸い松山大学の経営組織論の講座で講義する機会に恵まれましたので、数年後には長年追い求めてきた「仲間社会(ゲノッセンシャフト)論」と「5シップス理論」を中心に体系化を模索してみようと考えております。 |
| 平成十年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しております。 同時に、これまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれた妻に心からの感謝を捧げ、末永く健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十一年三月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十一年版「ひと・出会い・旅」を、恙なく纏めることができた。 |
| 平成十一年は私にとっても家内にとっても故郷道後の実家での生活の初年度に当たり、まさに戸惑いながらの一年でもあった。「故郷デビュー」にはそれほど気は使わなかったが、平成十年年末の家の改築から「古里人」の取り組みを開始した。黄金週間直前に土間を改造した待望のリビングルームが完成し、生活のリズムも漸次落ち着いてきた。 |
| カントリーライフをエンジョイしようと「ガーデニング・アフターヌーンティ・リーディング」を夢みたが、ガーデニングの初年度は畑づくりが中心であった。それでも息子たちに取り立ての野菜を送ることができたので成功といえよう。アフターヌーンティへの切替えは順調に行かず相変わらずのコーヒー党である。茶器や茶道具が納戸にぎっしり格納してあるので茶道をやろうかと思ってはみるが決心がつかない。リーディングは苦にはならないが経営関連よりは郷土史中心の調査研究が中心となった。 |
| 幸い伊予史談会、子規会、一遍会、坊ちゃん会という歴史あるサークルの会員になっており、月一回の例会にも積極的に参加しており大分勘どころが分かりかけて来た。畏友梅木賢正君との月例会で郷土史の基礎を学んできた。平成十一年は月三回の「ふるさと通信」と月一回の「熟田津今昔」を発信してきたが、平成十二年からは待望の郷土史レポート「来歴」(個人誌)を季刊で発信予定である。古希には「江戸期道後村研究レポート」が纏まればと夢見ている次第である。 |
| 会社関係では「日本的経営が輝いた日々(仮題) 鐘紡人事部私史」を取り纏め中であるが、あまりに生々しい経営に於ける人間的葛藤の記述を割愛する訳にもいかず恐らく原稿段階でお蔵入りかと懸念している。 |
| 平成十一年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しております。 同時に、これまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれた妻に心からの感謝を捧げ末永く健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十二年三月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十二年版「ひと・出会い・旅」をお蔭様で纏めることができました。 |
| 本年は私にとっても妻にとっても、やっと故郷道後での生活に足がついた一年でもありました。平成十一年春に土間を改装したリビングルームが完成したことから生活のリズムも漸次落ち着いてきたし、離れの間も主人を得て書斎らしくなってきたと思う。私の周辺での仕事は量質ともに増えてきた。元々「仕事人間」であったから苦にはならないが、退役後の「毎日が日曜日」の生活には程遠い環境になった。 |
| 伝統のある一遍会は二十数年に亘り代表副会長を勤めてこられた浦屋薫先生が顧問に退かれたので幹事として内務を総括することになり、松山東高校の同期会では年度幹事として最低三年間はお世話することとなった。又知らぬ内に道後町一〜二丁目町内会の世話人に推挙され秋祭りなど伝統行事の担い手の一人となった。伊予史談会、子規会、坊ちゃん会、古文書研究会という歴史あるサークルの会員になって月一回の例会にも積極的に参加しており、妻を呆れさせている今日この頃である。一方松山三田会の代表幹事や愛媛山岳会の月一回の山歩きは一休みの状態にある。 |
| 平成十年十月から月三回の「ふるさと通信」と月一回の「熟田津今昔」(平成十二年度末二十七号)を発信してきたが、本年は郷土史レポート「来歴」(個人誌)を月刊で発行し「三号雑誌」にならず十二号迄来た。身の丈以上の精力を使っているのは事実だが、道後郷三好氏の来歴と道後村の伝承並びに歴史の取り纏めができればと夢見ている。慶応時代に高村象平教授の西洋経済史のゼミで共に学んだ畏友萱森敬一君からの毎月一回の読後感の端書きが挫けそうな私の心を支えて呉れている。有難いことである。 |
| 会社関係では「日本的経営が輝いた日々(仮題) 鐘紡人事部私史」を執筆する予定であったが決断がつかないまま一年が経過した。二十一世紀入りした平成十三年一月一日付で鐘紡の商号が消滅しカネボウに変わることとなったのを機に、新年度から執筆を開始し本年末には草稿を完了させたい。 |
| 平成十二年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しています。 同時に、これまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれた妻に心からの感謝を捧げ末永く健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十三年二月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十三年版「ひと・出会い・旅」をお蔭様で纏めることができました。 |
| かつての友人に会うと「お暇でしょう」と云われ、松山の友人に会うと「忙しそうで中々会えないね」と云われる。どちらも本当であり、どちらも真実を伝えてはいない。平成十三年度の生活リズムを此処に記載しておくことにするが、平成十四年以降もこのライフスタイルかと尋ねられたら、そうだと云う自信は全くないのだが・・・・ |
| わが家では四月から十一月までがサマータイムであり、標準時間に比べて一時間繰り上がっている。日照時間に合わせた太陰太隈層の生活リズムでもある。起床後、神前拍手、仏前お勤め(般若心経、過去帳、十念仏)、作務(玄関拭掃除)、NHK
朝ドラ、コンビニ(日経購入、週刊誌立ち涜み)と続く。約二〇〇〇歩である。午前中の三時間は書斎で過ごす。E
メール・朝日新聞他インターネット閲覧後、郷土史関連研究&執筆(1)熱田津今昔(月刊(2)来歴(月刊)(3)古里通信(旬刊)(4)一遍関(5)子規関連であり、一遍と子競については、年各二本程度の小論を予定しており、子規会、一遍会や市民サークルの依頼があれば講演することになる。最近は日本的経営についての講演依頼は全く無い。現在の経済状況tpカネボウの現状をみれば当然のことと帝めている。 |
| 午後は三時間程度の作務。外回りの仕事になるが八〇〇坪弱の敷地だけに年中仕事が絶えることはない。春から夏にかけては畑づくりとッ草刈り、夏は草刈りと散水、秋から冬にかけては庭木の剪定と落ち葉掃除と続く。雨期の屋根と雨樋の点検修理は危険を伴うが、梅、柿、撞などの収穫は楽しい。一月と二月が暇と云えば暇だが、この「ひと・出会い・旅」を含めて執筆した作品の取り纏めに精を出している。約五〇〇〇歩である。 |
| 夏は自宅の温水機利用の入浴だが、春・秋・冬は遣後温泉に出掛ける。竹籠をさげての風流人となり俳句をつくっている。ぶらぶら歩きの一〇〇〇歩である。夜は午後九時位までがTV時間。その後は書斎での読書、インターネット、返信、日記執筆で十二時前後に就寝する。概ね一日七乃至八〇〇〇歩であり、週平均では一日一万歩になる様挑戦中。土曜、日曜は伊予史淡会、子規会、一遍会、古文書研究会、大学・高校月例会、友人との月例会、県山岳連盟山歩き月例会や美術展、コンサートなど各種催し物に精力的に出掛けているので家を留守にすることが多い。と云う次第で「忙中閑・閑中忙」、「毎日がウークデイ」なる生活であり、その一端をこの冊子に記録した次第である。 |
| 平成十三年版「ひと・〜出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しています。同時に、これまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれている妻に心からの感謝を捧げ、ともに末永く健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十四年二月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十四年度版「ひと・出会い・旅」を今年もお蔭様で取り纏めることができました。 |
| この小冊子も第六号となり「よく書くことがありますね」と家人から言われるのだが、これも毎日の積み重ねを一文に纏めるだけだから本人はあまり苦にしてはいない。むしろ昨今はインターネットの方に時間を取られている。一昨年末に富士通のパソコンを購入し、昨年にはホームページ(以下HPと略す)「一遍会」を立ち上げ「一遍徒然草紙」を定期的に掲載し、全国の一遍研究者や一遍フアンからのお便りをいただくようになった。又、高校同期会HP「東の窓」を企画し現在四十数名の仲間と日夜交信している。事務局を担当している「愛媛のピエロ」こと三橋英明兄の卓越したセンスとテクニックで日本一の同期会HPであろうと自負している次第である。併せて鐘紡三十三年入社組の集まりである「燦燦会」でもメールリンクして近況を連絡しあっている。 |
| その様な訳で五年目のマンネリにも陥らず「ひと・出会い・旅」は相変わらず日常的に賑々しく続いている。インターネットを楽しんでおられる方は、例えば「ヤフー」で「一遍会」や「東の窓」か一寸気恥ずかしいが「三好恭治」で検索していただくと「道後関所こと三好恭治」のHPが登場することになっています。 |
| 年末になると鐘紡(カネボウ)の先輩の方々の訃報のメッセージが纏まって届き気が滅入ってしまう。地元でもお世話している一遍会の代表である越智通敏先生を失い、また現在高校同期会の会長をしているのだが片腕に当たる副会長の井手大兄が涅槃に旅立つなど心寂しい一年であった。数少なくなった父母の兄弟姉妹たちや身内の葬儀には極力不義理を重ねないように努めてはいるが、その都度経済的にも時間的にも松山から東京・大阪は遠いなあと実感するようにもなった。 |
| 平成十四年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しています。同時にこれまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれている家人に心からの感謝を捧げともに末長く健康な人生を歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十五年二月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十五年度版「ひと・出会い・旅」を今年もお蔭様で取り纏めることができました。 |
| この小冊子も第七号となり「よく書くことがありますね」と家人から言われるのだが、日々の積み重ねを一文に纏めるだけだから本人はあまり苦にしてはいない。むしろ昨今はインターネットの方に時間を取られている。昨年ホームページ(以下HPと略す)「一遍会」を立ち上げ「一遍徒然草紙」「熟田津今昔」などを定期的に掲載し、一遍研究者や一遍フアンからお便りをいただくようになり、HPのカウンターも三六〇〇台を越えてやっと一人前になった。その様な訳で定年後六年目のマンネリにも陥らず、私自身の「ひと・出会い・旅」は相変わらず日常的に賑々しく続いている。 |
| 一遍会、松山子規会、伊予史談会、坊っちゃん会、松山三田会、高校同窓会&同期会などに精勤中ですが、平成十六年度からは道後今市上町内会のお世話も担当することになった。隣組が活発化した昭和十四、五年頃から昭和二十年の敗戦以降も父親が町内会長を務めていたので親子二代ということになる。これも地元との縁(ひと・出会い)であろうし精一杯勤め上げたいと思っている。 |
| 平成十三年度に続いて「小林小太郎」の小論などを記載しました。拙論は「子規会誌一〇〇号記念号」に掲載され、今秋には伊予史談会で「小林小太郎〜伊予松山藩の福沢門下生たち」と題して発表することが決定している。併せて「一遍と神々の出会い〜夢託ということ」も「一遍と神々の出会い」シリーズとして一遍会例会で発表している講演の抜粋である。「夢託ということ」「医聖・湯聖ということ」「女性(にょしょう)ということ」が既に纏まってはいる。ささやかな研究は上記のほかに郷土史にも首を突っ込んでいるが、道後三好家の伝承のひとつ「奥道後大蛇物語」が学研「ムー」誌の平成十六年四月号に掲載される予定である。ご笑覧頂ければ幸甚である。 |
| 平成十五年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しています。同時にこれまで通り「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれている家人に心からの感謝を捧げるとともに末長く健康な人生を二人して歩んでいきたいと改めて誓う次第である。 |
| 平成十六年二月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成十六年度版「ひと・出会い・旅」を今年もお蔭様で取り纏めることができました。 |
| この小冊子も第八号となったが、纏める苦労よりは毎年お送りして読んでいただける知友がいることへの感謝の気持ちが年一年と高まってくる。平成十六年前半は伊予史談会十一月例会で「小林小太郎」について発表することが決まっており、その準備に追われた。平成二〇年に慶応義塾は創立一五〇周年を迎えるが文久三年起『慶応義塾入社帳』筆頭に記載されている「伊予松山藩士 小林小太郎」の出自は今日まで全く不明であった。四年間こつこつと史料に当たりやっと実父である駿河田中藩士小林小四郎の所在を突き止める事が出来た。本年夏には論文が「伊予史談」誌に掲載され慶応義塾並びに福沢研究センターに報告されることになっている。今後「小林小太郎」の研究に当たっては本論文抜きには考られないと自負している。論文の一端を今回第一章に掲載した。 |
| 後半は松山東高校卒業五十周年記念行事があり同期会の会長としての義務と責任を果たすべく全力投球した。お陰で同期三三一名中一一三名が参加し盛大に開催することができ参加者にも満足してもらった。記念総会での挨拶と高校以来出会うことがなかった親友宛の手紙を卒業五十周年の記憶を風化させない為にあえて掲載した。 |
| 手抜きができない行事が重なったので毎年実行している年二回の海外旅行を断念して平成十六年は一月は長崎・博多、三月は讃岐、四月は津軽、七月は北海道、九月は信州、十一月は小豆島と隔月に国内旅行を楽しんだ。紀行文を本年度版にも多数掲載した。 |
| 平成十六年版「ひと・出会い・旅」をお手渡しできる縁に心から合掌しています。同時にこれまで以上に「夫唱婦随」で我が儘に付き合ってくれている家人に心からの感謝を捧げるとともに、いよいよ古希を迎え「黄金の七十年台」を心身共に健康に二人して歩んでいきたいと改めて誓う次第である。今後とも宜しくお願い申し上げます。 |
| 平成十七年二月吉日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、はじめに |
|
| 鐘紡株式会社(現カネボウ)で二十数年人事部に在籍し七年余にわたって人事部長の任に当たった。毎年の主要業務で且つもっとも楽しかった仕事に大学卒対象の採用時の人事面接があった。人事課長当時は四、五〇〇人以上、人事部長になってからも二〇〇人以上の学生と一時間に五人宛面談を繰り返していった。 |
| 面接に当たっていろいろと職業観や当社志望事由などを聴取するのだが、全員に決まって質問したのは次の三点であった。 |
| 1) よき友にめぐりあったか。 |
| 2) よき書物にめぐりあったか。 |
| 3) よき師にめぐりあったか。 |
|
| 現在では考えられないことだが当時は学生運動や国籍でリストに挙がった学生の採用は大手企業ではタブーであった。人事部長としての「琴線」に触れた就職志望者につき社長を説得して採用を決定した経緯もある。名前を明かすことは絶対にしないが、現在経営陣で活躍しているその当時の学生の姿を見ると人事部長冥利に尽きるという感慨を持つ。 |
| ところでこの三つの質問は私の独創ではなく、慶応義塾大学経済学部の学生としてゼミの指導教官である高村象平教授(以下高村先生)とのお付き合いの中で刷り込まれたものである。ゼミ終了後の雑談で身近かに高村先生の謦咳に接し、印象に刻んだ言葉は忘れないように下宿先に持ち帰り日誌に書き留めていったのだが、そのフレイズの一節が上記の面接の要項である。実はゼミ参加に当たっての先生からの質問も同様であった。今でもハッキリとその時の受け答えを覚えている。 |
|
| 1)よき友については、昭和二十年の敗戦当時同じクラスの友人一〇名で「蛍雪会」なるグループを結成し、九月進駐軍が松山に赴任する前日には松山城と対面する御幸寺山に登り「敵は幾万ありとても」とか「海ゆかば」を涙して歌い、明日以降進駐軍に殺されても友情を持ち続けようと誓い合った餓鬼仲間のことを語った。現在も八名が健在であり、そのうち何名かとは毎年の様に会っている。 |
| 2)よき書物については大塚久雄東京大学教授の「欧州近代経済史序説」とゲーテの「ファウスト」とエンゲルスの「家族・私有財産・国家の起源」を列挙した。 |
| 先生はにやっと笑って「歴史を学ぶものは原典に当たらねば書籍を読んだことにはならない」との一言痛烈なコメントが帰ってきた。そんな訳で卒論は日本語文献は殆ど利用しないで「十六世紀イギリス農村の一考察」と題して教会の遺産目録から当時の農村事情を四百字詰百五十枚に取り纏めたが正直云って難渋した。 |
| 3)よき師については、小学校(二神日満男先生)、中学校(桑原良之先生)、高等学校(渡部勝己先生)の恩師のお名前をあげ、大学ではまだ居ませんと答えた。 |
|
| 学問の世界から高村象平教授の先生像を描くのは不可能なので、大学時代の二年間に先生に接した印象から「私だけの高村象平先生」を描いていくことにする。 |
|
|
| 二、高村象平先生のプロフィール |
|
| 1)先生にとっての「よき友」 |
| 江戸っ子特有のべらんめいで辛辣な批評をする先生は、初対面から東京は下町の生まれと直観した。東京本所小梅瓦町(現・墨田区小梅一丁目)で育ち、明治四十三年(一九一〇)夏の洪水で本郷に移った由だが、いまでこそ本郷だが中央線の通っていない当時の本郷は下町からみれば郊外であったらしい。 |
| 先生は旧制開成中学で学んだが、ここで二人の終生の「よき友」に巡り会っている。その中のひとりは先生の研究室でも度々お会いし御指導頂いた小松芳喬早稲田大学教授である。この二人は開成中学の先輩達から神田のニコライ堂に呼び出され度々鉄拳制裁を受けたらしい。生意気過ぎる少年だったからだろうが、お二人の並んだ姿を拝見していると温厚な小松芳喬先生の方が巻き添えをくらった様に思われてならない。進学では早稲田・慶応に分かれたが、同じ経済史を専攻され、後年早慶の経済学部長から学長(義塾長・総長)まで「不本意ながら」出世されようとはご当人達は夢想もしなかったらしい。 |
| 高村先生は「ドイツ・ハンザの研究」では世界的な学者であるのでドイツ経済史を研究したいとは思ったが、大塚史学に魅せられるところが多かったので「十六世紀の英国農村事情の実証的研究」を選んだ。そこで先生は英国中世経済史の権威である小松先生を私に引き合わせ指導を受ける様にとアドバイスをいただいた。一学生にここまで面倒をみていただいたことは有り難いことであった。 |
|
| 2) 先生にとっての「よき師」 |
| 先生の大学の指導教官は野村兼太郎教授(当時)であった。幸いなことに私の時代には慶応義塾の名物教授である高橋誠一郎名誉教授と野村兼太郎教授が教壇に立っておられたので「経済学史」と「日本経済史」を受講した。小泉信三名誉教授は東宮での皇太子(現・平成天皇)の御指導に当たっておられたので残念ながらお会いしていない。 |
| 野村教授の講義は四回生で受講したが、他の学生とは違いある程度まで専門的な知識があったので講義内容の過半は既知のものであった。むしろテーマの設定や史料分析に当たっての視座に興味を持ったが、ご高齢であっても(と云っても六十七歳の現在の私より十歳近くも若いのであるが)切り口の新鮮さは鋭く毎週の講義が待ち遠しく前列に座って熱心に聴講したものだった。 |
| 高村先生が野村ゼミに入部して「イギリス産業革命期のチムニーボーイの研究」を希望された時、野村教授が一冊の本を挙げて図書館にあるから読みなさいと指示された。先生は早速図書館でその本を貸し出したがなんと索引のない大書であった。最初から最後まで目を通さねばならないことになった。そこで必要に迫られた斜め読みの技術を習得することになった。 |
| ゼミの同輩も同じ経験をしているのだが、先生から図書館にあるからR・H・トーニー著「英国十六世紀の農業問題」なる大著を一週間で読むように指示された。この本はイギリス中世経済史を専攻する学徒にとっては必須の文献と考えるが翻訳本はないし丁寧な索引もない。一週間下宿に籠りっぱなしで読んだがいつの間にか斜め読みをしていた。先生に報告すると、にやりと笑って次の本を書架から取り出して又一週間で読みなさいと手渡して頂いた。正直これほど厳しい愛の鞭を受けたことはなかった。実質一年半で二十数冊の原書に目を通したことになり、これらの原書の抜き書きから卒業論文を執筆することになった。あとで振り返ってみると高村先生が野村教授の薫陶を受けたやり方に酷似していた様だ。R・H・トーニーには他に「宗教と資本主義の興隆」があり今日では岩波文庫で手軽に読めるが昭和三十年当時は原書のみであり随分苦労して「斜め読み」をした思い出がある。 |
|
| 2) 先生にとっての「よき書」 |
| 先生から伺ったことはないし、もし質問したとしてもドイツ語での文献であろうから私にとっては専門外である。ただし先生が愛読した書物は漠然とこの本ではないかと思うのだが・・・・ |
| 三田の通りで酒を飲みながらの雑談の折だったか、ゼミ終了後の懇談の場であったか今となっては記憶は定かではないが、先生が卒論に纏めた「チムニーボーイ」は翻訳すれば「煙突少年」であり、イギリス産業革命初期に都市の貧しい少年が身体ごと煙突を上り煤煙掃除をする少年労働者のことである。開成中学か慶応の予科の時代にディケンズの「オリヴァ・ツイスト」を読んで若者特有の正義感に燃えて塾友と気勢を挙げたらしい。先生と同世代の慶応の大先輩に高村先生のことを訊ねると、きまって「おお、チムニーボーイの高村か」という返事が返ってきたのには驚いた。青春時代は酒と新劇と読書の毎日だったらしい。 |
| もう一冊は先生の研究に関係するのだが、トーマス・マンの「ブッデンブローク家の人びと」でマンの自伝的小説である。後にノーベル文学賞を得た作品でありドイツ・ハンザの盛衰を描いた大河小説である。この物語を語る時の先生は留学時代のリューベックやハンブルブの酒場と演劇を熱っぽく語る演劇青年であった。戦争のない平和でもっと自由な時代であれば新劇の俳優として築地の劇場で小山内薫の指導を受けて羽ばたきたかったのではないかという位のロマンを感じさせるひとときであった。 |
|
|
| 三、学者としての先生 |
| 先生の学問的業績を語る程の知識もないし勇気も持っていない。昭和四十六年(一九七一)新春の宮中での講書の儀で先生が「ドイツ・ハンザの経済史的意義」について御進講された。その後御進講の原稿に目を通すことができたので要旨を少し長くなるが記述しておきたい。 |
|
|
| ドイツ・ハンザの十二世紀から約五百年に及ぶ歴史を簡潔に述べ、都市同盟的制約はなく加盟或いは脱退が自由で経済的利益を追求する団体ないし共同体であったと指摘する。 ドイツ・ハンザ都市間では利害が反するも五世紀にも及ぶ結束を保ったのは決して共同体の規制ではなかった。ハンザ会議という最高の審議機関が随時開催されたが、多数決の議決に統制力はなく軍備も持たなかったが、仲間を統一する体制が必要だとする共同体的思考が分裂を阻止したと考えられる。併せてドイツ皇帝からの援助は一切受けず自由なスタンスを保持したことも大きな要因であった。 |
| ドイツ・ハンザを支えた自由都市リューベックから、イギリスとの結びつきを強めたハンブルグ、ベルリン、ハノーバーが押し上がり政治と結託し巨大な都市として成長する。ドイツ・ハンザの歴史的評価が低いのは、ドイツが自由都市から絶対主義的な領邦諸侯の支配に移行したことによると考えられる。 |
|
|
| 最後に先生は昭和天皇に次の様に纏めを申し上げている。 |
| 「加盟都市はそれぞれが自己の経済的利益を追求しておりますものの、ごくやむを得ない場合のほかは、武力行使にでることなく、都市相互間の紛争も、外国との折衝も、話し合いや仲裁、調停によって解決することに全力を尽くしたことが、五百年間に残した記録からも明らかでございます。この点は、現在におきましも、記憶さるべきことと考えておる次第であります。」 |
|
| 賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶと云われるが、先生は天皇の前でこのことを平常心で訴えられたのであろう。この年に沖縄が返還されアメリカの占領体制がやっと終結し、翌昭和四十七年(一九七二)田中角栄内閣が誕生し日中の国交正常化が実現する。以後三十余年の今日に至るまで歴史を忘れて経験に頼り日本丸の行き先が依然として見えて来ない。先生は未来を予測しドイツ・ハンザの歴史に学べと遺言したのではあるまいか。 |
|
|
| 昭和三十二年の秋、慶応義塾で全国大学ゼミナール大会があった。西洋経済史分野では慶応から高村ゼミが参加し、私が基調報告をした。東京大学が大塚久雄ゼミ、一橋大学が増田四郎ゼミ、早稲田大学が小松芳喬ゼミ、福島大学からは吉岡昭彦ゼミが参加した。当時福島大学は吉岡教授の「寄生地主論」が脚光を浴びており学生の鼻息も荒かった。理論的な大塚ゼミと実証的な高村ゼミの討議は正直なところ噛み合わなかったが「対外試合」でもあり大いに勉強をしたのも今となっては懐かしい。 |
| 増田先生は平成九年(一九九七)八十八歳で逝去されたが、同年九月の「創文」に小松先生の談話が掲載されておるので数行引用する。 |
| 「(増田)四郎君と高村(象平)君と僕(小松芳喬)とでは、どこを捉えても、類似点が多いとは言えないでしょう。それにも拘らず、案外気が合ったことも少なくなかったのです。例えば、もう何年前でしたか、我々はいろいろな所へ行く機会が多いけれども、細君を連れて行ったことが殆どないから、家族会を作って、我々の行くところを細君にも見せてやろうじゃないかと、高村君が言い出しました。提案は異議なく成立して、まず高村君の顔のきく新橋で第一回が開催されましたが、僕も四郎君も、高村君のような粋人ではないので、いざ当番となると、少なくとも場所の選択には頭を悩まされることが珍しくありませんでした。それでも大いに苦心して、何回かやりましたが、言い出した張本人が一〇年近く前に姿を消してしまったのですから。今となっては、楽しかった思い出になってしまいました。」 |
| 大塚先生は足が悪かったし、四人の先生が新橋か祇園で席を持てば座持ち役は恐らく高村先生であったろうし、下ネタ豊富な高村先生が粋筋には持てたに違いないと妙に確信している。先生、この推測が当たっていたらごめんなさい。 |
| 高村象平先生は平成元年(一九八九)、大塚久雄先生は平成八年(一九九六)、小松芳喬先生は平成十二年(二〇〇〇)に相次いで逝去されている。学恩のある四先生のご冥福を心からお祈りする次第である。 |
| ここで高村先生の経歴を簡単に記しておく。 |
|
| 【略歴】 |
|
明治三八年(一九〇五)東京に生まれる。東京開成中学校を経て、昭和四年(一九 二九)慶応義塾大学経済学部卒業。 |
|
その後、同学部助手、助教授、教授として経済史とくにドイツ中世経済史を専攻。 助手時代にドイツへ二ヵ年留学。戦後、経済学部長、図書館長、塾長兼大学長を歴任。経済学博士。 |
|
塾外では、社会経済史学会・大学基準協会の理事、中央教育審議会・大学設置審議 会の委員、私立大学審議会・日本私立大学連盟・全国大学教授連合の会長などを歴任。 |
|
平成元年(一九八九)没。多摩霊園に眠る。 |
|
| 【主要著書】 |
|
|
「近代技術史」 (一九四〇年 慶応出版社) |
|
「日葡交通史」(一九四二年 国際交通文化協会) |
|
「資本主義の歴史的問題」(一九四八年 泉文堂) |
|
「経済史随想」(一九五一年 塙書房) |
|
「アメリカ資本主義発達史」(一九五二年 金星堂) |
|
「ドイツ中世都市」 (一九五九年 一条書店) |
|
「ドイツハンザの研究」(一九五九年 日本評論新社) |
|
「西洋経済史」(新版) (一九七一年 有斐閣) |
|
「私学に生きる」(一九七二年 文化総合出版) |
|
「五年のあしおと」(一九六五年 慶応通信) |
|
「西欧中世都市の研究」(一九八〇年 筑魔書房) |
|
「回想のリューベック」(一九八〇年 筑魔書房) |
|
|
| 追記 |
| 土肥恒之著(一橋大学名誉教授)『西洋史学の先駆者たち』 (2012..6.10発行 中央公論新社 [中公叢書]) |
|
慶応時代の指導教官である高村象平教授から謦咳に接した野村兼太郎教授、(早稲田大)小松芳喬教授の名前がある。卒論は英国中世経済史であったので小松芳喬先生の影響が強い。
更に学恩のある(東大)大塚久夫、高橋幸次郎、松田智雄、(一橋大)上原専録、増田四郎、(関西大)矢口孝次郎、在野の服部之総諸先生の名前を見ると「学生」に戻った自分を発見する。(2012・9・21付 日記より) |
|
| 後日、書架を整理して、「西洋史学」のコーナーを設けた。最右端は大類伸著『西洋史新講』(昭和9年 富山房)である。学生時代の「思い出の書架」となった。 |
|
|
|