競売不動産に係る利回りについて
愛媛県不動産鑑定士協会 大 西 泰 祐
Ⅰ はじめに
競売不動産評価基準を全国的に標準化する流れの中で、収益物件について収益還元法の適用が検討されている。東京、大阪、名古屋の3庁においても、適用物件、適用方法、収益は純収益なのか総収益なのか、還元利回りをどのように設定するか等検討中のようであるが、還元利回りの設定が最も大きな問題であると思われる。
松山市周辺の取引利回りの調査結果については、「取引利回りについて」(「鑑定四国」(2001.12.20No.18))で発表したとおりであるが、今回は、競売不動産に係る利回りについて調査することとした。
Ⅱ 調査方法
松山地方裁判所本庁管内の収益物件の落札利回りを調査するとともに、今回は本庁管内、西条支部管内及び今治支部管内の入札参加者に対してアンケート調査を実施した。
1 落札利回り調査
(1) 抽出事例
松山地方裁判所本庁管内(平成10年7月23日入札分~平成14年5月22日入札分)の落札物件のうち、賃料収入が得られる収益物件
(2) 総収益
評価時点の実際支払賃料を年額で計上し、空室分は計上しない。(空室の多い物件は異常に利回りが低くなるが、生の数値を捉える方がよいと考えた。)敷金等の一時金の運用益は計上しない。駐車場収入等のその他収入は計上する。
(3) 利回り
上記(2)の総収益を落札金額で除した粗利回り(落札利回り)とする。
(純収益に対応する還元利回りは、「還元利回り=0.787×粗利回り」(R2=0.9761相関度)で示されているので、仮に還元利回りが必要な場合は、当該式を用いることによって対応が可能と考えられる。(注1))
2 アンケート調査
(1) アンケート対象者
競売不動産の入札に頻繁に参加している法人、個人業者等のうち、住所等が判明した者(本庁:23、西条支部:9、今治支部:9)(注2)
(2) アンケート内容
アンケート調査用紙
| 競売不動産のうち賃貸マンション、事務所、店舗等の収益物件についてお尋ねします。 問1 収益物件に投資(入札)する場合に検討する項目 (優先する項目を3つまで○をつけてください) ①物件の立地条件 ②物件の建築後経過年数 ③物件の維持管理の状態 ④物件の規模(延床面積) ⑤現在の賃料収入 ⑥将来の賃料収入予測 ⑦現在の入居率(空室率) ⑧入居者(テナント)の属性 ⑨その他( ) 問2 物件の種類に応じた投資利回りはどの程度を目安としていますか。 (この場合の利回りは、現在の賃料収入年額を投資額で割った粗利回りとします)(共益費は含まず、駐車場収入は含みます) (1) ファミリータイプ賃貸マンション ①~8%②8%~9%③9%~10%④10%~11%⑤11%~12%⑥12%~13%⑦13%~14%⑧14%~15%⑨15%~16%⑩16%~17%⑪17%~ (2)ワンルームタイプ賃貸マンション ①~8%②8%~9%③9%~10%④10%~11%⑤11%~12%⑥12%~13%⑦13%~14%⑧14%~15%⑨15%~16%⑩16%~17%⑪17%~ (3)店舗(一般的な店舗) ①~10%②10%~11%③11%~12%④12%~13%⑤13%~14%⑥14%~15%⑦15%~16%⑧16%~17%⑨17%~18%⑩18%~19%⑪19%~20% ⑫20%~ (4)店舗(中心市街地の飲食店舗) ①~12%②12%~13%③13%~14%④14%~15%⑤15%~16%⑥16%~17%⑦17%~18%⑧18%~19%⑨19%~20%⑩20%~21%⑪21%~22%⑫22%~ (5)事務所(一般的な事務所) ①~10%②10%~11%③11%~12%④12%~13% ⑤13%~14%⑥14%~15%⑦15%~16%⑧16%~17% ⑨17%~18% ⑩18%~19%⑪19%~20% ⑫20%~ 問3 一般の投資用物件に対して競売不動産の持つ「リスク率」(競売物件特有の売主の協力が得られない場合が多い、事前に物件に立ち入れないこと等による減価)は利回り(問2と同じ粗利回り)でどの程度考慮されますか。 (例:一般物件の賃料収入600万/年に対して投資額が5,000万であれば600万/5,000万=12%ですが、競売物件だと投資額を若干低目とすることが予想され、仮に4,000万とした場合は、600万/4,000万=15%になります。この差3%(15%-12%)を競売によるリスク率とします。) ①差はない②1%程度③2%程度④3%程度⑤4%程度 ⑥5%以上⑦その他( %程度) 問4 競売不動産(収益物件)を転売してキャピタルゲインを目的とした場合の利益率はどの程度を目安としていますか。 ①~10%②10%~20%③20%~30%④30%~40% ⑤40%以上 問5 過去に競売不動産(収益物件)を転売して損失が生じたことがある場合、どの程度の損失だったでしょうか。 ①損失が生じたことはない②諸経費程度③10%~20% ④20%以上 問6 その他意見等があればお聞かせください。 御 社 名 御担当者名 アンケートは以上で終りです。御協力どうもありがとうございました。 |
Ⅲ 調査結果
1 粗利回り(落札利回り)
グラフ1
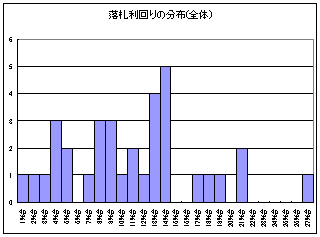
表1
| 所 在 | 地域種別 | 物件用途 | 評価梨利回り | 落札利回り |
| 松山市泉町 | 住居系 | 共同住宅 | 6.97% | 4.24% |
| 松山市福音寺町 | 住居系 | 共同住宅 | 5.20% | 4.82% |
| 松前町大字西古泉 | 商業 | 共同住宅 | 5.56% | 5.49% |
| 松山市御幸2丁目 | 住居系 | 共同住宅 | 8.22% | 7.93% |
| 松山市三番町5丁目 | 商業 | 共同住宅 | 8.89% | 8.73% |
| 松山市南吉田町 | 住居系 | 共同住宅 | 13.13% | 9.05% |
| 松山市小栗3丁目 | 住居系 | 共同住宅 | 13.93% | 9.07% |
| 松山市久万ノ台 | 住居系 | 共同住宅 | 10.49% | 9.47% |
| 松山市道後姫塚 | その他 | 共同住宅 | 14.41% | 11.32% |
| 松山市雄郡1丁目 | 住居系 | 共同住宅 | 17.74% | 12.33% |
| 松前町大字筒井字義農 | 商業 | 共同住宅 | 16.03% | 13.10% |
| 松山市高砂町3丁目 | 住居系 | 共同住宅 | 16.13% | 13.84% |
| 松山市木屋町1丁目 | 商・住混在 | 共同住宅 | 24.17% | 14.67% |
| 松山市雄郡1丁目 | 住居系 | 共同住宅 | 18.85% | 14.89% |
| 中島町大字大浦 | 住居系 | 共同住宅 | 17.05% | 17.05% |
| 松山市内宮町 | 住居系 | 共同住宅 | 27.81% | 27.78% |
| 共同住宅系平均 | 11.49% | |||
| 松山市保免西4丁目 | 住居系 | 更地、駐車場 | 2.08% | 1.09% |
| 松山市南堀端町 | 商業 | 更地、駐車場 | 3.50% | 2.91% |
| 更地駐車場系平均 | 2.00% | |||
| 松山市中央1丁目 | 住居系 | 事務所 | 17.06% | 14.04% |
| 松山市喜与町2丁目 | 商業 | 事務所・共同住宅 | 5.98% | 3.07% |
| 松山市平和通5丁目 | 商業 | 事務所・共同住宅 | 4.41% | 4.34% |
| 松山市勝山町1丁目 | 商業 | 店舗・共同住宅 | 5.16% | 5.16% |
| 松山市小坂4丁目 | 住居系 | 店舗・共同住宅 | 8.63% | 8.02% |
| 松山市歩行町1丁目 | 商業 | 店舗・共同住宅 | 12.83% | 11.84% |
| 松山市千舟町7丁目 | 商業 | 店舗・共同住宅 | 18.05% | 13.00% |
| 松山市海岸通 | 工業 | 店舗・共同住宅 | 15.32% | 14.66% |
| 松山市立花3丁目 | 商業 | 店舗・共同住宅 | 22.55% | 21.04% |
| 松山市湊町5丁目 | 商業 | 店舗・事務所ビル | 18.43% | 8.25% |
| 松山市千舟町4丁目 | 商業 | 店舗・事務所ビル | 14.19% | 14.14% |
| 松山市千舟町5丁目 | 商業 | 店舗・事務所ビル | 32.19% | 19.84% |
| 松山市千舟町5丁目 | 商業 | 店舗ビル | 13.60% | 10.30% |
| 松山市三番町1丁目 | 商業 | 飲食店舗ビル | 18.10% | 13.91% |
| 松山市三番町2丁目 | 商業 | 飲食店舗ビル | 19.74% | 18.94% |
| 松山市二番町1丁目 | 商業 | 飲食店舗ビル | 36.57% | 21.35% |
| 商業系平均 | 12.62% | |||
(評価利回りは、総収益を担当評価人の評価額で除した利回りで、参考までに併記した。地域種別は筆者の判断。)
(1) 全体
1.09%から27.78%までの分布となり、予想どおり幅広く分散した。ただし、この中には、更地の駐車場に係るものが二つ含まれており、それぞれ、1.09%、2.91%であるから、これらを除くと、3.07%から27.78%の分布となる。
既述のとおり今回は生データ結果を重視したため、評価時点で空室分の賃料を査定して計上しておらず、かなり低い結果が含まれている。以下、共同住宅系と商業系についての結果を概観する。
(2) 共同住宅系
① 結果数値
最小値:4.24%、最大値:27.78
平均値:11.49%、中央値:10.40%
標準偏差(σ):5.75%
信頼度95%の信頼区間数値8.42%~14.55%
(但し、自由度(n-1)のt分布推計、危険率5%)
② 分布結果の分析
利回りの低いものは、やはり空室が多い物件である。一方、高いものは、建築後経過年数が経っているが、評価時点で空室が少なく、今後空室発生が予想される特殊な物件であると判断される。したがって、実際に収益還元法を適用する場合には、空室の多い物件での空室分収益の査定計上と逆に空室の少ない特殊物件での事後の空室リスクの査定計上が必要と思われる。
③ 利回り
データ数(n)は16と少ないものの、信頼度95%の信頼区間数値(利回り)は、8.42%~14.55%であるから、ほぼ予想された利回りである。この数値は、昨年の一般物件での調査結果、粗利回りの信頼度95%の信頼区間数値(利回り)10.91%~14.97%(注3)と比較してもほぼ同様の傾向値である。
以上のことから、11.5%を中心として、物件特性(リスク等)に応じた±3%程度開差という利回りを仮に設定することができないだろうか。(東京競売不動産評価事務研究会での同様の試みでは結果が広範囲に分散するため「平均値は求められるが、個々の物件の属性を反映した標準的な利回りを求めることはできなかった。」との報告がある。(注4))
(3) 商業系
① 結果数値
最小値:3.07%、最大値:21.35
平均値:12.62%、中央値:13.46%
標準偏差(σ):5.84%
信頼度95%の信頼区間数値9.51%~15.73%
(但し、自由度(n-1)のt分布推計、危険率5%)
② 分布結果の分析
最小値の3.07%の物件は、自用部分と貸家部分からなる物件であるが、自用部分について貸家を想定した収益を計上しておらず、異常に低い数値となっている。この外、5%台までの物件は特殊な物件である。一方、高いものは飲食店舗ビルを中心に相当高いリスク率が含まれていると判断される。
③ 利回り
商業系物件については、共同住宅系以上にリスクが大きく、利回りにリスク率をどのように反映させるかが問題になると思われる。
信頼度95%の信頼区間数値(利回り)として、9.51%~15.73%という結果は導かれたものの、商業系物件については、20%を超えるものもリスクを考慮すれば、特に異常な数値ともいえないようである。
したがって、商業系については、一応の目安の数値としては、12.6%を中心として±3%を標準とするものの、リスクの大きいものは+10%程度のリスク率加算も必要ではないだろうか。この辺りの判断については、今後さらに議論が必要と思われる。
2 アンケート調査
松山地裁本庁管内23人のうち、有効回答数7(うち1人は宇和島支部管内在住)、
同西条支部管内9人のうち、有効回答数5、
同今治支部管内9人のうち、有効回答数3、
なお、質問項目のうち、回答のなかった項目があるので、項目による総数は一致しない。
(1) 物件に入札する際の検討項目 表2
| 物件の立地条件 | 14 |
| 物件の建築後経過年数 | 8 |
| 物件の維持管理の状態 | 2 |
| 物件の規模(延床面積) | 1 |
| 現在の賃料収入 | 6 |
| 将来の賃料収入予測 | 10 |
| 現在の入居率(空室率) | 3 |
| 入居者(テナント)の属性 | 1 |
| その他 | 0 |
(2)投資利回り目安
① ファミリータイプ賃貸マンション グラフ2
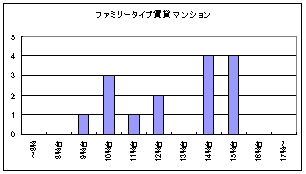
② ワンルームタイプ賃貸マンション グラフ3
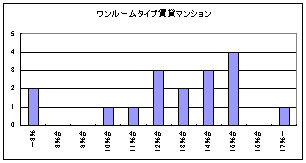
③ 店舗(一般的店舗) グラフ4
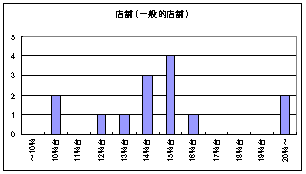
④ 店舗(中心部飲食店舗) グラフ5
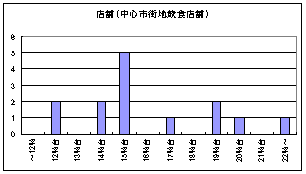
⑤ 事務所 グラフ6
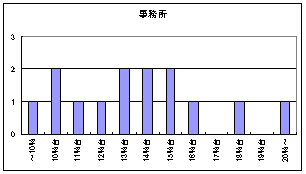
(2) リスク率 表3
| 2%程度 | 1 |
| 3%程度 | 7 |
| 4%程度 | 3 |
| 5%以上 | 4 |
(3) キャピタルゲイン目的利益率 表4
| 10%~20% | 4 |
| 20%~30% | 7 |
| 30%~40% | 4 |
(4) 過去の損失 表5
| なし | 5 |
| 諸経費程度 | 1 |
| 10%~20% | 3 |
| 20%以上 | 1 |
(5) アンケート調査結果分析
① 共同住宅利回り
ファミリータイプの賃貸マンションの利回りは、「9%台から15%台」に収束し、上記1落札利回り(2)共同住宅系の信頼度95%の信頼区間数値(利回り)「8.42%~14.55%」とほぼ一致した。落札利回りの調査結果が、アンケート結果により検証できたと思われる。(アンケートは、松山、西条、今治地域に分かれたが、地域による数値偏向性は認められなかった。以下同じ。)
ワンルームタイプは、賃料単価がやや高く、入退居が多いため、理論値としては利回りがやや高めになる傾向が推定されたが、アンケート結果では、17%以上の回答が1件あった以外には、ファミリータイプに比して特に開差は認められない。
② 店舗利回り
一般的店舗と中心部の飲食店舗を分けてアンケート調査したが、いずれも15%台を頻出値として幅広く分散した。飲食店舗のリスクが予想されたが、アンケート調査結果を見る限り、特にこれらの相違を意識した結果は認められない。
③ 事務所利回り
事務所については、頻出値はなく、10%前後から20%以上まで、見事に結果が分散した。
回答者によって、想定した物件特性が異なることが原因とも考えられるが、このことは、共同住宅系と異なり、物件によって10%程度のリスク率開差が存在することを証明したのかもしれない。
④ その他
リスク率は、競売物件と一般物件の違いによるリスク率を質問した。質問で具体的数値の例示をしたために、これにより誘導されてしまった感も否めないが、3%程度が最も多く、次いで、5%以上、4%程度となった。つまり、一般物件と競売物件の違いによるリスク率よりも、競売物件における事務所等の物件特性の違いによるリスク率の方がはるかに大きいということである。(競売不動産評価における個別物件特性による価格差は非常に大きく、評価人による適正な評価の重要性を再認識させられた。)
その他関連する質問項目に対する結果は上記のとおりである。また、その他意見として、「物件に事前に立ち入れないのだから、写真等わかりやすい資料を」という意見が寄せられていたのでここで紹介しておきたい。私自身の自戒も含めて、諸先生方の評価の際の参考にしていただきたい。
Ⅳ おわりに
1 調査結果のまとめ
(1)共同住宅系
11.5%程度を標準として、一般的には、物件特性に応じて±3%程度の調整を要する。(但し、一般的でない物件については、別途検討を要する。)
(2)商業系(店舗、事務所)
落札利回り調査結果では、一応の目安として、12.6%を中心に±3%程度の数値に信頼度95%の信頼区間数値が収束する。
しかし、他方、アンケート調査結果では、店舗系は15%程度を頻出値として幅広く分散し、事務所系は、ほぼ10%程度から20%程度まで等しく分散することから、標準的な利回り数値を設定することはできない。これは、評価時点の実際支払賃料が適正かどうか、リスク率の問題をどう処理するか、とも絡んだ問題であるため、利回り単独の問題ではなさそうである。今後さらに議論、検討が必要と思われる。
2 その他
今回、競売不動産に係る収益物件の落札利回り調査と入札参加者へのアンケート調査を実施したが、利回りに関しては、一般物件との差はあまりないように感じられた。(人気物件については、競売であっても競争原理が働き、評価利回りに対して落札利回りは相当下落している。)
最後に、競売不動産に係る利回りについては、東京、大阪、名古屋をはじめ、先進庁での議論が進んでいると思われるが、本調査結果が、愛媛や四国における今後の議論の叩き台になれば幸いである。
(注1)大西泰祐「取引利回りについて」(「鑑定四国」(2001.12.20No.18)21頁Ⅲ2(4))参照
(注2) 本庁管内は筆者が入札情報等を基に選定したが、西条支部管内は平田耕二先生に、今治支部管内は渡辺正隆先生に選定をお願いした。
(注3) 前掲(注1)20頁Ⅲ1(1)参照
(注4) 「不動産鑑定」2002.10(住宅新報社)48頁。「わかりやすい競売評価実務-収益還元法-東京地裁における競売不動産評価の収益還元法の適用」での小谷先生の報告