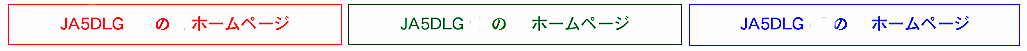| 狸詠嘆の文献 えい‐たん【詠嘆・詠歎】 声を長く引いて歌うこと。 声に出して感嘆すること。 感動すること。感嘆。 |
|
| 狸を詠んだ和歌、狂歌、連歌(俳諧)、俳句、川柳さては童謡に民都は古来かず限りなくあって謡曲や長唄にもうたわれている。 |
| 〇 和歌 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
| 昭和二十六年の秋、近畿地方御旅行の節、大津にて信楽焼きの狸像の行列に迎かえられて詠まれた天皇の御歌 |
| 「幼な時集めしからになつかしも信楽焼の狸を見れば」 |
|
| にとあり、天皇も幼少の頃は狸像蒐集の御趣味があったことがうかがわれるのである。 |
|
| 腹つゞみ打つや深山の穴狸 |
|
あやに楽しき御代の秋とて |
|
季恭 |
|
|
|
|
|
| 住みなれて奥山寺を月今宵 |
|
面白狸つゞみ打つなり |
|
惟貞 |
|
|
|
|
|
| 恩ふことならで幾夜を古狸 |
|
楽しかる音を打つつゞみかな |
|
千陰 |
|
|
|
|
|
| 更けぬるか時の鼓は打ちやみて |
|
あらぬ音こそ野辺にきこえれ |
|
景樹 |
|
|
|
|
|
| 世の中の調べによしや合はず共 |
|
われ腹つゞみ打ちて遊ばん |
|
高畠式部 |
|
|
|
|
|
| 人住まで鐘も音せぬ古寺に |
|
狸のみこそ鼓打ちけれ |
|
寂蓮法師 |
|
|
|
|
|
| 深山辺に鼓の音の聞ゆるは |
|
幾ももとせの古狸かな |
|
麗尾部 |
|
|
|
|
|
| 奥山に松が琴弾きや芒が踊る |
|
狸浮かれて腹つゞみ打つ |
|
失名 |
|
|
|
|
|
| やよ狸まし鼓打て琴ひかん |
|
われ琴ひかんまし鼓打て |
|
" |
|
|
|
|
|
| 調子よくたぬ鼓打ってわたづみの |
|
いざ狸うて鼓打て小夜更けて |
|
” |
|
|
|
|
|
| 人はいざかかる深山の楽しみも |
|
知らじ狸の鼓聞くとは |
|
紀忠基 |
|
|
|
|
|
| やよ狸鼓なやめぞ今しばし |
|
人もかよはじ夜は明けぬとも |
|
“ |
|
|
|
|
|
| やよ狸なれが鼓の音づれも |
|
片山里の友とこそきけ |
|
斐成 |
|
|
|
|
|
| 長き夜を化けおほせたる古狸 |
|
尾先な見せぞ山の端の月 |
|
番岳上人 |
|
|
|
|
|
| 古狸酒もとむるや雨の夜の |
|
そのつれづれのすさびなるらん |
|
大田垣蓮月 |
|
|
|
|
|
| 夜もすがら遊ぶ狸の昼寝せし |
|
夢おどろかす入相の鐘 |
|
紀忠基 |
|
|
|
|
|
| 深山辺はまだ宵ながら淋しきを |
|
なくさめとてや狸くるらし |
|
“ |
|
|
|
|
|
| 飛火重にあられど背おふしい芝の |
|
もへ出づるにぞ狸なくらし |
|
" |
|
| 東京根岸に病む正岡子規居士が郷里の松山市にある八股お袖狸の榎大明神を詠んだ望郷の歌に |
| 餅あげて狸を祀る枯榎 |
|
紙の幟に春雨ぞ降る |
|
|
|
| 百歳の狸すむてう八股の |
|
ちまたの榎いまあるやなしや |
|
|
| また松山市の郷土史家にして歌人であった影浦稚桃翁の詠める |
|
| 桜咲く夕日の丘に麗人の |
|
あなにやしゑやまみわざならし |
|
| ○ 狂歌 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |

| 寿きを長地に打てや腹つゞみ |
|
タタタ狸のチチ千歳まで |
|
蜀山人 |
|
|
|
|
|
| 世の中は兎角狸の泥の舟 |
|
漕ぎ出さぬがカチカチの山 |
|
高橋泥舟 |
|
|
|
|
|
| ぽんぽんが痛いと嘘をつきの夜に |
|
鼓の稽古休む子狸 |
|
失名 |
|
|
|
|
|
| 丑三ツに吹き来る風の音づれは |
|
ね入り狢の目やさますらん |
|
京伝 |
|
|
|
|
|
| 冬がれて荒れたる野辺の腹つゞみ |
|
これや狸の化けのかは音 |
|
参和 |
|
|
|
|
|
| 分福の茶釜にばけのはへたるは |
|
上手の手から水のもりん寺 |
|
酒舟 |
|
|
|
|
|
| のびちゞむ八畳敷のたたみざん |
|
狸ね入りに君をこそまで |
|
四方上人 |
|
|
|
|
|
| 腹までもまだ入り足らずうましとて |
|
舌つゞみ打つ狸汁かな |
|
貞徳 |
|
|
|
|
|
| ふきがらで狸ね入りを見てとられ |
|
床の狐が腹つゞみうつ |
|
万亭 |
| 古稀までも裸で住みし世の中を |
|
今更ら化けて通るてもなし |
|
| 〇 連歌(俳諧) 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
| 蕪村七部集明烏中に |
| ふししげき竹を簀に組みわびて |
|
|
|
凡董 |
|
|
|
|
|
|
|
日頃の狸来ずなりにけり |
|
蕪村 |
|
|
|
|
|
| 股引の朝からぬるる川越へて |
|
|
|
凡董 |
|
|
狸をおどす篠張りの弓 |
|
史邦 |
|
| とある。 |
| 元禄の頃、宝井其角が書き残した「狸歌仙」は日向の国で俳人の魯山が、化けた古狸と風流を語り、気の合うままに両吟の付合わせを巻いたというその一節に |
| 八畳を月に目のりの住居かな |
|
魯山 |
|
|
|
| 雨の降る家の秋の造作 |
|
狸 |
|
|
|
| 菊の名に酒買うほどは銭ありて |
|
魯山 |
|
|
|
| 忘れては又捨てた世をなげき |
|
狸 |
|
| とあり、三十六句の両吟を巻き終った時、魯山がウッカリ煙草の火を畳に落した途端、忽ち八畳の草庵は消え失せて魯山はドッと夜の大地に投げ出されたという。この八畳の草庵こそはいうまでもなく古狸の八畳敷の芸当であったのである。 |
| さて俳句のメッカといわれる松山に俳諧研究の文献が少ないのは残念である。子規居士は俳諧から独立した発句を俳句と改称して俳文学を盛り立てたが、その母体である俳諧は文学の遊戯で文学的価値が乏しいと言って軽んじたが決してその研究を怠ったものではない、研究するまでの寿命が許されなかったのである。これを裏付ける文献として明治二十八年頃、松山地方の俳諧の宗匠であった宇都宮丹靖翁と両吟の付合わせをした連歌が残っている。虚子や碧梧桐が俳諧の研究に着手したのは子規の没後であって、若し子規をして俳諧研究に時間を与えしめたら古い式目を排して新しい形式の俳諧文学が打ち立てられたにちがいないと思う。 |
| さて愛媛県内の狸に関する連歌の文献に付ては愛媛大学の和田茂樹助教授から教示されたものに「大山祇神社連歌」(和田茂樹編)奉納一万句の中の文明十四年(一四八二年)七月二十七日 |
| 三 |
| 第四、賦何塩連歌中に、 |
|
|
| の前句に対し |
|
|
| の付句がある。たのきは伊予の方言で狸である。今から約四八〇年前のものであるから、文芸に現われた狸としては県内最古の文献だろうということである。芒の茂る草深いところには兎角狸がうかれ出すことになっている。 |
| また和歌の方では「宇和旧記」中にあるもので天正四年(一五七六年)か、とあるから今から約三九〇年前のこと、これは板島丸串(いまの宇和島、板島を宇和島と改めたのは文禄四年)の城主西園寺公広の兄弟宜久の伊勢参宮記の項に載せられたもので八月一日、鞆にて宿を得た時、 |
| ゆがみねる二かいに居れば下よりも |
|
焼ふすべられ狸にぞなる |
|
| と詠まれている。その宿は荒れ果てて狸でも住みそうな二階であったことが偲ばれる。狸を生け取るには生マ松葉をふすべて追い出す方法があるが、宜久公がゆがみかかった二階で、狸のように下から焼きふすべられて右往左往していた情景を思うと、庶民でないだけにほほ笑ましい歌であり、いずれにしても県内の古い狸文芸である。 |
| ところで「たぬき」とは直接の関連はないが、私の俳諧師匠であった故田中野狐禅翁(東京、本名政秋)と巻いた俳諧のうちの一巻をご披露して大方のご批判を乞う。 |
| 言うなれば野狐禅と狸通の付合わせで「狐狸俳諧譜」とも言えるものである。 |
| 両吟「梅雨晴の巻」昭和二十九年 |
|
|
|
|
|
| 梅雨晴を一とむら伸びて縞芒 |
|
野狐禅 |
|
|
|
| 枝蛙つく朝戸出の下駄 |
|
狸通 |
|
|
|
| 青簾かけてたたくは箔やらん |
|
狐 |
|
|
|
| きらびやかにも帯の縫取り |
|
狸 |
|
|
|
| 樹立透く池広々と月の影 |
|
狐 |
|
|
|
| 話もほどけ虫送る鉦 |
|
狸 |
|
|
|
| 爺婆の念仏踊り三夜待 |
|
狐 |
|
|
|
| 離れた慾に倖せが来る |
|
狸 |
|
|
|
| 人の顔見れば物やる酒の癖 |
|
狐 |
|
|
|
| たしかにあった当りくじ券 |
|
狸 |
|
|
|
| ほのぼのと恥らいのぼる頬の艶 |
|
狐 |
|
|
|
| 傷付く胸を旅にさすろう |
|
狸 |
|
|
|
| 月明かしおもい寝の宿淋しうて |
|
狐 |
|
|
|
| 又借りに行くどぴろくの銭 |
|
狸 |
|
|
|
| 紅葉する柿の巨大の二タところ |
|
狐 |
|
|
|
| 燈火親しき窓見えかくれ |
|
狸 |
|
|
|
| ととさまいのうと子役の又泣かせ |
|
狐 |
|
|
|
| 縁日追うて花屋台曳く |
|
狸 |
|
|
|
| 蝶々の吹きあげられし高き崖 |
|
狸通 |
|
|
|
| 手杓浮けある春水の中 |
|
野狐禅 |
|
|
|
| 国宝の修理も成りて捨頭巾 |
|
狸 |
|
|
|
| 草霞む山雨にじむ空 |
|
狐 |
|
|
|
| 頑に住みて疎まれ留守の庵 |
|
狸 |
|
|
|
| 結び文して簪(かんざし)落ちてる |
|
狐 |
|
|
|
| 逢曳の刻に遅れて橋の上 |
|
狸 |
|
|
|
| 円板が飛ぶ天も物うき |
|
狐 |
|
|
|
| そうらしき意気な雪駄の音をきく |
|
狸 |
|
|
|
| 燭をとる手に菊の薫れり |
|
狐 |
|
|
|
| 月に座すうしろ姿は尼ぜなる |
|
狸 |
|
|
|
| 芒ゆらゆら化生めかして |
|
狐 |
|
|
|
| 鰯雲湧く時占う習いあり |
|
狸 |
|
|
|
| わが警備船羅致されし報 |
|
狐 |
|
|
|
| 次ぎ次ぎに解かれて踊る猿芝居 |
|
狸 |
|
|
|
| 汚職の大臣恥知らぬ言 |
|
狐 |
|
|
|
| 日の本の民主未だし花の散る |
|
狸 |
|
|
|
| 道後温泉祭春の魁 |
|
狐 |
|
|
| ○ 俳句 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
| 「狸は冬月に極肥し、山珍の首なり」といって季題は大体冬季になっている。狸肉、狸汁、狸狩などは冬季に属するが、腹鼓はおぼろ夜の春季か、明月の秋季の方がよさそうである。また縁台の話題になる狸は夏季に限る。いずれにしても七変八化で春夏秋冬を通じて季題とくっ付けて融通性がある。 |
| 春 |
|
|
| 大榎狸の穴の木の芽かな |
|
飄 亭 |
|
|
|
| 飼いなれて狸寝まねん花の雨 |
|
李 朝 |
|
|
|
| 鼓打つ音は狸かおぼろ月 |
|
兎 玉 |
|
|
|
| 夏 |
|
|
|
|
|
| 弘法を狸にしたる蚊遺かた |
|
支 考 |
|
|
|
| 霽月や蝙蝠つかむ豆狸 |
|
子 規 |
|
|
|
| 山里は狸もまじる踊哉 |
|
花 弄 |
|
|
|
| 珍らしや匂いも夏の狸汁 |
|
狐 麦 |
|
|
|
| 同行はたぬきなりけり木下闇 |
|
残 花 |
|
|
|
| 秋 |
|
|
|
|
|
| 戸を叩く狸と秋を惜しみけり |
|
蕪 村 |
|
|
|
| 秋の暮仏に化ける狸かた |
|
” |
|
|
|
| 秋惜しむ戸に音づるる狸哉 |
|
” |
|
|
|
| 狸死に狐留守する秋の風 |
|
子 規 |
|
|
|
| 小のぼりや狸を祀る枯榎 |
|
” |
|
|
|
| 秋の暮狸をつれて帰へりけり |
|
” |
|
|
|
| 猿松の狸を繋ぐ芭蕉かな |
|
” |
|
|
|
| 祭獅子荏原狸がまねを打つ |
|
雷死久 |
|
|
|
| 化けて来し狸と秋を語りけり |
|
極 堂 |
|
|
|
| 冬 |
|
|
|
|
|
| 子を遺う狸もあらん小夜時雨 |
|
蕪 村 |
|
|
|
| 草庵の炬燵の中や古狸 |
|
丈 草 |
|
|
|
| 炭はねて庫裡に狸の走るなり |
|
大江丸 |
|
|
|
| (三津にて狸伴に贈る) |
|
|
|
|
|
| 獺を狸の送る夜寒かな |
|
子 規 |
|
|
|
| 古家や狸石打つ落葉かな |
|
” |
|
|
|
| 戸を叩く音は狸か薬喰 |
|
” |
|
|
|
| 枯野原汽車に化けたる狸あり |
|
漱 石 |
|
|
|
| 冬ざれや狢をつるす軒の下 |
|
” |
|
|
|
| 狸来て叩く雨戸や夜半の冬 |
|
霽 月 |
|
|
|
| 薮寺の炬辺へ狸のあからさま |
|
極 堂 |
|
|
|
| 宿訪へば狸出で来ぬ時雨寺 |
|
” |
|
|
|
| 罠のまま逃げてしまいし狸かた |
|
文 方 |
|
|
|
| 狩くらの月に腹うつ狸かな |
|
蛇 笏 |
|
|
|
| 犬の子を狸はぐくむ霜夜哉 |
|
暮 野(子規別号) |
|
|
|
| 四季申(タヌキ) |
|
狸 通 |
|
|
|
| 伴連れて狸化けこむ花の宿 |
|
|
|
|
|
| 狸出た出ぬの噂の涼台 |
|
|
|
|
|
| 猶も澄む月へ狸の腹っゞみ |
|
|
|
|
|
| 杣ケ家の話も荒らき狸汁 |
|
|
|
| ○ 川柳 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
瓢逸と明朗、皮肉と風刺を詠む川柳の題としては狸は打ち付けのものであろう。そして古川柳では狸を観念的に掘り下げて詠んでいる。
| 狸の遺言決して茶釜には化けるなよ |
|
| 茶釜に成って狸も困り果て |
|
| ぷんぶくは人を茶にして変化なり |
|
| 金玉に寝た夜もあり武者修行 |
また狸を詠んだ紅灯下の標客の句が多いのは古川柳の妙味でもある。
| 化けて来た狐狸を起すなり |
|
| 狐をぱ化かして帰へる古狸 |
|
| 起きなんしょなどと狸へよりかかり |
「川柳の雑誌」主管の麻生路郎氏選による最近の川柳では
| 拝まれる身になり狸老いはてる |
|
水 客 |
|
|
|
| 山門に別の狸がいる月夜 |
|
健 作 |
|
|
|
| 夕月に笠のけて見る化け狸 |
|
八 歩 |
|
|
|
| 腹つゞみ打つほど狸食うていず |
|
帆 船 |
|
|
|
| 斯う化けて見よと狸は子を育て |
|
路 郎 |
|
|
|
| 難産に狸は医者をよびに化け |
|
” |
前田伍健翁の川柳には次のようなうがったものがある
| 化け狸うっかり尻尾忘れたり |
|
| 花が降る笠きて狸化けて来い |
|
| 狸々汝元来霊か実か |
|
| 伝説の狸めでたし不老不死 |
|
| 逆立ちの狸に邪魔なものがあり |
|
| 狸曰く人よあくせくしなさんな |
|
| 人間の欲を笑って狸寝る |
|
| ○ 能狂言「狸の腹鼓」あらまし 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
古塚に住む女狸が、帰りのおそい夫をたずねて鳥部山のふもとにさしかかる時、その夫狸を射止めたる猟師に出逢いける。狸は大いになげき且つ怖れをなしけるが思い切って猟師に向って言える「天笠の伜という魔王は釈迦の教化により、我身の皮を仏に供養して太鼓となし生前の殺生の罪を懺悔したり善哉」女狸にさとされた猟師は己の罪を詑び殺生を悔いて立別かれる。
夫の仇討も叶わぬ女狸は、せめて猟師に不殺生の善戒を垂れ得たるをよろこび、其功徳を以て腹の子も無事に産み落し育てること叶うべしと、自らを慰めて腹つゞみしつつおぼろ月の夜道を古塚の穴に帰らんとしける。これを見た猟師は浅間しくまた欲の皮を突っ張って、魔王の不殺生訓を忘れ無慈悲にも孕狸に銃先きを向けて射んとする。おどろいた女狸は太鼓のような腹を示して、消ゆる我身はいとわねど生れ出る子の不憐やいとしや、見逃し玉えと嘆願つくす。助け願えれば御礼として人間界にはかつてなき狸の鼓を打ちて聞かせんと、早々腹を鼓としポンポンポンと叩きければ、狸寝入りか不思議にも夫狸は生き返り、おどろく猟師も共々によろこび合って泰平をめでたしめでたしと歓をつくして夜を更かすという筋の秘曲である。 |
| ○ 長唄 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
長唄の「たぬき」は一名を「浮世ぷし狸」ともいい、今からざっと百年ほど前の元治元年(一八六四年)に杵屋勝三郎師匠が作詞したものである。勿論その以前にも「狸」の唄はあったというが、現在唄われているのは勝三郎の作である。この唄は狸に関係のある話を一曲の中にまとめたもので、唄出しは荘重なる大薩摩で始まり、分福茶釜からカチカチ山、広尾野の狸長屋のソソリ節があり、また端唄調や新内調子もとり入れて月夜の腹鼓があり、最後は剽軽で賑やかに狸ばやしで綱渡りに終る茶気満々たる滑稽で、しかもめでたい唄である。
現在地方の長唄界ではうまく唄いこなす唄い手が少なという珍しい名曲である。故人では富土田吉治師匠から伝授されて名手になった坂田仙八師匠の専売芸でもあった。長唄「たぬき」それ伝へ聞く茂林寺の分福茶釜のその由来、あやしくもまた面白き、昔々その昔、姿喰った爺の狸汁、縁の下やの骨までも広野原の狸そば、のびた鼻毛をほおかむり、たぬき長屋をエエ廻はろ廻はろとそそり節、月はさゆれど心はさえぬ、さえた月夜も闇となる、可愛いお方にみのかさきせて、他からならべりゃ尚よかろ、山で寝る時や木の根がまくら、柴を背負ったら気を付けろ、火の用心さっしゃりやしょう女「オヤオヤ源はん、どこえおいでだエ、一服のんでおいきなはいヨ」、狸「アアいてえいてえ、ひでえことをするな、背中の火傷がまだ治らねエ」おやお気の毒、ここに狸のあんぽんたん、飲んでくだまきゃエーイ、のうまくさまんだ、ぱさらんだ、狸にござる法印さん、じたい我等は田舎の生れ、月に浮かれて腹つづみ、打つやうつつの夢の夜を、八畳敷の炉にかけし、茶釜尻尾をオヤオヤ振り立てて、狸ばやしの音につれて、あるいは軽業綱渡りぢゃ、サテサテサテこの度のお目にかけます軽業は、綱の半ばに大き
な狸を引っかけて、これを名付けてかんたん狸の夢の枕ぢゃ、おもしろ狸の角兵衛獅子おかしらし神変不忠議の有様は治まる御代の話草今にその名を残しける。 |
| 松山市で作られた狸長唄 |
| 「お袖」 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
| 昭和二十二年十二月,吉田橙子氏の作。解説に曰〈勝山城に多年住へるお袖狸の親子が現ほれ、お袖は過ぐる年、この町の灰になりし(戦災)述懐に沈む、されど復興の力強きを子狸に語り、親子狸は復興祭の町の灯をよろこび拍子を合はせ満月を浴びて暁まで踊りぬく、一名を復興狸とも云う夫れ南海の景勝のその名も高き湯の郡、中に聳ゆるお天守を囲みて繁き煙草山、先づは一服召しあがれ聞え申さん古狸、お袖の君の物語、西よ東よ南北、友どち多きやっがれの住いは古き石垣の傾き覆う茅草の蔭に横たう狸穴(まみあな〕に姿見せたる親子連れ。去んぬる年の水無月十五夜、祝融(しゅくゆう)の災いあり、古町に上る火の柱、折からの烈風に天魔のわざか見入られし紅蓮の焔は末広に西の京(みやこ)と云はれたる、この松山の灰燼に長年我れの住いたる八股榎もあとなきさま、わが同胞(はらから)と誓いたる町人(まちひと)ひとしく右往左往、住むに家なく喰らうに食なき有様を泣くなくもこの山中の我がすみか、倚りて眺むる欄干の天守櫓も今なしと祈る東雲(しののめ)の神の霊験ありとても罪なき人の困厄(こんやく)を如何にか仇に見らるべき。さるにても人力ひとにすぐれたる
この里人(さとひと)の復興はめざましくも雄々しく打つや木槌の音高く今新たにも生る街、巷々は広やかに甍再び重りて道行く人もおほどかに、成る再建の喜びを今宵は共に喜ばん、今夜は共に舞はんかな。折からさせる月魄(つきしろ)は森の梢にさしかかり見るや戸毎の提灯の火色 (ほいろ)映れる濠の水、ゆらくと見しは花電車、上る花火の音高く拍子合はせてポコポンポコポン、めぐる盃数知らず紫竹の門の内外に糸竹管紘のあそび事、打つや腹鼓ボコポンボコポンポンポコポン、ポコポン、筒井の門を筒抜けて表(おもて)小富士に届くまでボコポン、裏(うら)石槌に響くほどポコポンポコポン、叩く手拍子軽るやかにポコポンポコポン、舞うや足どり軽るやかにポコポンポコポン、かざす扇子は持たねども取るや尻尾の太総(ふとふき)を打ちふリ打ちふり声高く指す手引く手の親子連れ八畳敷はおろかおろか、狸囃子のボンポコポン、山一とめぐり踊りぬき、巷(ちまた)八ちまた賑いの山の上下を一色に月天心を漕ぎぬけて忽那の島に沈むほど櫓々のうからやからも声を揃えて千木高々と東雲の雲の横雲匂い出るまで踊りぬく、めでたかりける次第なり.めでたかりける次第なり。 |
| 「狸ばやし」 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
| この長唄狸ばやしは昭和二十三年、前田伍健氏の作詞で、作曲は望月太郎氏両氏ともすでに故人となった。望月氏はこの曲譜を作るに当り、月のよい夜の石手川堤防を再三逍遥して苦心されたということである。そして翌年十月二十三日、榎町の元御宝教会で松山大桜会の主催になる望月師匠追善演奏会の時、発表された長唄である。 |
| むかしむかしそのむかし、かちかち山の泥の舟、うっかり漕いでいましめのヨイヨイヨイヤサ世の中の教え語りに笑はれたタタタ狸の恩返し、くめどもつきぬ分福の茶釜にめぐむ一はやし、遠くて近くで鳴るつゞみチラチラホラホラ散る桜、ともせ提灯ブウラブラ、うてやサッサ腹つゞみ身は粗末なる破れ笠、縁起徳利に福通い、すすき穂風に千金の,月夜だ感謝だボンポコポン、囃せうれしき豊年の、浮夜風稚な草枕、さとりすませばなごやかな、笑いにまるい心意気、誰が知ってか察してか、赤い鳥居にあずきめし果報うれしき油あげ、丸に八の字立てのぼり、末広がりの目出度さを、今宵も感謝腹つゞみ、月も浮かれてのぞきこむ、すすきも共にお手拍子、狸ばやしのおもしろさ。 |
| 「狸まつり勧進帳」 |
| 昭和三十五年十二月、作詞富田狸通、作曲稀音家六悠美師匠(本著発刊記念に演奏発表会予定) |
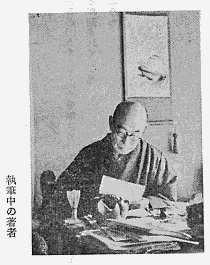 庭は月夜に映えわたリ映えわたリ露もしとゞの七曲(ななまがり)なびく尾花に招かれて、折しも聞ゆる火の元の要心さっしゃれませの拍子木を、打ち打ち、落葉音立てて社を抜け出で渓に沿い、行けば中天月冴えてすすきの丘にぞ着きにけり「斯様に申すものは伊予の久谷久万山(くたにくまやま)に奥住う八百八狸の総師隠神刑部(いぬがみきょうぷ)狸にて候、今宵の狸まつりにことよせてもろもろ獣の一族が狸に化けて入りこむ由、わなの関所をしつらえて一々詮議仕る、方々左様心得侯え」はや修験者に身をかりて月に浮かれて芝の道.徳利ぶらぶら提灯で狸たぬきの伴ぞろい、わなの近くに現はるる「それやるまいぞ化かされな勧進帳のあるまでは」「仲々なんと」従う金平、喜左衛門、小女郎、お袖もありゃありゃら、狸寝入りも間に合はず尻尾を巻いて笠隠れ、とんほ返りをニツ三ツ、ここが狸のお家芸、八畳敷に座を広げ、つけぬ狸の通帳、勧進帳に見せかけて股にはさんで大音声、風にすすきの添う如くうねりうねりと綱渡り、うそ八百に読みあげて取らぬ狸の皮算用、ぽんと叩いた太鼓腹、度胸のほどぞ
あやふけれ「天晴れ明答善哉善哉」狸の好む油あげ、小豆めしにも色そえて、もろもろ盛りし式台に、こわ嬉れしやと立つ拍子、うっかり出した大尻尾、すわや、しく尻大あわて一期の浮沈ここなりと力まかせに打ちまくる世は泰平のありがたや、ぽんぽこぽんぽこ腹つゞみ分福茶釜に禿げ狸、淡路の芝に佐渡団三(さどだんざ)、八万八千八百の大狸に豆狸よろこびとげて打ちつれて、まつりの座にこそ直りけり、まつりの座にこそ直りけり。 庭は月夜に映えわたリ映えわたリ露もしとゞの七曲(ななまがり)なびく尾花に招かれて、折しも聞ゆる火の元の要心さっしゃれませの拍子木を、打ち打ち、落葉音立てて社を抜け出で渓に沿い、行けば中天月冴えてすすきの丘にぞ着きにけり「斯様に申すものは伊予の久谷久万山(くたにくまやま)に奥住う八百八狸の総師隠神刑部(いぬがみきょうぷ)狸にて候、今宵の狸まつりにことよせてもろもろ獣の一族が狸に化けて入りこむ由、わなの関所をしつらえて一々詮議仕る、方々左様心得侯え」はや修験者に身をかりて月に浮かれて芝の道.徳利ぶらぶら提灯で狸たぬきの伴ぞろい、わなの近くに現はるる「それやるまいぞ化かされな勧進帳のあるまでは」「仲々なんと」従う金平、喜左衛門、小女郎、お袖もありゃありゃら、狸寝入りも間に合はず尻尾を巻いて笠隠れ、とんほ返りをニツ三ツ、ここが狸のお家芸、八畳敷に座を広げ、つけぬ狸の通帳、勧進帳に見せかけて股にはさんで大音声、風にすすきの添う如くうねりうねりと綱渡り、うそ八百に読みあげて取らぬ狸の皮算用、ぽんと叩いた太鼓腹、度胸のほどぞ
あやふけれ「天晴れ明答善哉善哉」狸の好む油あげ、小豆めしにも色そえて、もろもろ盛りし式台に、こわ嬉れしやと立つ拍子、うっかり出した大尻尾、すわや、しく尻大あわて一期の浮沈ここなりと力まかせに打ちまくる世は泰平のありがたや、ぽんぽこぽんぽこ腹つゞみ分福茶釜に禿げ狸、淡路の芝に佐渡団三(さどだんざ)、八万八千八百の大狸に豆狸よろこびとげて打ちつれて、まつりの座にこそ直りけり、まつりの座にこそ直りけり。 |
| 〇 童謡及び民謡 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
童話では「証城寺の狸ばやし」が一番よく唄われているが、カチカチ山や分福茶釜、それに各地では、その土地の狸ぱなしを主材して理に関する童謡は次から次へと作詞されている。
厳谷小波作詞、原秀夫作曲の童謡「文福茶釜」七節のうち
| 一、 |
|
|
ブンブクブンブク音がする |
|
|
|
夜なかに何だか音がする |
|
|
|
屑屋もむくむく起き出して |
|
|
|
のぞいて見たら驚いた |
|
|
| 二、 |
|
|
見れば狸にちがいない |
|
|
|
さては化けたな、こいつめと |
|
|
|
うとうとしたらこれ待った |
|
|
|
私しゃわるさはいたしません |
|
|
| 三、 |
|
|
かわりにいろんな芸をして |
|
|
|
お目にかけますこの通り |
|
|
|
たたく尾太鼓腹つづみ |
|
|
|
屑屋も感心するばかり |
|
|
| 四、 |
|
|
今も名高い茂林寺の |
|
|
|
文福茶釜のお話は |
|
|
|
誰も知らないものはない |
|
|
|
誰も知らないものはない |
|
|
民謡も土地によって数限りなく唄われている。
(松山地方)
雨の降らんのに傘さして 毘沙門(狸の名)狸にだまされた
(高知地方)
狸さん狸さん火を一つ貸せんせ この山越えて、あの山越えて 火はここに こっちこっち
(徳島地方)
若い衆音頭出せ、与一(狸の名)が踊る、 今宵も与一が出て踊る
(高松地方)
今ないたん誰かいの 浄願寺の禿狸 お飾り三ッで黙あまった
(開東地方)
ゆうべ見た大きな夢を、何を見た何を見た 富士のお山に、有馬の火の見に、
布袋のおなかに、とんぼの目玉に、 狸の金玉八畳じき、ちがいないぞ、そうだ。
狸娘の十二三もはやとうから、もはやとうから、 分福茶釜に毛がはえた チョイメチョイメノチョイ |
| 〇 和歌
○ 狂歌 〇 連歌
○ 俳句 ○ 川柳
○ 能狂言 ○ 長唄
〇 童謡及び民謡 |
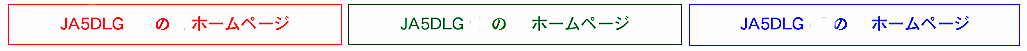
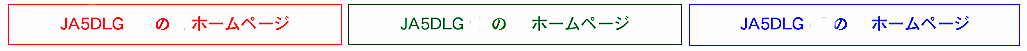
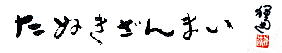 富田 狸通 〇
和歌 ○ 狂歌
〇 連歌 ○ 俳句
○ 川柳 ○ 能狂言
○ 長唄 〇 童謡及び民謡
富田 狸通 〇
和歌 ○ 狂歌
〇 連歌 ○ 俳句
○ 川柳 ○ 能狂言
○ 長唄 〇 童謡及び民謡

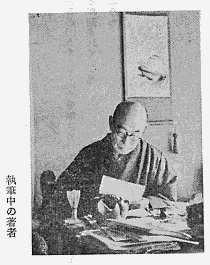 庭は月夜に映えわたリ映えわたリ露もしとゞの七曲(ななまがり)なびく尾花に招かれて、折しも聞ゆる火の元の要心さっしゃれませの拍子木を、打ち打ち、落葉音立てて社を抜け出で渓に沿い、行けば中天月冴えてすすきの丘にぞ着きにけり「斯様に申すものは伊予の久谷久万山(くたにくまやま)に奥住う八百八狸の総師隠神刑部(いぬがみきょうぷ)狸にて候、今宵の狸まつりにことよせてもろもろ獣の一族が狸に化けて入りこむ由、わなの関所をしつらえて一々詮議仕る、方々左様心得侯え」はや修験者に身をかりて月に浮かれて芝の道.徳利ぶらぶら提灯で狸たぬきの伴ぞろい、わなの近くに現はるる「それやるまいぞ化かされな勧進帳のあるまでは」「仲々なんと」従う金平、喜左衛門、小女郎、お袖もありゃありゃら、狸寝入りも間に合はず尻尾を巻いて笠隠れ、とんほ返りをニツ三ツ、ここが狸のお家芸、八畳敷に座を広げ、つけぬ狸の通帳、勧進帳に見せかけて股にはさんで大音声、風にすすきの添う如くうねりうねりと綱渡り、うそ八百に読みあげて取らぬ狸の皮算用、ぽんと叩いた太鼓腹、度胸のほどぞ
あやふけれ「天晴れ明答善哉善哉」狸の好む油あげ、小豆めしにも色そえて、もろもろ盛りし式台に、こわ嬉れしやと立つ拍子、うっかり出した大尻尾、すわや、しく尻大あわて一期の浮沈ここなりと力まかせに打ちまくる世は泰平のありがたや、ぽんぽこぽんぽこ腹つゞみ分福茶釜に禿げ狸、淡路の芝に佐渡団三(さどだんざ)、八万八千八百の大狸に豆狸よろこびとげて打ちつれて、まつりの座にこそ直りけり、まつりの座にこそ直りけり。
庭は月夜に映えわたリ映えわたリ露もしとゞの七曲(ななまがり)なびく尾花に招かれて、折しも聞ゆる火の元の要心さっしゃれませの拍子木を、打ち打ち、落葉音立てて社を抜け出で渓に沿い、行けば中天月冴えてすすきの丘にぞ着きにけり「斯様に申すものは伊予の久谷久万山(くたにくまやま)に奥住う八百八狸の総師隠神刑部(いぬがみきょうぷ)狸にて候、今宵の狸まつりにことよせてもろもろ獣の一族が狸に化けて入りこむ由、わなの関所をしつらえて一々詮議仕る、方々左様心得侯え」はや修験者に身をかりて月に浮かれて芝の道.徳利ぶらぶら提灯で狸たぬきの伴ぞろい、わなの近くに現はるる「それやるまいぞ化かされな勧進帳のあるまでは」「仲々なんと」従う金平、喜左衛門、小女郎、お袖もありゃありゃら、狸寝入りも間に合はず尻尾を巻いて笠隠れ、とんほ返りをニツ三ツ、ここが狸のお家芸、八畳敷に座を広げ、つけぬ狸の通帳、勧進帳に見せかけて股にはさんで大音声、風にすすきの添う如くうねりうねりと綱渡り、うそ八百に読みあげて取らぬ狸の皮算用、ぽんと叩いた太鼓腹、度胸のほどぞ
あやふけれ「天晴れ明答善哉善哉」狸の好む油あげ、小豆めしにも色そえて、もろもろ盛りし式台に、こわ嬉れしやと立つ拍子、うっかり出した大尻尾、すわや、しく尻大あわて一期の浮沈ここなりと力まかせに打ちまくる世は泰平のありがたや、ぽんぽこぽんぽこ腹つゞみ分福茶釜に禿げ狸、淡路の芝に佐渡団三(さどだんざ)、八万八千八百の大狸に豆狸よろこびとげて打ちつれて、まつりの座にこそ直りけり、まつりの座にこそ直りけり。