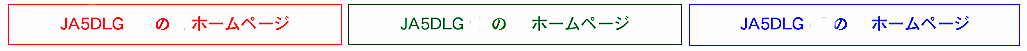 |
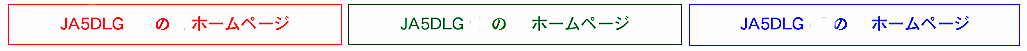 |
| 正岡子規の句 | ||||
| 牛行くや 毘沙門阪の 秋の暮 ふゆ枯れや 鏡にうつる 雲の影 色里や 十歩はなれて 秋のかぜ 馬しかる 新酒の酔や 頬冠 籾ほすや にわとり遊ふ 門の内 春や昔 十五万石の 城下哉 春や昔 古白といへる 男あり 我死なで 汝生きもせで 秋の風 見あぐれば 塔の高さよ 秋の空 天狗泣き 天狗笑うや 秋の風 松山や 秋より高き 天守閣 桔梗いけて しばらく仮の 書斎哉 柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺 行く我に とどまる汝に 秋二つ 糸瓜咲て 痰のつまりし 仏かな 痰一斗 糸瓜の水も 間にあわず をとゝひの へちまの水も 取らざりき 鶏頭の 十四、五本も ありぬべし 栗の穂に鶏飼ふや一構 国なまり 故郷千里の 風かをる 城山の 浮かみ上るや 青嵐 卯の花を めがけてきたか 時鳥 卯の花の 散るまで鳴くか 子規 名月や 伊予の松山 一万戸 賽銭の ひゞきに落ちる 椿かな 人もなし 杉谷町の 藪の秋 若鮎の 二手になりて 上りけり 海晴れて 小富士に秋の 日くれたり 十月の 海ハ凪いだり 蜜柑船 菎蒻につつじの名あれ太山寺 君を送り 思ふことあり 蚊帳に泣く 花木槿 家ある限り 機の音 興居嶋へ 魚船いそぐ 吹雪哉 初汐や 松に浪こす 四十島 永き日や 菜種つたひの 七曲り 菜の花や 道者よびあふ 七曲り 秋の山 松欝として 常信寺 新立や 橋の下より 今日の月 送られて 一人行くなり 秋の風 十一人 一人になりて 秋の暮 山本や 寺ハ黄檗 杉ハ秋 画をかきし 僧今あらず 寺の秋 新年や 鶯啼いて ほとゝぎす |
閑古鳥 竹のお茶屋に 人もなし 東野の 紅葉ちりこむ 藁火哉 山門に 蛍にげこむ しまり哉 岩堰の 岩にけし飛ぶ 霰哉 湯の山や 炭売りかへる 宵月夜 薫風や 大文字を吹く 神の杜 真宗の 伽藍いかめし 稲の花 秋風や 高井のていれぎ 三津の鯛 ていれぎの 下葉浅黄に 秋の風 永き日や 衛門三郎 浄瑠理(璃)寺 旅人の うた登り行く 若葉かな 身の上や 御鬮をひけば 秋の風 南無大師 石手の寺よ 稲の花 火や鉦や 遠里小野の 虫送 巡礼の 夢を冷やすや 松の露 茸狩や 浅き山々 女連れ 霜月の 空也は骨に 生きにける 寺清水 西瓜も見えす 秋老いぬ 我見しより 久しきひょんの 茂哉 新年や 鶯啼いて ほととぎす 新場所や 紙つきやめば なく水鶏 朝寒や たのもとひゞく 内玄関 名月や寺の二階の瓦頭口 僧や俗や 梅活けて発句 十五人 十一人 一人になりて 秋の暮 せわしなや 桔梗に来り 菊に去る 雪降りや 棟の白猫 声はかり 漱石が来て 虚子が来て 大晦日 風呂吹を 喰ひに浮世へ 百年目 冬さひぬ 蔵沢の竹 明月の書 碌堂と いひける秋の 男かな 鶯や 主税今年 年十七 栗の穂の こゝを叩くな この墓を 母様に 見よとて晴れし ふじの雪 節季候の 札の辻にて 分れけり 社壇百級 秋の空へと 登る人 のどかさや 少しくねりし 松縄手 萱町や 裏へまわれば 青簾 踏みならす 橘橋や 風薫る 三津口を 又一人行く 袷哉 梟や 聞耳立つる 三千騎 春風や 遍路飯くふ 仁王門 |
めずらしや梅の蕾に初桜 うそのような十六日桜咲きにけり 松に菊 古きはものゝ なつかしき 百号に満ちけり菊はさきにけり 内川や 外川かけて 夕しぐれ 鼓鳴る 能楽堂の 若葉かな 荒れにけり 茅針まじりの 市の坪 御所柿に 小栗祭の 用意かな うぶすなに 幟立てたり 稲の花 朝夕に 神きこしめす 田歌かな じゅずだまや 昔通ひし 叔父が家 行く秋や 手を引きあひし 松二木 花木槿(むくげ)家ある限り 機(はた)の音 汐風や痩せて花なき木槿垣 西山に 桜一木の あるじ哉 故郷は いとこの多し 桃の花 朝寒や ひとり墓前に うづくまる 桜散って 山吹咲きぬ 御法事 ものゝふの 河豚(ふぐ)にくはるゝ 悲しさよ 花木槿 雲林先生 恙なきや 酒ありめしあり十有一人秋の暮 風流のはや髭に出し去年の 名月や 伊予の松山 一万戸 籾(もみ)ほすや 鶏遊ぶ 門のうち 鳩麦や昔通ひし叔父が家 狸死に狐留守なり秋の風 松が根になまめき立てる芙蓉哉 ハ方に風の道ある榎実哉 春や昔 十五万石の 城下哉 ふらんすに夏痩なんどなかるべし おもしろや紙衣も著(き)ずに済む世なり 志保ひ潟(しほひがた) 隣の国へ つづきけり 涼しさや 馬も海向く 粟井坂 涼しさや 馬も海向く 淡井坂 夏川を二つ渡りて田神山 夕栄の 五色が浜を かすみけり 五月雨や 漁婦(たた)ぬれてゆく かゝえ帯 門さきに うつむきあふや 百合の花 追いつめた 鶺鴒見えず 渓の景 追いつめた 鶺鴒見えず 渓の景 案山子もの言はば猶さびしいぞ秋のくれ 西行の子とは思えず鳥おどし |