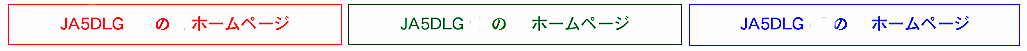 |
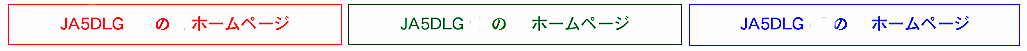 |
| 特別陳列 修理完成記念 国宝・一遍聖絵 |
| 展示予定作品 (●は国宝、◎は重文、○重美) ●一遍聖絵 十二巻 京都・歓喜光寺、神奈川、清浄光寺蔵 ●一遍聖絵巻第七 一巻 東京国立博物館蔵 ◎木造一遍上人立像 一躯 京都・長楽寺蔵 |
| 一遍聖絵は、鎌倉時代に時宗の祖となった念仏聖・一遍上人(1239〜89)の生涯を描いた絵巻で、十二巻からなっています。この絵巻は、奥書や最終段の詞書から、上人の異母弟といわれる聖戒が、ともに念仏修行した上人の恩に酬いるために制作を発起したもので、自ら詞書を起草、絵を法眼円伊が描いて、上人の没後十年にあたる正安元年(1299)に完成したことが知られています。 絵を描いた円伊は、これが唯一の作品で、人物像については諸説ありますが、はっきりしたことはわかっていません。けれども、写実性を帯びた風景表現や、巧みな群像表現に、やまと絵の伝統を感じさせるとともに、新しく伝来した水墨画の筆法を融合させた新しい様式を示し、制作年代が明らかなことも含めて美術史の基準作品として重要な位置を占めています。 一遍上人はなくなるとき「わが化導は一期ばかりぞ」と言ってすべての書物を焼き捨て、また屍を「野に捨てて獣に施すべし」と言い残しているほど、徹底した捨聖の姿勢を貫きました。そのために著作などは残されておらず、『一遍聖絵』がその生涯や思想、詠歌を知る基本的な資料となっています。 この絵巻には、念仏勧進ために諸国を旅した上人の行跡が、各地の名所の風景とともに描き出され、またそれぞれの場の現実感を高めるために、人々の生活、風俗が豊富に描きこまれています。この点から、『一遍聖絵』は、絵画としてのすばらしさだけでなく、時代を雄弁に語るヴィジュアル資料として歴史、民俗、建築などさまざまな分野の関心も集めています。「福岡の市」をはじめとして、中学校や高校の歴史教科書で、この絵巻からとられた場面がしばしば挿図として用いられているのは、こうした理由からです。 この作品は、絵巻としてはきわめて珍しい絹本に描かれていることもあって、経年損傷がみられていましたが、平成七年から六年間かけて保存修理が施され、従来巻第三、巻第六に見られていた順序の乱れの復原も含めて昨春完成、面目を一新しました。修理期間中は展示の機会も少なく、公開の要望に十分応えることができませんでした。そこで、修理完成後一年を経て、状態も安定したこの機会に、全巻を一堂に展示することとしました。この作品は普段巻第一から第六の前半が奈良国立博物館に、また巻第七から第十二の後半が京都国立博物館に保管されており、今回全体を通してみることができる絶好の機会でもあります。 今回の展示では、江戸時代に寺外に逸失し、現在東京国立博物館に所蔵されている巻第七の絵(国宝)も特別に加えられ、また時宗七条道場に伝存した木造一遍上人像(重要文化財)も所蔵者である長楽寺のご好意により展示されます。これらとあわせて、裏打ちを取替える際の、絹の裏からの観察によって明らかになった図様の改変など、修理に際して得られた新知見に関する資料も展示します。 この特別陳列陳列によって、あらためて『一遍聖絵』のもつ価値や魅力を、知っていただければと思っています。 今回の特別陳列で展示される国宝『一遍聖絵』巻十二の巻末には、廟堂内に安置される一遍上人の像が描かれています。同絵巻は上人入寂のわずか十年後に成立していますから、そのころには同上人の肖像彫刻が製作されていたことがうかがえます。残念ながら絵巻に描かれた像は現存しませんが、一遍上人像は、その後いくつも製作されました。なかでも本像は、近年おこなわれた修理の際に、像内から応永27年(1420)に仏師康秀が製作した旨の墨書が発見され、現存する一遍上人の肖像彫刻としては、西日本でもっとも古いものであることが確認されました(ちなみに最古の像は神奈川の無量光寺にあります)。やや前かがみなって胸前で合掌して遊行する姿や、遊行にあけくれたことを示すようなこけた頬などの特徴は『一遍聖絵』に描かれる肖像と共通しています。時宗寺院では代々の遊行上人の肖像彫刻が製作されましたが、遊行する姿であらわされる彫像は一遍上人像だけで、これが同上人に特有の姿であるということが強く意識されていたことがうかがわれます。 なお、当像は現在長楽寺に所蔵されていますが、かつては七条道場金光寺に伝えられてきました。このあたりの詳しい事情は、一昨年に当館で開催した『長楽寺の名宝』展の図録(当館ミュージアムショップ・長楽寺で販売中)をご覧ください。 |
| さいめい‐てんのう【斉明天皇】 7世紀中頃の天皇。皇極天皇の重祚チヨウソ。孝徳天皇の没後、飛鳥の板蓋宮イタブキノミヤで即位。翌年飛鳥の岡本宮に移る。百済救援のため筑紫の朝倉宮に移り、その地に没す。(在位655〜661)(594〜661) |
| くうかい【空海】 平安初期の僧。わが国真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果ケイカに学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院シユゲイシユチインを設立。詩文に長じ、また三筆の一。著「三教指帰」 「性霊集」「文鏡秘府論」「十住心論」「篆隷万象名義」など。諡号シゴウは弘法大師。(774〜835) |
| てんじ‐てんのう【天智天皇】 ヂ ワウ 7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別アメミコトヒラカスワケ、また葛城カズラキ・中大兄ナカノオオエ。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671) |
| しょうおう【正応】シヤウ 鎌倉時代後期、伏見天皇朝の年号。(1288.4.28〜1293.8. 5) |