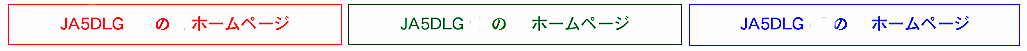 |
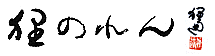 富田 狸通 松山名物
富田 狸通 松山名物五色ぞうめん 緋のカブラ ていれぎ タルト もぶりずし 三津の朝市 銘菓タルト記 坊っちゃん団子考 求肥 牛皮
音に名高き五色ぞうめん
音に名高き五色ぞうめん
古い歴史をもつ道後温泉振鷺閣(しんろかく)から打ち出す刻太鼓(ときだいこ)の音に明け暮れる松山は、自然の環境に恵まれて、詩のくに、歌どころといわれている静かな明るい城下町である。
古い民謡の伊予節は、伝統の俳句とともに、松山在任中の思い出と荷物にならぬ伊予路のみやげとして県外人に親しまれているが、小節まわしがむずかしいので、やっとうたえるようになるころにはソレ転勤というわけで、一名“テンキン節“ の名がある。が、この伊予節の代表的な歌詞に「伊予の松山名物名所三津の朝市道後の湯 音に名高き五色素麺 十六日の初桜 吉田さし桃小杜若(こかきつばた) 高いの里のていれぎや 紫井戸や片目鮒(ぷな) うすずみ桜や緋の蕪(ひかぶら) チョイト伊予絣 と天明時代(約百八十年前)からの文句で、伊予名物の味覚が歌いこまれてある。
このうち、そうめんと緋のカブラは、松山藩主につながる因縁の名物である。三代目城主久松定行(当時は松平姓)が、桑名から転封したのは寛永十二年(一八〇〇)で、そのとき随従してきた御用商人の長門屋市左衛門が桑名そうめんの製法を伝え、初め松山ぞうめん、伊予ぞうめんの名で名物となり、のち享保七年(一七二二)に美麗な五色に染め分けたそうめんをつくり、藩主はこれを参勤交代のつど将軍家への自慢のみやげものとして献上するようになった。以来、伊予の「五色ぞうめん」の名が江戸で評判になった。
そのころ、近松門左衛門も、友人に「五色素麺是亦給ひ候、賞翫より先、食膳の美玉冬日の遊糸共可候やらん」と礼状をよこしたということが、長門屋十五代目の現当主森川君の自慢話になっている。ゆでても色が流れぬ上質のそうめんで、夏は風鈴の下で、唐糸(からいと)のように優美な五色のそうめんを、ガラス器の中からすくいあげて水を切り、かけつゆですする風味は、伊予路古来の風習を伝えるもの。また冬の料理法として、市内の高級料亭では吸いもの、にゅうめん、揚げめんなどに使用して、観光客の目と舌を喜ばせている。一箱五把入りの六十円から千円箱までの数種類ある。
緋のカブラ
緋のカブラ
緋のカブラについては、明治三十年一月の正岡子規居士の句に「根岸の草庵にて故郷の緋蕪をおくられて」と前置きして「緋の蕪の三河島菜に誇って曰く」というのがある。寛永四年(一六二七)松山藩二代目の城主として移封してきた蒲生忠知(一代で断絶)が、前任領の近江日野からカブラの原種を取り寄せて栽培させたもの。そこで、日野カブラと書くのが正しいという時代もあったが、ともかく葉の繊維やカプラの表面が赤くて、ナマスやつけものにするときダイダイ酢をかけると、見るうちにカブラのしんまで鮮紅色になるので「緋のガブラ」の名がつけられた。
このカブラは、近江地方でも日振八幡社周辺の土地のが良質で、松山でも日招八幡社の太鼓の音が聞こえる範囲の土地でないと、赤色のものができぬという言い伝えがあって、いつまでも、このことが農家の 間に信じられているのも、日野、日振、日招と“日“ の字に縁起を持つおもしろい話である。
いうなれば、日野から移入したカプラで“日“ の字のつく限られた土地にしか栽培できぬという不思議 と、藩主が移入したありがたい縁起が幸いして、珍味となったのかもしれぬが、酢づけにした真っ赤なつけものが、伊予特産の「緋のカブラづけ」の名で珍重されている。酒のサカナや茶うけにも好適で、値段も一オケ三百円と五百円の手ごろなものであるが、時期的に生産が途切れるのは惜しい。
ていれぎ
ていれぎ
子規の句に「秋風や高井のていれぎ三津の鯛」とよまれている「ていれぎ」は、昔から、市の郊外にある久米の高井部落を南北に流れる小川にしかはえぬ水辺植物である。ていれぎといえば高井、高井といえぱていれぎの里という。その小川はいつも清澄に流れていて、ていれぎはけっして濁り水にははえない植物で、セリによく似ている。清潔でピリッとした香辛味が食通の嗜好に合って、刺し身のケンや吸い物に喜ばれる珍味である。ちかごろは酒カスに詰めた「ていれぎづけ」も市販されている。
以上が、古い伊予節の中に歌いこまれた、郷土独特の伝統をもつ味覚である。
タルト
タルト
また、松山藩は、早くから裏千家の茶道が盛んで、古来、菓子類も上等品が多かったのであるが、アンをカステラで巻いた「タルト」も、藩主の久松定行が長崎探題のとき、その製法を移入したという因縁の菓子で、当時は珍しい洋菓子であった。それがある時代の倹約令にひっかかって製造ご法度となり、和菓子に押されて忘れかけていたのを、大正中期ごろから製法を改良して復活し、今日の観光菓子「松山のタルト」となった。そして、市内いたるところに製造元、元祖の看板が見られるようになり、値段も一本百円から二百円と、ピンからキリまであるから、ピンのほうで賞味しないと、ほんとうの松山の味が出ないのである。
夏目漱石石の小説「坊っちゃん」の中に「おれの這入った団子屋は遊廓の入口であって大変うまいと云ふ評判だから、温泉に行った帰りがけに一寸食って見た・・・翌日一時間目の教室へ這入ると、団子二皿七銭と書いてある・・・二時間目にも屹度何かあると思ふと、遊廓の団子旨い旨いと書いてある」の一節がある。当時の団子は、湯ざらし団子といって、モチをちぎってアンにまぶしてサラ盛りにし、ハシで食うアンころモチであった。大正の中期にこねモチの三色でクシ刺しにした現在の「坊っちゃん団子」が、タルトのの片棒をかついで、よく売れている。
珍品・もぶりずし
珍品・もぶりずし
ところで.昔から松山の珍しい料理に「もぶりずし」ーー俗に“松山ずし“というのがある。このすしに用いる具の材料は、ニンジン、ゴボウ、レンコン、シイタケ、サヤマメなど、季節によっては、タケノコやフキであしらって色どりをつけてまぶすチラシずしである。その上に金糸卵に、焼きアナゴや酢づけの生魚と紅ショウガをのせ、木の芽やタデを配して季節の味を持たせてある。
食いしんぼうの子規は、この松山ずしが大の好物で、郷土料理の誇りにしていたことは有名な語り草になっている。
明治二十九年の子規の句に「われ愛すわが予州松山の鮓」の句がある。明治二十五年の夏、まだ子規が大学予備門の学生で、暑中休暇で帰省中、漱石が初めて子規をたずねて松山に来たとき、彼の母堂は、遠来の漱石に自慢の松山ずしをつけて食べさせたところ、漱石はおおいに喜んで、その味が忘れられず、同二十八年の春、松山中学校の教師として赴任したときも、第一番に松山のもぶりずしを所望したという。
三津浜の魚の朝市
三津浜の魚の朝市
さて、道後温泉をたずね、松山を観光する客があこがれる味覚は、伊予柑などのくだものは別として、なんといっても瀬戸内の小魚料理であろう。紺碧に輝く明るい国立公園瀬戸内海の波の色に新鮮な銀鱗の味覚を連想するのは当然でもある。このピチピチはねる魚は毎朝三津浜の魚市で集散される。この朝市場の古くて珍しい円輪型の建て物は先年惜しくも改築されたが、朝市の方法と形式の情景は元和二年(一 六一六)の昔から連綿として今日までその伝統を守りつづけて、伊予節にもうたわれている郷愁深い風物詩である。子規の友人河東碧梧桐は、この朝市の活気を「生きのいきさかな一度躍って尾とばん刃」と詠んでいる。( 「週刊読売」昭和四〇、七、四)
銘菓「タルト」の記
銘菓「タルト」の記
道後温泉、国宝松山城の名声と共に知られている松山の銘菓「タルト」は、元来フランス語の「タルトレット TARTLETTE」といふ菓子の名から由来したものであります。
この「タルトレット」は、今から約三百年前の正保元年、徳川家光の時代、松山藩三代目の領主で久松家初代の松平隠岐守定行が探題として長崎に赴任当時、オランダ人の手を経てカステーラ、ボーロ、金平糖、アルヘイト等と共に輸入された蛮製菓子の一種で、其の製法が松山に伝えられたのです。
本来の「タルトレット」は材料・香料等の関係でそのままでは吾国の嗜好に合いませんので、自然製造も途絶え、折から当時西洋菓子製造禁止の御布令もありましたが、松山では藩主久松家と由緒ある菓子だったので、ひそかに其の製法を伝えて、文政の頃いろいろと考案し改良の結果出来上ったものに「タルト」と名付て復興し、以来明治年間から盛んに売出され、一躍松山の名産として自慢の出来る今日の銘菓「タルト」となったのであります。
この「タルト」は、舌ざわりのよさと風雅で風味の上品さから、泉都松山を訪れる方々には温泉情緒の伴侶として最適のおみやげであります。
金皷堂富田狸通識
(伊予道後湯之町御菓子司沼田栄屋宣伝文、昭和二六)
「坊っちゃん団子」考
「坊っちゃん団子」考
タルトに次いでよく売れる郷土の菓子に「坊っちゃん団子」があり。最近の漱石文学の流行とともに観光松山を文化的に宣伝している。もちろん小説「坊っちゃん」の中に出てくる「遊廓の団子旨い旨い」という、湯ざらしだんご(あんころモチ)から考案創始されたものであることはいうまでもない。
ところで、ことしの春、この坊っちゃん団子の創始者が三十年目に会った友人の三浦一良君であることを知ったので、以下同君から聞いたままを記して、坊っちゃん団子の来歴を残しておきたいと思う。
三浦君の家は、先々代の利八という人が屋号を三浦屋といって城北の道後町(今の高砂町)で製薬業を営んでいたが、明治二十年ごろ、道後松ヶ枝町(今の上人町)の入口右側へ転居して来て、古い道後名物の湯ざらしだんごも売っていた。
その後三浦屋は二転して湯之町本通りの裏側町で営業していたが、大正七、八年のころ、A新聞の記者が夏目漱石に関する松山の史蹟探訪に来た。当時二十歳だった三浦君は、その記事を読んで、夏目漱石がそんなに偉い大文豪であったのかと、改めて「坊っちゃん」を読み直してみた。そして「・・・おれの這入った団子屋は遊廓の入口にあって、大変うまいと云ふ評判だから、温泉に行った帰りがけに一寸食って見た・・・」の一節を発見し、「坊っちゃん」の団子事件の震源地は祖父の時代の三浦屋であると自らの心にいいきかせて、若い一良君の頭の中に去来したのが、漱石先生ゆかりの「坊っちゃん団子」という名前であった。そして商売人らしい野心もなく、ただ菓子屋本職のお手のものとして趣味半分に考案した原形が現在の串ざし三色だんごであった。
いま市販されている団子のシンは、牛皮で作ってあるからアンのとり合わせの悪い味となっているが、一良君が創始した団子は、シンに道明寺(干飯)を使用し、味のとり合わせに心をくだいて、ひき茶(緑)と卵(黄)とアズキ(茶)の三色アンを考案して黒もじに串ざしたもので、値段は一本二銭であった。そういえば当時の湯ざらしだんごは、一皿五銭であったが、新しい串ざし団子の売り出しには、若い店員に 「坊っちゃん団子」と染めぬいたハッピを着せてジャンジャン宣伝していた三浦屋の風景を思い出したの
である。
gyuuhyi
牛皮
ぎゅうひ‐あめ【求肥飴】ギウ 白玉粉を蒸し、あるいは水とあわせて熱を加え、これに白砂糖と水飴とを加えて練り固めた、柔軟で弾力ある菓子。求肥糖。求肥。牛皮。
三浦君は昭和十年に道後を引き払って別府市に渡り、今もなお彼独創の趣味を生かした民芸竹細工の製作卸し商を営んでいる。
(「愛媛新聞」昭和四○、七、ニニ)
五色ぞうめん 緋のカブラ ていれぎ タルト もぶりずし 三津の朝市 銘菓タルト記 坊っちゃん団子考 求肥 牛皮