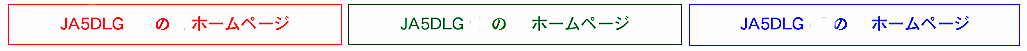 |
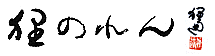 富田 狸通 つきぬ郷愁
富田 狸通 つきぬ郷愁夏目漱石の小説「坊っちゃん」のてんぷら事件の中に、“序でだから一杯食って行こうと思って上り込 んだ、見ると看板ほどでもない・・・・金がないのか滅法きたない。畳は色が変っておまけに砂でざらざらして居る。壁は煤で真黒だ。天井はランプの油烟でくすぼってるのみか、低くって思わず首を縮める位だ“ とあるが、これは明治二十八年の松山大街道の店のことである。
モデル考によると、この店は今グランド映画劇場の前あたりにあった亀屋というしにせの古いうどん屋 であった。この時の実演者は弘中又一という英語の教師で、しっぽくうどんを四杯平げたのでしっぽく先生の仇名を付けられ、生徒が作った数え歌の中でも”一ツ弘中しっぽくさん”と唄いこまれている。このしっぽくさんは、小説では漱石が好きだった“てんそば“ に書きかえたのだということになっている。
この亀屋は、うどん亀屋の愛称で戦前までは松山第 一の麺類の老舗であって、地方から松山の城下町を訪れるものは、このうどん亀屋ののれんをくぐらんことには城下町に出てきた意味がないというくらい名物の店であった。そして当時一杯六銭のしっぽくが一 番最高だったという。
そんなことはどうでもよいが、そのころの松山商店街の照明灯が石油ランプであったことはまちがいな い。松山でランプが用いられたのは明治三年ごろで、二番町のいま友愛会館になっている(元料亭梅廼家) のところに白川親応という旧藩士が住んでいて、神戸から石油と洋灯を取り寄せたのが最初である。
そのころの一般の人家は、種子油を灯したアンドンであった。石油に次いでガスが灯されたのはずっとのちのことで、明治二十年ごろ大街道のところどころに瓦斯灯と称するものが架設されたということが 「松山文化史」に書いてあるが、これは石油のガス灯ではないかと思う。
松山地方に電気灯を企図したのは明治二十五年であったが、需要が少なかったのでものにならず、それから十年を経た明治三十五年の秋、初めて電気がついたのである。電気灯は風が吹いても消えぬ、ガスも出ん、電球は割れてもすぐ消えるから火事にならん、マッチもいらぬ、また、ものの影がうつらぬから部屋中が明るいなどと、いま考えるとウソのような評判で、電気灯を見るために田舎から弁当がけで城下町へ出かけてくるものが多かったということである。そして電灯の取付けを申込む時には「五燭光とはランプの何分芯のことですかやナモシ」と質問されて面喰ったという話も残っている。
私の義家の本家は湯之町で古くから小間物問屋を営んでいたが、店の照明灯の一部にガスを用いていたことを覚えている。裏の土蔵の横に直経一メートル、高さ二メートルほどのトタンのタンクがあって、それから長いゴム管を引き出して点灯していた。タンクの中には白い砂のようなものが残っていたからカーバイトだったろうと思う。
昭和の初めごろ、道後公園の南堀端に天心園という青年道場があった。この道場は一代の先覚者であった森恒太郎翁(盲天外)が地元の青年有志を呼合して思想教育を試みた所で園内にはいろいろの設備があったが、その中の一つに燃料用の天然ガス発生装置があった。それは広い園の片隅に、毎日の残飯残菜を投げ入れて密閉し、メタンガスを発生させる方法で、学校の化学の時間に教わってはいたが実験を見るのは初めてだったので、さすがはソツのない森翁の実践指導ぶりに感激した。
石油ランプについて我々年輩のものが忘れることのできぬことはホヤに対する抵抗である。小学校時代、夕暮どきになると必ずホヤの掃除をさせられたものである。ホヤの中へ古布や反古紙を丸めて煤をとり、ある時は水で洗い、あやまってホヤを割って叱られたりしたこともたびたびであった。
明治の末期にできた松山市江戸町の黒いガスタンクは、伊予鉄高浜沿線の大きな目標であったことが昨日の如くに思われて、今年の明治百年に当たり、燃料や灯火についてのガスの思い出は、地下にガスパイプが延びるように、追えども追えども尽きぬ郷愁がある。
春愁を動かすネオンが明滅す (「ガスニュース」昭和四二、四)