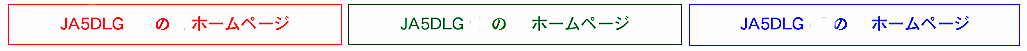 |
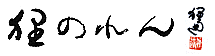 富田 狸通 誇らしき伊予の方言
富田 狸通 誇らしき伊予の方言先般挙行された子規、漱石、極堂三文豪の生誕百年記念祭の諸行事は、郷土の各種文化団体がこぞって協力して文化都市松山を改めて全国に宣伝した世紀の盛事であった。中でも全国松山俳句大会が、今後も年中行事として継続されることは、松山俳壇の水準を高め、俳都の名を誇るものとして喜ばしいことである。
子規の俳句と共に、松山を紹介する漱石の「坊っちゃん」についても私にはいろいろのことが考えられるのである。その中でも、松山のなまり言葉と方言である。「ナモシと菜飯はちがうぞなもし」などと書かれていて、ナモシは全国的に知られているが、今この方言はめったに聞くことが出来ず、その他の方言も共に追々忘れられ、消えて行こうとしている。もちろん標準語で統一しようという教育方針はわかるが、そのために人間までが規格品のようになるようで味気ない思いがする。
方言の中には、その土地々々の時代や人情風俗がしのばれて、郷愁深い情趣は無形の郷土史ともいえる。したがって誰でもがオイソレとすぐ真似のできぬ味わいの深いものがある。大正の中期ごろ、先代の市川猿之肋が、初めて「坊っちゃん」を芝居に上演したとき、例のナモシや伊予弁のセリフのアクセントがむずかしいので、松山人についてその発音を稽古したときのこと、このことは今テレビや映画で人気のある 「おはなはん」の場合でも同じことだろうと思うが、その時に選ばれたのが、今年八十五歳でなお元気さかんな松山出身の洋画家八木彩霞さんであった。八木さんは毎日猿之肋一座の稽古場へ出かけて、熱心に伊予弁の指導をしたが、どんなにうまく真似たようでも、どこかしらアクセントが引っかかって具合が悪い。そのとき猿之肋は「江戸ッ子育ちは生まれ付き頬の筋肉がベランメー口調になっているのだから、まず頬の肉をほぐしてかからねばならん」と注意したという。これは新劇の井上正夫が、生涯伊予弁なまりで苦労したのと同じ話である。
ところで「坊っちゃん」の小説が世に出た当時、すなわち明治四十年ごろ、松山地方から東京へ遊学する学生は「松山中学出身だ」というと「フンあの野蛮な坊っちゃんの学校か」と、田舎ものの張本人扱いにされるので、松山生まれということに抵抗を感じたということである。それでなくとも愛媛県人は、島国根性で小賢しく、器用に利口ぶるくせがあるので「伊よ猿」の名で軽蔑され、肩身のせまい思いをした時代があったから、我々当時の学生も、お隣りの九州男児を羨ましく思ったものである。そんな影響もあってか、松山人はナモシに限らず郷土の方言を使うことを嫌うようになったのかも知れん。
このことは、どこへ行っても堂々と「バッテン」を使って九州男児を威張り、「モーカリマッカ、アキマヘン」というあいさつが大阪商人の土根性を象徴しているのと比べて、現代の松山人は、伊予の方言を意味なく卑屈に考え、自ら松山人の誇りを失い、郷土を忘れようとしているようで残念でならぬ。
明治十六年、子規も始めて上京したとき、周囲から「四国から来た伊予猿」と田舎もの扱いに軽蔑されたが、そのとき子規は「世の人は四国猿とぞ笑うなる。四国の猿の子猿ぞわれは」と歌を詠んで、自ら四国の子猿であると豪語し、威張って友人知己を煙にまいている。この度胸と郷土を誇る自信があってこそ、不治の病床六尺の間に、近代文学の革新に不朽の金字塔を打ち立てたのであろう。
ときあたかも今年は子規、漱石の生誕百年記念に当たり、自ら一匹の伊予猿を称して誇った子規の気概と漱石の「坊っちゃん」によって全国に宣伝された伊予の方言に思いをいたし、伊予人、松山人の自覚と誇りを以て郷土の方言を見なおしたいものである。そして伊予路を訪れる全国の観光客に対しても、一ツやニツ、伝統の正調松山方言を混えて迎えてあげることも金のかからぬ観光サービスとして大いに意義のあることと思う。 (「柿」昭和四十一、十一)