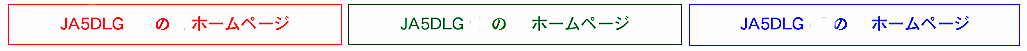 |
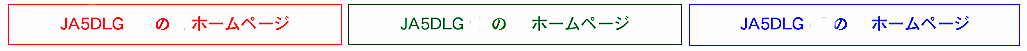 |
|
| アンダーラインで訂正箇所を示す |
| 特別寄稿 山頭火との出会い 高橋 照葉 H18・06・05 20号 昭和十五年八月、夏休みであった。父の弟は本名高橋始、俳号を一洵(いちじゅん)と言う。その叔父が新築した祝いに、父と二人で旅行がてら松山へ行くことになった。宇高連絡船で高松へ、栗林公園、屋島まで見物して夕方松山へ着く。 父と二人だけの旅は、この時だけだったのでよく覚えている。翌日新築祝いの宴が張られる。席に座らせてもらえない私は、玄関で来客の履物整理をしていた。そこへ風の如く、風体のよくない坊さんが網代笠をかむつたまま入って来た。「一洵さんおられるかな」という。えっ、何しに来たのこの坊さん、と思いつつ叔父に告げる。飛んで出た叔父は、下へも置かない風に座敷の正座に据える。新しい畳が汚れそうと、私は思った。玄関で脱いだちびり下駄は、半分に割れたのを無理に縄でしばり、臭うような代物。鼻つまみつつ片隅に置こうとした私を一暼し、恥かしそうな、申し訳なさそうな、切ない瞳を見た一瞬、私も急いで瞳を伏せた。何者、あの乞食坊主は・・・と思ったものの、問い詰める気もない十六才の私と山頭火との出会いであった。座敷でいささか酩酊した坊さんを遠目しつつ、あの深い哀しみをたたえた眸は何を言わんとしていたのだろうか・・・と何となく印象深い思い出として胸深く納めた。 当時、叔父は松山商大の教授で、フランス語と政治学を教えていた。若干四十一歳なのに一風変わった人で、いつも着古した背広に、ズボンはベル ト替わりに縄でしばり、ちびた下駄をはいて、夏休み中全国を講演していた。途中大阪の我が家へおんぼろ風体でこられるのには、困惑した思いもした。今思えば、山頭火を尊重するあまり、同じ風体で世を闊歩していたのかな・・・。フランス語とちび下駄とのバランスがおかしくて、ほんまに大学のせんせいかな?と疑った。 昭和十四年秋、手拭一枚の姿で、山頭火は松山の一洵を訪ねきて、初対面なのに居候、道後の宿賃から小遣いまで与えて、それから一年余り、底抜けの優しさと温かさで晩年の山頭火をつつみこんだ一洵であった。 昭和十五年十月十一日、山頭火五十九歳の生涯をとじる。「層雲」の同人仲間では衝撃的ニュースであったかも知れない。世間一般では、一人の飲んだくれの俳人が人知れず世からコロリ往生して消えたということに過ぎなかったろう。ましてや、俳句がどっちむいているか、凡そ関心のなかった少女の私には何の感慨もなかった。その後叔父も山頭火と同じ五十九歳の若さで昭和三十三年一月忽然逝った。私は父が「始」と絶句して、男泣きに泣いているのを初めて見た。 一洵が逝ったあと、山頭火ブームが起こり、山頭火を俳聖まで押し上げたのは大山澄太氏。が、山頭火の晩年を見送り葬式までした一洵のことはあまり知られていない。 私が俳句に心魅かれ入門したのが、叔父が逝って、二十五年後のことである。その俳句勉強過程で、あの時の坊さんが山頭火と初めてしったのである。あの時のあの人が山頭火!と絶句した時の、驚愕と深い悔恨を今も忘れない。無念と叫んだまま、ますます俳句にのめり込み、どうしても俳句を捨てることの出来ないのは、山頭火をこよなく愛した叔父一洵の血をいささか頂いている故か? その後、山頭火と一洵のことをエッセイで何度か書こうとしていたお陰で、平成十一年埼玉文化ホールで金子兜大先生ともお会いできたし「ぐるつけ」主宰の品川鈴木先生、小豆島で「紫苑」の主宰真砂松韻先生とも親しくして頂けるチャンスがあったのも、山頂火を束の間かいまみた体験のお陰かもと、深く感謝している。でもあの世で一番よろこんでいるのは一洵叔父であろう。 |
| 筆者は高橋一洵の姪(兄の娘)。伊丹市在住 |