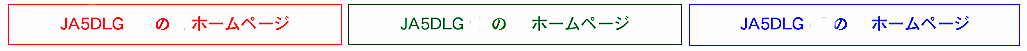 |
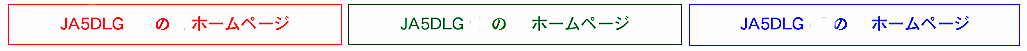 |
|
| 河村みゆきという女(ひと) 藤 岡 照 房 H16・08・20 16号 |
| ○ 咳をしても一人 放哉 ○ その松の木のゆふ風ふきだした 山頭火 山頭火や放哉がお世話になった小豆島の西光寺に二人の句碑が建てられ、四月七日の放哉忌に合わせて除幕と同時に講演の機会を与えられた。 以下はその要旨である。 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 昭和14年10月、河村みゆきは、胸を病む体を第61番札所香園寺に休ませていた。そこへ山頭火が見舞いに訪れて、8日から13日朝まで滞在したのである。山頭火が旅中こんなに長く一か所に留まることは極めて珍Lいことである。 その時の写真が残されている。夫恵雲(えうん)とその両親、友人の木村無相、山頭火とみゆきである。 河村みゆきは、小田原出身で、旧姓は富田。「層雲」(昭11年)に彼女の句がある。 ○ 私にも三十といふ齢が来ることが 更けてゆく星空 このことから、生年は明治40年頃と考えられる。みゆきの俳句歴は、「層雲」(昭7年2月)の「句会たより」の中に ○ それぞれに灯って 暮れてしまった の句が最初である。鎌倉の谷津の会でのことで、この会には井泉水、伊藤雪男、みゆきほか三名が出席している。誰に伴われての出席か?若い女性が不意に出席出来るような会とは思われないのだが、何か井泉水との旧縁といったことが考えられる。 彼女の「古い日記から」には、昭和4年「今日先生にお目にかかったら、僕たちの仲間では形式的な暑中見舞の挨拶なんか要りませんよ、とお仰言った。」とある。「先生」とは非泉水であろうが、この頃からの縁とすれば彼女の随分若い頃なのである。 みゆきは又、求道者のー面をもつ。昭和4・5年頃と推測されるのだが、一灯園(西田天香)へ放哉同様に単身で飛び込み、修行生活を始め、次いで岡山の金光教(高橋正雄)へ移り、ここで恵雲と出会い結婚したようである。 昭和10年にはこんな句文を残している。 是非ない後姿へ笠をお渡 しする。 「又ても四国路に旅立つ夫だった。 是非ない人の子の業を負うて行乞流転する夫に、結局は泣きながらもついて行かねばなにないのが女である。 放哉さんも山頭火さんも妻子を捨てたとか、捨てられてもついて行っても、所詮寂しい女の命・・・・・・」  この後、二人は恵雲の両親と共に香園寺での生活を始めるのだが、みゆきの聡明で誠実な人柄は寺の人々の信頼を集め、その指導力は高く評価されるのだが、まもなく病を得て、香園寺外寮の一室に身を横たえることになる。 この後、二人は恵雲の両親と共に香園寺での生活を始めるのだが、みゆきの聡明で誠実な人柄は寺の人々の信頼を集め、その指導力は高く評価されるのだが、まもなく病を得て、香園寺外寮の一室に身を横たえることになる。この時代、みゆきの俳句は多く、「層雲」誌上に見られ、その巻頭を飾ることもあった。又、吾亦紅、鳳車、白船、緑平ら錚々たる選者たちによる「共選俳句」欄の常連でもあった。 昭和13年にはこんな句を作っている。 ○ 私にもこんなうれしい日が 駅のさくらチラホラ 前書きに「井師御巡拝」。 井泉水が四国遍路にやって来たのである。山頭火が来る丁度一年半前のことであった。 ところが3月26日今治付近の数寺を詣でたあと、井師は、遍路泣かせの横峰寺やみゆきの臥する香園寺を忌避して西条へ行ってしまうたのである。 この間の事情について井師の一文がある。 「ー本山の駅に出ると、そこにも亦、私を待うてゐる人が居た。香園寺のMであった。私は、前々日、札所の順序として、第六十一番、香園寺、第六十二番、 宝寿寺、第六十三番、吉祥 寺といふ風に巡る筈であって、それを略した為に、香園寺に彼を訪ふべきところを訪ひ得なかったのだ。其ことわりの葉書は出しておいたが、それに依うて、私の足どりを考へて、彼も亦、私を追うて来たのだった。さうして、彼は、此日一日は私と行を共にしたいと云ふのだった。」 (「遍路日記」) 桜咲く駅は、本山駅。3月28日のことであった。 (註、Mはみゆき、彼は彼女である。) 井泉水にもみゆきの境遇についての心配があった。この「ことわりの葉書」はみゆきにとってまさに恩情の葉書であったろう。井師との邂逅に胸おどらせる日もあったが、みゆきの病状は更に進むのである。山頭火の住所録には小松町のみゆきの住所の次に、三原市の赤十字療養院が付け加えられてる。そして、この頃から彼女の句には自らの病の句が多くなってゆく。 ○ わが ○ この母のひとりの娘とし 病む髪を続かせることか ○ 一瞬死の怯えを、更に血を、氷のうが脈打つ 大戦最中の昭和17年、みゆきは療養のため実家へ帰ることにした。 ○ 井戸やそのあたりの 雑草や生れた家 その間も、俳句への情熱は衰えていないのである。 ○ 句を拾ひそして熱をしるす 赤鉛筆いっぱん持つ 「層雲」(昭19)新年号に ○ 菊の香や医者へ行く日の 白い足袋はく しかし、この句を最後にみゆきの句は消えてしまうのである。昭和24年5月「層雲」に卦報が載った。 「河村みゆきさん(東京)22年逝去」 明治、大正、昭和にかけてあの時代に、自由律俳句を杖に生きた一人の病がちの女性の記録である。 夫恵雲が贈った法名である。 心月院明蛍禅尼 |