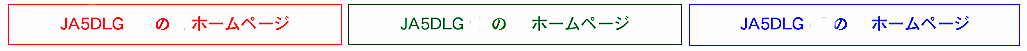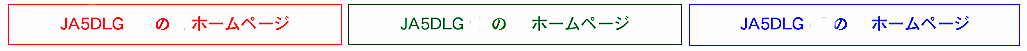| 本ホームページに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権は 「まつやま山頭火の会」 に属します。 |
|
ある頃の山頭火 ② (高村昌雄) H11・10・01 3号
突然の休筆宣言である。いったいどんな「事情」があったのだろうか。年譜などを見てもこの「事情」となりそうな記事は見当たらない。
一方、「五句集」もその後何か月か休刊しているようである。次に保存されているのは「野分」
(大正元年11月号=通巻12号)で、この号から復活したようである。同時に山頭火も復帰している。
|
・ |
野分葉に何の虫鎌人不足いふ |
|
|
|
|
・ |
野分名残を飛ぶ小鳥葦の枯れ枯れに |
|
|
|
|
・ |
カラと晴れて野分跡柿赤う澄む |
|
|
|
|
・ |
野分海の遠鳴も徹夜読む床に |
|
|
|
が出ている。もう ー句あるはずだが、署名が無いので確認できない。その他、「雑録」に
がある。いずれも「全集」にも「大全」にも収録されていない。
ここで前にかえって「夏の蝶」、「夜長」、「爐開」、「河豚」に出ている句も紹介しておこう。
◎夏の蝶(明44・8=4号)
|
* |
夏の蝶勤行の瞼やゝ重き |
|
|
|
|
* |
後園ニ名花散んぬ夏の蝶を嘆ず |
|
|
|
|
* |
流藻ニ夢ゆら二なり夏の蝶 |
|
|
|
|
* |
カフエーにデカダンを諭す夏の蝶飛べり |
|
|
|
|
* |
吾妹子之肌奈まあかし夏の蝶 |
◎夜長(明44・11)
|
* |
酒に茶を夜長客席遠弾が |
|
|
|
|
* |
追放す邪宗徒もありて 夜長船 |
|
|
|
|
* |
除目洩れを 復た陸奥へ夜長し |
|
|
|
|
* |
孤独讃ず 偏狭を夜長星晴れて |
|
|
|
|
* |
湖畔きて 森の宿夜長啼く鳥か |
◎爐開(明44・12)
|
・ |
爐開や汝が恬淡に慊らず |
|
|
|
|
・ |
貧に處す 爐開や森の落葉雨 |
|
|
|
|
・ |
不平難ず 返書の爐開の比喩もあり |
|
|
|
|
・ |
家格また 爐開の古都に見る悲し |
|
|
|
|
・ |
安産の来状や爐開く朝 |
他に、
が「雑ろく」にある。
◎河豚 (明45・1)
|
・ |
「ふくなべ』の 文字赤し家並凹凸な |
|
|
|
|
・ |
捨身たゞ名残るもの 河豚と火酒あり |
|
|
|
|
* |
窓に迫る巨船あり 河豚鍋の宿 |
|
|
|
もう二句あるはずだが、署名がないので特定できない。
他に、
|
・ |
我に小さう籠るに耳は 眼はなくも泥田の田螺 幸もあるらむ |
という短歌と、前号で紹介した
が「雑ろく」にある。
は、「層雲(第2巻12号・大正2年3月号の「雲層層」・井泉水選)に「田螺公」の名で入選した句である。*のある句は全集・大全に収録されている句である。
なお、明治45年は7月29日まで、7月30日から大正元年となるから、「河豚」と「野分」は同年のものである。
「野分」の次は「寒さ」(大正元年12月・通巻13号)であるが、これには山頭火の句はない。「雑録」には「大正元年の暮田螺公」しとて「此度は例のヅポラで出句しませんでした」と記してある。
大正2年1月・通巻14号となる「初凪」にも句は出句していない。「雛録」に、1月27日夜の日付で、8ページにわたる長文を書いており、その中に、
|
|
深い穴がある。 |
|
|
|
|
|
冷たい風が吹く。 |
|
|
|
|
|
誰やら歩いてくる ーー |
|
|
|
|
|
灰色の靄の奥から、 |
|
|
|
|
|
とぼとぼと歩いてくる。 |
|
|
|
|
|
誰だ?シッカリしろ! |
|
|
|
|
|
ビクビクするな、 |
|
|
|
|
|
急げ、急げ |
|
|
|
|
|
愚図々々せずに |
|
|
|
|
|
急いで来い! |
|
|
|
|
|
危ない、気をつけろ! |
|
|
|
|
|
穴がある |
|
|
|
|
|
深いあながある、 |
|
|
|
|
|
暗い穴が或る。 |
|
|
|
|
|
落ちるぞ ー |
|
|
|
|
|
いっそ飛び込め! |
|
|
|
|
|
ー あ、彼は ー |
|
|
|
|
|
私はヅドンと倒れた!! |
という詩がある。(続く) ???